● いすの話-13
いすの話も2年目に入りました。今年は私が直接会ったことのあるデザイナーを中心にきままな話をテーマに取り上げます。いすのデザインは楽しいのですが、それだけではありません。事業としても非常に魅力的な分野で、人と人をつなぐ、幸せにする真っ当な素晴らしい事業です。そのことを証明した先輩の話をしていきたいと思います。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年02月01日(火) |
|
「デビッド・ローランド」
|
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
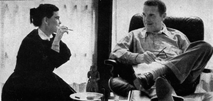
レイ・イームズ&チャールズ・イームズ

クランブルック・プレス

デトロイト郊外、クランブルック・アカデミー・オブ・アーツ

ラウンジ合板チェアー
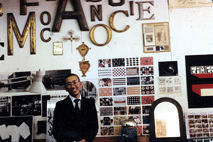
レイ・イームズに撮ってもらったスタジオ写真

「109」スタジオ、ロスアンジェルス郊外ベニス
2011年1月1日 井上 昇
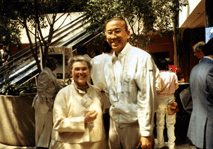
1986年ワシントンDCのカンファレンスの時
● いすの話-14
2月はデビッド・ローランドをとりあげます。デビッド・ローランドは800万台以上,生産され、今も作られている、たった1脚の椅子のデザインで、生涯お金持ちのデザイナーとしてアメリカでとても有名な椅子のデザイナーです。昨年、2010年8月13日、86才で亡くなりました。どんな椅子かといいますと、「GF40/4」というスタッキングチェアーです。今ではスチールのスタックングチェアーは沢山ありますがその原型をつくったのはデビッド・ローランドといえるでしょう。いまでもその原型の椅子「GF40/4」はやはり一番すばらしいと私は思います。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |

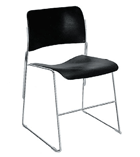 「GF40/4」
「GF40/4」 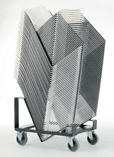
David Rowland 1-27-2010
デビッド・ローランドは1924年ロスアンジェルスで生まれました。第2次大戦ではヨーロッパ戦線で空軍に在籍。戦後、1949年、25才でイリノイ州のPrincipia College を卒業後、ミシガン州のクランブルックに入学、27才の1951年、修士卒業。その当時、クランブルックにはエーロ・サリネンが建築科、ハリーベルトイアが彫刻科の教授、フロレンス・ノル等も活動していて、大きな影響を受けていたはずです。クランブルックが一番輝いた1950年代に在籍しているのです。

デビッド・ローランド 1979年10月
巾600mm×奥行520mm×高さ760mm
122cm-76cm=46cm÷40=1.15cm。

ニューヨーク、フィールドトリップ
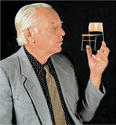
HOWE 40/4


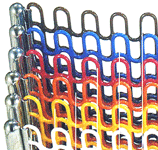
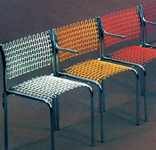
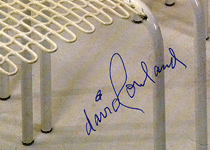
Thonet Sof-Tech Collection
2011年2月1日 井上 昇
● いすの話-15
3月はイタリアのマリオ・ベリーニ氏をとりあげます。マリオ・ベリー二氏はイタリアで数多い椅子のデザイナーの中でもエットレ・ソットサスや近年亡くなったジコ・マジストレッティー等と並んで巨匠中の巨匠の1人だと私はみています。建築の方でも有名ですが工業デザイン、家具のデザインでもとても魅力的な作品を手がけています。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年02月01日(火) |
| 「デビッド・ローランド」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
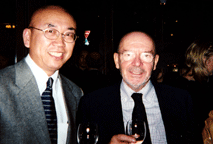

マリオ・ベリーニ氏と日本で ミラノでベリーニ氏の自宅で、1995年

ベリーニ氏の自宅

キャブアームレスチェアー

キャブアームチェアー


ブレークチェアー ティルブリーソファ
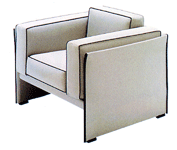
デュックソファ


Figura 2 Ypsilon
2011年3月1日 井上 昇

ベリーニソファ
● いすの話-16
4月は“めげないデザイナー”を紹介します。東日本大震災にめげない意味を込めて。アメリカでも有名なオフェスチェアーのデザイナー、ニールス・ディフェリエント氏です。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年02月01日(火) |
| 「デビッド・ローランド」 |
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
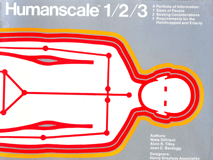
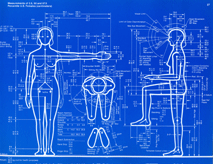
アメリカの人間工学
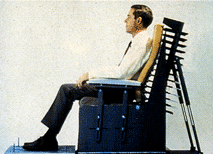
若き日のディフェリエント氏
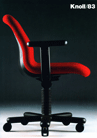
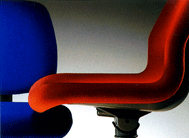
ディフェリエントチェアー(ノル社・1983年)
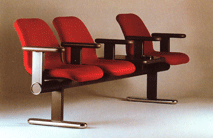
タンデムチェアー(ノル社)

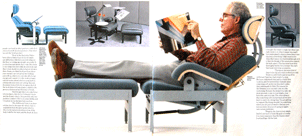
60歳代にデザインしたスナー・ハウザーマン社の椅子


Humanscale's
Freedom Chair
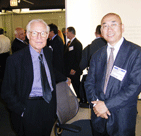

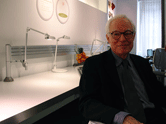
ディフェリエント氏と筆者(左)Liberty Chair(HS)(中)最近のディフェリエント氏(右)

Diffrient World Chair(HS)
2011年4月4日 井上 昇
● いすの話-17
1936年、ミズーリー州・セントルイス生まれ
正式名:William Eugene "Bill" Stumpf
(March 1,1936〜August 30, 2006)
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年02月01日(火) |
| 「デビッド・ローランド」 |
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |

Bill Stumpf(1936-2006)
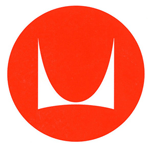
ハーマンミラー
 アーゴンチェアー(1976)
アーゴンチェアー(1976)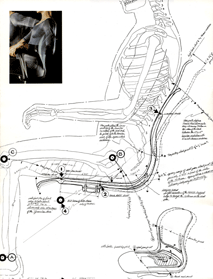
アクアチェアー
ヒューマンエルゴノミクス


アクアチェアー
 ビル・スタンプ氏
ビル・スタンプ氏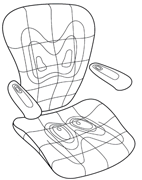
アーゴンヒューマンエルゴノミクス
�「デザインはジャズのようでなければならない。改善し発見し、人生の喜びや苦しみをブレンドして、何かすばらしいものに作り上げる」
「私は崖淵に立ったとき、自分の鼻っ柱を折られそうになったとき、そして再び無垢になれたとき一番働けます。ハーマンミラーは、私をそんな風に追い詰める 方法を知っています。D.J.DePree(ハーマンミラーの創業者)が最初に私に話してから何年も経ちますが、この会社は今だに『グッドデザインは単なる儲かるビジネスではなく、 グッドデザインはモラル上の義務である』ということを信じているからです。これはプレッシャーです。」
スタンプの闘いは、実際には1960年代に始まりました。「全てはあのウイスコンシン大学時代に戻ります。」大学の環境デザイン・センターで研究をし、また教えていた助手時代に触れながらこう述べています。


アーロンチェアー
2011年5月6日 井上 昇

エンボディチェアー
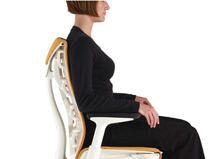
● いすの話-18
ブルーノ・マットソン
Bruno Mathsson
1907 - 1988
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年02月01日(火) |
| 「デビッド・ローランド」 |
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年07月04日(月) |
| 「ルッド・ティエセン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
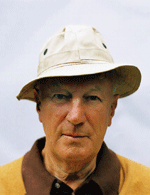
Bruno Mathsson(1907-1988)
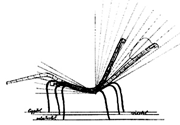
マットソンのアイデアスケッチ
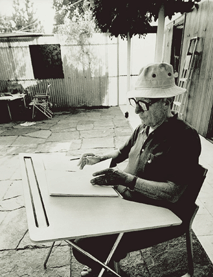


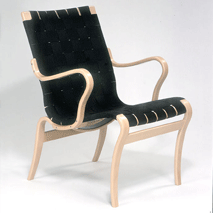

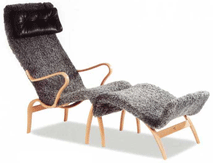
www.scandinaviandesign.com/bruno-mathsson-int/
写真は「Bruno Mathsson International」と(株)天童木工よりの引用です。

 フリッツハンセン
フリッツハンセン「スーパー楕円テーブル」

● いすの話-19
Rud Thygesen (1932 - )
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2011年01月01日(土) |
|
「レイ・イームズ」
|
| 2011年02月01日(火) |
| 「デビッド・ローランド」 |
| 2011年03月01日(火) |
| 「マリオ・ベリーニ」 |
| 2011年04月04日(月) |
| 「ニールス・ディフェリエント」 |
| 2011年05月06日(金) |
| 「ビル・スタンプ」 |
| 2011年06月07日(火) |
| 「ブルーノ・マットソン」 |
| 2011年08月05日(金) |
| 「ハンス・J・ウエグナー」 |
| 2011年09月04日(日) |
| 「ユーロ・クッカプロ」 |
| 2011年10月04日(火) |
| 「ドン・アルビンソン」 |
| 2011年11月11日(金) |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
| 2011年12月08日(木) |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
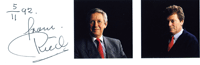
ルッド・ティエセン(左)
ジョンー・ソーレンセン(右)

King's Chair (Botium)1969
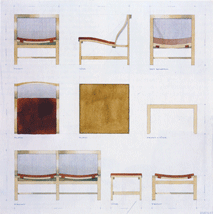
キングスチェアースケッチ
(1968年コンペ案)


 マグナス・オールセン社8000シリーズ
マグナス・オールセン社8000シリーズ マグナス・オールセン社 Twinシリーズ
マグナス・オールセン社 Twinシリーズ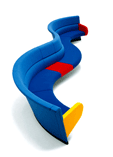
マグナス・オールセン社
Swingerシリーズ
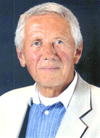
最近のルッド・ティエセン
● いすの話-20
Hans Jorgensen Wegner (1914 〜2007 )
| ● バックナンバー | |||
|
タイトル
|
|||
| 2017年のいすの話 | |||
| 2016年のいすの話 | |||
| 2015年のいすの話 | |||
| 2014年のいすの話 | |||
| 2013年のいすの話 | |||
| 2012年のいすの話 | |||
| 2010年のいすの話 | |||
| 2011年01月01日(土) | |||
|
「レイ・イームズ」
|
|||
| 2011年02月01日(火) | |||
| 「デビッド・ローランド」 | |||
| 2011年03月01日(火) | |||
| 「マリオ・ベリーニ」 | |||
| 2011年04月04日(月) | |||
| 「ニールス・ディフェリエント」 | |||
| 2011年05月06日(金) | |||
| 「ビル・スタンプ」 | |||
| 2011年06月07日(火) | |||
| 「ブルーノ・マットソン」 | |||
| 2011年07月04日(月) | |||
|
|||
| 2011年10月04日(火) | |||
| 「ドン・アルビンソン」 | |||
| 2011年11月11日(金) | |||
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 | |||
| 2011年12月08日(木) | |||
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
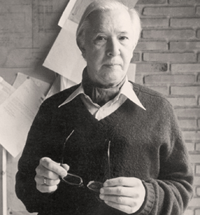
スタジオでのハンス・ウエグナー氏
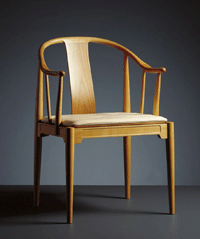
1944年 FH-4283 チャイナチェアー

1949年 PP-503 ザ・チェアー
 1953年 PP-250 パレットチェアー
1953年 PP-250 パレットチェアー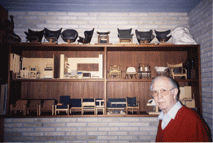
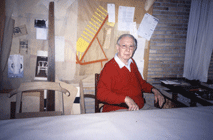 製図台前で一番最初にデザインした椅子を紹介
製図台前で一番最初にデザインした椅子を紹介 ウエグナー氏の製図道具と最初にデザインした椅子
ウエグナー氏の製図道具と最初にデザインした椅子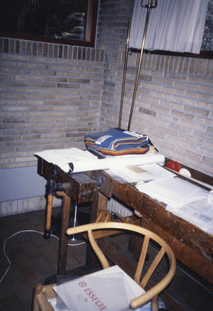
スタジオの中の工作台

1965年 PP-701 パイプチェアー

1950年 CH-24 Yチェアー
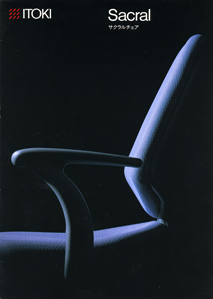
イトーキ サクラルチェアー
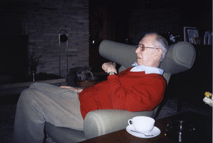
1960年 EJ-100 ザ・オックスチェアーに座って説明するウエグナー氏
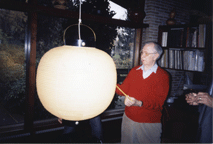
提灯の寸法を測るウエグナー氏
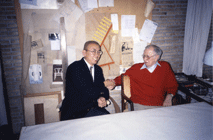
ウエグナー氏と握手。
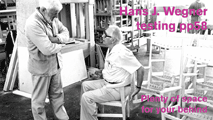
PPモブラーのアイナー・ペターセンとウエグナー氏
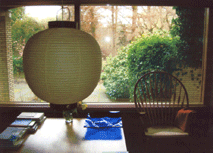
昨年デンマークにいる友人から送られてきた現在のウエグナー邸の提灯
話は長くなりましたがハンス・ウエグナー氏に生前お会い出来たことは私にとって宝です。
● いすの話-21
Yrjo Kukkapuro(1933〜)
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2011年01月01日(土) | |
|
「レイ・イームズ」
|
|
| 2011年02月01日(火) | |
| 「デビッド・ローランド」 | |
| 2011年03月01日(火) | |
| 「マリオ・ベリーニ」 | |
| 2011年04月04日(月) | |
| 「ニールス・ディフェリエント」 | |
| 2011年05月06日(金) | |
| 「ビル・スタンプ」 | |
| 2011年06月07日(火) | |
| 「ブルーノ・マットソン」 | |
| 2011年07月04日(月) | |
|
|
|
|
| 「ハンス・J・ウエグナー」 | |
| 2011年10月04日(火) | |
| 「ドン・アルビンソン」 | |
| 2011年11月11日(金) | |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 | |
| 2011年12月08日(木) | |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
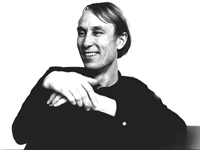
若き日のユーロ・クッカプロ氏

1963年 Karuselli(カルセリ)

 1960年 Swivel chair
1960年 Swivel chair remmi-1970
remmi-1970ユーロ・クッカプロは1933年フィンランドの東カレリア地方(現ロシア領)生まれ、現在78歳。私が会いましたのは2003年ですから70歳の時です。ヘルシンキ芸術デザイン大学の 教授・学長も歴任し、機能性を重視するデザインを教えたという教育者でもあります。
 fysio
fysio氏の優しさはそんな所からもきているのかもしれません。今回、いすの話で記事と写真を収集してみてその作品の多さにおどろきました。

experiment seat 1982

Finland Rocking chair

子供椅子

SOFA
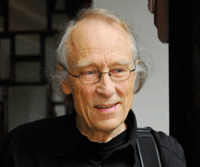
ユーロ・クッカプロ氏

ラウンジチェアー

ラウンジチェアー

最近の作品
● いすの話-22
Don Albinson(1915-2008)
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2011年01月01日(土) | |
|
「レイ・イームズ」
|
|
| 2011年02月01日(火) | |
| 「デビッド・ローランド」 | |
| 2011年03月01日(火) | |
| 「マリオ・ベリーニ」 | |
| 2011年04月04日(月) | |
| 「ニールス・ディフェリエント」 | |
| 2011年05月06日(金) | |
| 「ビル・スタンプ」 | |
| 2011年06月07日(火) | |
| 「ブルーノ・マットソン」 | |
| 2011年07月04日(月) | |
|
|
|
|
| 「ハンス・J・ウエグナー」 | |
| 2011年09月04日(日) | |
| 「ユーロ・クッカプロ」 | |
| 2011年11月11日(金) | |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 | |
| 2011年12月08日(木) | |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |
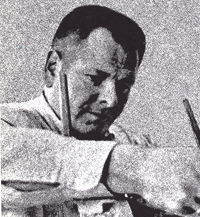
ドン・アルビンソン

アルビー・アルビンソン(左)と
ダン・クラマー(右から2人目)
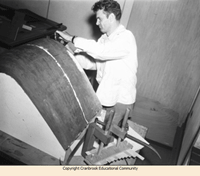
スタジオのチャールズ・イームズ
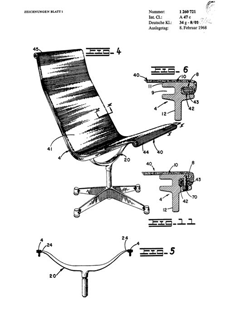
イームズと共同開発した
アルミニウムグループチェアー

イームズスタジオのドン・アルビンソン
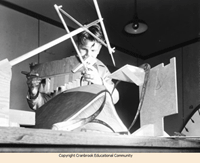
イームズスタジオのドン・アルビンソン


ハーマンミラー社製ソファコンパクト
1964年から1971年までの7年間、ノール社のデザインディレクターを務め、その後、70年代、彼はウェスチングハウス社のオフィスの椅子、家具システムの設計に携わり大成功を納めます。カリフォルニア大学ロサンゼルス校でも工業デザインを教えていました。1987年、72才の時、息子の名前「アルビー」と同じ名前のスタッキングチェアーを発表します。

アルビンソン・スタッキングチェアー


ウェスチングハウス社のオフィスの椅子
● いすの話-23
Giancarlo Piretti (1940-)
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2011年01月01日(土) | |
|
「レイ・イームズ」
|
|
| 2011年02月01日(火) | |
| 「デビッド・ローランド」 | |
| 2011年03月01日(火) | |
| 「マリオ・ベリーニ」 | |
| 2011年04月04日(月) | |
| 「ニールス・ディフェリエント」 | |
| 2011年05月06日(金) | |
| 「ビル・スタンプ」 | |
| 2011年06月07日(火) | |
| 「ブルーノ・マットソン」 | |
| 2011年07月04日(月) | |
|
|
|
|
| 「ハンス・J・ウエグナー」 | |
| 2011年09月04日(日) | |
| 「ユーロ・クッカプロ」 | |
| 2011年10月04日(火) | |
| 「ドン・アルビンソン」 | |
| 2011年12月08日(木) | |
| 「フランク・O・ゲーリー」 |

ジャンカルロ・ピレッティ

プリアホールディングチェアー

DSCスタッキングチェアーと
タンデムシーティングチェアー
フォルムもとても美しくこの椅子がでて来たときの衝撃は忘れません。イタリアにすごい椅子のデザイナーがいる。私がピレッティの椅子と出会ったのは家具メーカーに勤めている時でした。海外とのライセンス契約を積極的に展開し、社内で生産していたDSCスタッキングチェアーとタンデムシーテングチェアー。アルミをふんだんに使ったこの椅子は完成度が高く、美しく、合板バージョンもあってこんな椅子をデザインしたいものとあこがれもしましたし、そのシステマチックな構成に多くの影響を受けました。典型的な工業デザイン的椅子の代表例。アメリカに行ってもこの椅子はどこでも見かけ(国連の中)、ヨーロッパはもちろん世界中でヒットした。これもジャンカルロ・ピレッティの代表作です。

バーテブラチェアー"Vertebra"
私はジャンカルロ・ピレッティ程の椅子の天才はそういないと思います。特にその造形力。バランス感覚の良さ、とてもイタリア的な人の良いアーチストです。

バーテブラチェアーマネジメント

バーテブラチェアーエクゼクティブ
ピレッテイコレクションもその1つですが日本中で使われています。

ドーサルチェアー
エミリオ・アンバスとジャンカルロ・ピレッティ、2人の素晴らしいクリエーターから学ぶことは、いくら良いデザインをしてもそれだけで椅子のデザインが終ったわけではありません。まず特許、意匠登録、そこからが大変なのです。販売をする為の生産計画、品質維持、販促活動、カタログ、インターネット等々。椅子を販売しているメーカーは世界を問わず、そこに大変な努力と投資を行なっています。椅子のデザインは総合経済活動なのです。
今でもピレッテイがデザインした「バーテブラ」はお勧めの椅子の1つです。

ピレッティコレクション
● いすの話-24
Frank Owen Gehry(1929-)
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2011年01月01日(土) | |
|
「レイ・イームズ」
|
|
| 2011年02月01日(火) | |
| 「デビッド・ローランド」 | |
| 2011年03月01日(火) | |
| 「マリオ・ベリーニ」 | |
| 2011年04月04日(月) | |
| 「ニールス・ディフェリエント」 | |
| 2011年05月06日(金) | |
| 「ビル・スタンプ」 | |
| 2011年06月07日(火) | |
| 「ブルーノ・マットソン」 | |
| 2011年07月04日(月) | |
|
|
|
|
| 「ハンス・J・ウエグナー」 | |
| 2011年09月04日(日) | |
| 「ユーロ・クッカプロ」 | |
| 2011年10月04日(火) | |
| 「ドン・アルビンソン」 | |
| 2011年11月11日(金) | |
| 「ジャンカルロ・ピレッティ」 |
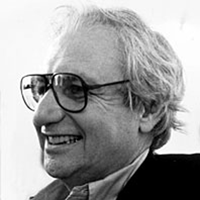
フランク・O・ゲーリー
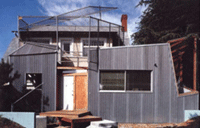
サンタモニカのゲーリー自身の自宅

段ボールの椅子

段ボールのソファとオットマン
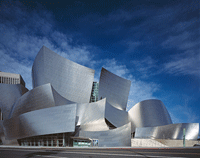
ディズニーコンサートホール
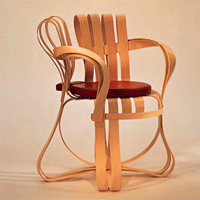
クロスチェックアームチェアー

パワープレイクラブチェアー
今月で私が実際にお会いした海外の椅子デザイナーの「いすの話」は終わります。

フェイスオフカフェテーブル