● 井上昇のいすの話-52 Part 4
デッソウ・バウハウスの戦後
デッソウ市はユンカース飛行機工場があったこともあって、第2次大戦末期連合軍に徹底的に破壊され市街の80%がガレキに化したという。ゼミでの東ドイツの友人が言うのには、連合軍はユンカースの工場そのものよりも周辺の民家を徹底的に爆撃したという。工場は後に使うことを考慮してあまり壊さなかったという。バウハウスは建物本体は壊されなかったものの、窓枠などは壊され、そのあとレンガで窓をふさがれ、昔の面影を若干とどめるだけになってしまって月日が過ぎていった。その後、AIFによって創立当時そのままの姿に復元され美しい姿を今は見ることが出来る。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |


ユンカースJu88爆撃機(左)、バウハウス校舎、右がセミナーハウス・左が建築専門学校(右)
私が参加した当時の東ドイツ時代は地上3階、地下1階の大きな棟のうち1楝は2年生のホーホシューレ・専門学校として使われ、回廊でつながれた旧学生寮、食堂、劇場とつながる本館は、AIFの管理下におかれ宿泊できるデザイン研修センターとしてつかわれていた。1階はバウハウスミュージアムとしてバウハウス時代の家具を含む資料が展示されている。
また劇場はバウハウスシアターとして一般の劇場と変わりなく使用されていた。私は2週間の滞在中、いくつかの中からパントマイムのみゼミの仲間と観劇した。この劇場はマルセル・ブロイアーの折りたたみパイプ連結椅子で知られている。舞台は小さいながら、設備も一通りそろっており、バウハウス時代有名なオスカー・シュレンマーの劇が上演されたところである。私が2週間宿泊した旧学生寮は2人部屋を1人で使わせていただき、各部屋にお湯と水が出る洗面シンクと机、キャビネットとコーヒーテーブルと椅子が3脚おいてある。各階に男女トイレがあり、奥に2部屋ずつ男女のシャワールームがあり、地下に管理人が住んでいた2階に小食堂を兼ねたミーティングルームがある。本館の3階にAIFの事務室があり、ミュージアムから食堂で働く人全部含めて、60人以上の人がここで働いていた。窓枠は全て黒、外壁及び内壁はほとんど白で統一された建物は美しく、特に窓がとても美しい。当初、私が想像してたよりも建物の規模が大きい。「建築における芸術の再統合」を目指したグロピウスの理想をこの建物に込めた建物であるだけに、位置、どこからも見える視点からも計算し尽くされた芸術的考慮が伺える。まさにアートのなかに住んでいる2週間だった。

デッソウ、バウハウス劇場
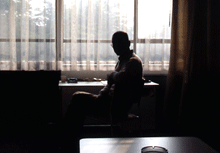
バウハウス寮内部
「フェルディナンド・クラマー」ゼミナール
若いときバウハウスで学び、一時アメリカに亡命し、東ドイツ帰国後、建築家、家具デザイナー、教育家として、数々の業績を東ドイツに残しセミナーの前年、亡くなったフェルディナンド・クラマーのデザイン理念「常に最も単純化された解決をさぐる」をベースに「住宅における多機能収納家具」開発をするのがこのゼミナールの目的であった。参加者は東ドイツからプロの建築家、教授、助手、学生、家具デザイナー、プロダクトデザイナー、ファッションデザイナーを含めた多士済々。海外からはチェコからアートインスティテュートに勤め、デザイナーでもあり、1人はphdの資格をもつ2人の女性(Ms.イヴァーナ・カプコバとMs、ダニエラ・カラソーバ)。ブルガリアとポーランドからはデザイン事務所に勤めるプロのデザイナー(キリル・ニコルチェフとヤセック・ミコラザック)ハンガリーからはミセスのプロデザイナー(アボタ・ハイツ・サラリー)オランダからは大学の教授で食器のデザイナーでもある年配のバン・マネン氏。そして日本から家具デザイナーの私。20歳から60何歳かの大学教授まで、平均年齢は38歳ぐらい。専門はいろいろであったが建築関係と家具をふくむプロダクトデザイナーが多かった。

「フェルディナンド・クラマー」
ゼミナール

「フェルディナンド・クラマー」
ゼミナール
東ドイツの参加者の中には2人のドクターを持った人も含まれていた。海外からの参加者は私を除いて東ドイツに留学経験を持っている人が多かった。ゼミは全部ドイツ語ですすめられたが、フランス語と英語の通訳を用意してくれていたので作業に支障はなかった。ゼミに参加した東ドイツの若い人は結構英語を話せる人もいて、4カ国語を話せるオランダのバン・マネン氏ともにずいぶん助けてもらった。ヨーロッパに行くと母国語の他に2〜3ヶ国語しゃべれる人が多い。英語でもなんとか事は足りるが、後にワイマールやライプチッヒを旅行して一部のインテリを除いて英語が全然通じないのにはかなり困った。英語の他にもう一カ国語、話せる事必要なようである。
バウハウスの1日目
空港からバウハウスに到着した日はゼミナールの始まる前日・日曜日だったので参加者は誰もいず、昼食のあと、バウハウス館長のブルマイスター氏がデッソウから東へ車で40キロばかりの所にある宗教改革者、マルチン・ルッターで有名なウィッティンベルグへ案内してくれた。
エルベ川のほとりにあるウィッティンベルグは古い城砦都市である。ルッターが1517年に95ヶ条の誓文をドアーに打ち付けた宮廷教会や、聖母教会、ルッターの住居・大学跡などの旧跡を見て回った。宮廷教会に続く公園の入り口にモニュメントとして台の上に第2次世界大戦のときのソ連軍戦車が据え付けられているのには少なからず驚いた。ルッターゆかりの教会の前に赤軍戦車。ここがソ連圏であることを思い出したがブルマイスター氏はあまり良い顔をしてなかった。


ウィッティンベルグ ウィッティンベルグ市内
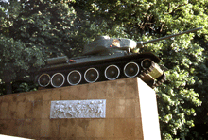
ウィッティンベルグ入口のソ連軍戦車
ゼミナールの主旨は東ドイツ工業デザイン局から頂いた資料を翻訳したものをそのまま掲載した方がわかりやすいと思うのでそのまま載せます。そして2週間の滞在記録は帰国してデザイン誌に寄稿した文章をそのまま掲載させて頂きます。長くなりますが一番当時のバウハウス滞在を理解して頂く上で適当と判断する故です。
Dr.ハインツ・ヒルディナ(作成:ゼミナール指導教授)
この工房ゼミナールは工業デザイン局主催でデッソウ・バウハウスで5月26日から6月6日(1986年)の間催される。
■ 要望
このゼミナールは「住いにおける収納」問題に対する設計上の解決と理念とをもたらすという課題をおっている。ここでの収納の対象というのは、衣服から家財道具、家具、書籍、絵画、写真類、趣味や家事のための道具や材料、そして収集品に至るまでのもの、つまり住いの内の空間や容器の中に一定の場所をしめざるを得ないものすべてが考えられねばならない。
設計にあたっていろいろなスタイルで住まう住民、そして住まうということについてのイメージの違いと言ったことが考慮される必要がある。ゼミナールの目標はこの十余年来DDR(東ドイツ)では100万市民がかってない規模で新しい住いに移っておりさらに住いを新たに確保したり整備したりする大衆的な過程は1990年まで続くであろうという状況によって規定されている。同時に日増しに増える物をどう処理してよいか誰もが困惑するするようになってきているということも重要である。
第2にゼミナールは建築家・デザイナー・グラフィックデザイナーであったフェルナンド・クラマーの個性によって規定されている。かれのデザインは材料と空間の経済・節約を旨とするが、しかしそれは対象を貧弱するものではなく、むしろ使用の洗練をこそもたらすものなのである。
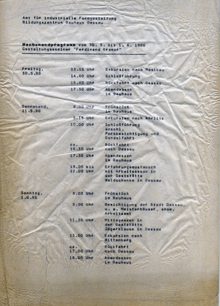
ゼミナールの予定表カーボンタイプ

バウハウス2階内部から玄関を望む。
■ 状況
住まいにおける貯蔵空間の増大には限界がある。この条件のもとでは、新たな貯蔵空間を発見することばかりでなく、収納問題を改めてじっくり検討することが肝要といえよう。収納ということには事物をすばやくかつむだのない処理の可能なように収納するにはどうしたら良いかという問題も含まれる。そしてここでいう処理ということには一方ではその事物の道具的側面、つまり、取り扱いということが考えられ、他方ではその芸術的側面ないし空間におけるフォルムの側面、つまり直感にむけられた処理ということでもなければならない。住むということについてのイメージの違いによって何が隠され何が人目にさらされるべきかということに対する対応は異なるものである。この問題はデザイン課題としての(空間ー対象)関係、つまり容器としての(空間ー対象)関係、つまり容器としての空間および空間の中での貯蔵という関係に通じているのである。
今回の設計課題「収納」にかかわる問題は住居の平面図から容器内の仕切りまで及ぶ。収納はまた諸対象そのものの造形にとってのテーマでもあってここには特に以下のような諸問題が含まれている。
- 諸対象の使用状態と収納状態とは互いにどのようにかかりあわせることことができ、諸対象の形態あるいは量を折り、差し込み、積み重ねなどをとおしてどのように収納容易ならしめうるか、また逆に使用に向けてはどのように形をかえ量を大きくすることが出来るか
- 手に持ったり収納したりということを設計の土台としたような場合(例:壁にとりつけたケースに掛けておくようになっている髭剃り機)そのことによって形態の質にどのような改革、発展が生じうるか。
- 新しい材料、新しい使用方法が収納の仕方をどのように変えうるか。(以上)
5月26日(月)11:00 受付
14:00 オープニング
15:30 ゼミの説明
16:30 ローラ・クラマー女史による
プレゼンテーション
5月27日(火) 8:00 全体討議、グループ分け
5月27日(水) デザインワークショップ、グループ討論
5月29日(木) 同上
5月30日(金)10:30 グループ別中間発表
5月31日(土) 9:15 ボーリッツ公園ピクニック夜パーティー。
6月01日(日) 9:00 デッソウ市内見学
13:00 ウィッテンベルグ見学
6月02日(月)11:00 デザイン ワークショップ
6月03日(火)11:00 同上
6月04日(水)11:00 同上
6月05日(木)11:00 グループ別作品展示及び説明
14:00 審査・表彰
16:00 パーティー、解 散
6月06日(金) 7:30〜 8:00 朝食
10:00〜10:30 コーヒーブレーク
12:00〜13:00 昼 食
15:00〜15:30 コーヒーブレーク
18:00〜19:00 夕 食
5月26日〜5月29日の夕方(19:00〜20:30)
外国参加者の作品プレゼンテーション
以上のような趣旨、テーマ、日程で2週間のバウハウスセミナーは実施された。
ゼミナール1日目
月曜日に始まったゼミナールは別表のようなスケジュールで始まった。オープニングのあと教授でもあるローラ・クラマー女史を囲んで、バウハウス3階の階段の踊り場で記念写真を撮る。

バウハウス内ミュージアム


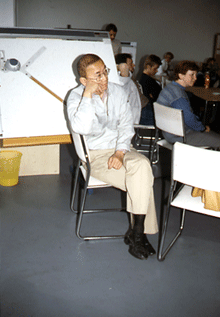
ゼミナール風景(上3枚の写真)

ゼミナール参加記念写真:バウハウス校舎階段で
その後、Dr.ヒルディナともう一人の教授によるゼミナールの全容が説明され、続いてローラ・クラマー女史によるフェルディナンド・クラーマーの建築及び家具プロダクトの作品とデザイン理論のスライドを含めたプレゼンテーションがあった。
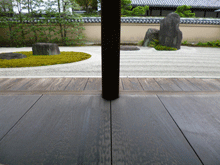
京都の日本庭園

自分の作品のプレゼンテーション
夕食後7時半からスライドによる外国からの参加者によるプレゼンテーションがあり、トップバッターとして私が最初に行った。これは一週間、夕食後毎日続く。又、東ドイツの何人かもこれに加わった。私のスライドは初めに、京都の竜安寺、金閣・銀閣寺、詩仙堂や民家を含む京都の日本間、庭、日本食などの器を紹介して、日本の住宅の畳を中心とするモジュールの仕組み、及びその多機能性を説明した。次に私の作品である、家具とりわけ事務用OA関係の椅子、及びロビーチェアー、オフィスインテリア、ディスプレイ、プロダクトデザインのスライドをプレゼンした。途中、日本の住宅に対する質問や私の専門に関することで質疑応答で当初の30分の予定が1時間以上もオーバーしてしまった。過去、現在も含め日本に対する関心の高さは想像以上である。
ゼミナール2日目
グループ分け。東ドイツはソ連に次ぐ第二の工業国でその発展はめざましい。日本の国土の1/3強のところに1670万人が住んでいる。
日本と違って北部は平野なので、農業に適している。経済の発展にともない住宅も建てられ、ここ10年で100万戸の住宅が建てられつつある。それに伴い住宅事情も狭くなってきている。そこで、従来のような家具ではなくより効率的に多機能に使える新しい考え方に基づいた家具が必要とされて来ている。これらのニーズにいかに答えるかが今回のゼミナールの目的である。今回のゼミナールの成果は今後の住宅に生かされる。今回はグループ分けを議論するうち、次の3タイプに分けられる事になった。
- 住宅の設計から収納を考えていくAグループ
- 家庭で使われる食器や道具を含めた家具及び収納家具をテーマに考えるCグループ
- その中間のグループB
と3つに別れ各自の希望するグループを分けた結果、Aグループが多かったのでAグループを2つに分けA-1・A-2とした。私はグループCに入った。A1・A2グループは建築関係の人が多かった。各グループはほぼ7人ずつ。午前グループ分けして午後からは各チームによるディスカッション。
Cグループはまとめ役としてバン・マネン氏。氏はオランダからシトロエンに乗って車で来た。東ベルリンまで8時間で着くとのこと。ベルリンからデッソウまで2時間であるから10時間で来た事になる。朝出て夕方着く。ヨーロッパの狭さを改めて実感すると共に戦争の時は大変だなと思った。メンバーは47歳のライプチヒから参加したプロの建築家スダウ氏。東ベルリンから参加した建築科の30を少し過ぎたばかりのハインツ・シャウス氏、あと同じく東ベルリンから陶器デザイナーで大学院生のエリカとファッションデザイナーのアンドレア。そして主婦兼インテリアデザイナーのDr.ヘルガ・パテッツと私の7人である。ジョークを飛ばしながらブレーンストーミングし、つまり収納する為の考え方やキーワードをどんどん出し合い、その中で使えそうなものはグループの共通のワードとして拾いだす。このあたりは日本で新しいものを開発する時、問題点をはっきりさせるためにやるディスカッションと全く同じである。
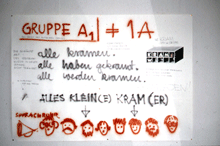
セミナーグループ分け

我々のCグループ:エリカ、スダウ、ヘルガ
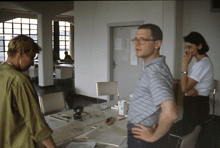
我々のCグループ:アンドレア、シャウス

我々のCグループ:バン・マネン氏とエリカ
グループで仮定のアパート住宅の平面図を決め、夫婦と子供2人の標準家庭を設定し、リビング・ダイニングルーム、キッチン、バスルーム、ベッドルームとユーティリティーのアパートメントのレイアウトから始めてゆき、グループとしてのプランを決めた上で各自おのおのの具体的なテーマを決めていった。食事時もコーヒーブレークもグループでとることが多かったし、夜は夜でワインやビールを飲みながらワイワイと遅くまでやり、他のグループに出かけていって話し込んだりした。Dr.ヒルディナやブルマイスター氏らのゼミの運営グループはそれぞれのグループに首をつっこみ問題のテーマから外れないようにしていた。
午後1時に各グループが一堂に集まりグループ別に中間発表をした。金曜日の中間発表が終ると東ドイツの参加者はほとんど土日の休日を取り自宅に帰っていった。金曜日の午後、インターナショナルグループは近くの旧領主の夏宮を見に行った後、寮の食堂で飲み放題のビールとワインで遅くまで歓談する。このとき折り鶴教室を開き皆で作る。
雨の中、3台の自動車に分乗しAIFの人達の案内でボーリッツ公園へ行く。途中田園のの村々をとおり農村地帯を抜けると東ドイツでも屈指の公園が見えてくる。ヨーロッパ大陸ではじめて英国風庭園を模倣して作られたものでいくつかの大きな湖と建物、教会が調和し美しい。バウハウス時代カンジンスキーやクレーが好んできたところである。ここは有名な公園なので沢山のハイカーが来ていた。

ボーリッツ公園
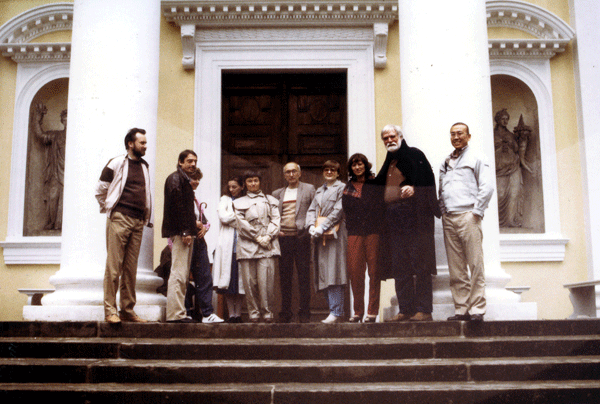
ボーリッツ公園
その中に黒人の人とか東洋系の人も混じっているグループもあった。黒人の人はアフリカの人が多いようだ。東洋人は主としてベトナム、北朝鮮、中国の人らがほとんどで共産圏の人たちがツアーで来ているのであった。東ドイツの貿易の70%がコメコンで占められる。人の交流においてもこのとき共産圏と資本主義国と全く別れているのが興味深かった。ゼミの友人に聞いたところ、砂糖はキューバ、コーヒーはニカラグア、紅茶はベトナム、中国は穀物と交流が人・物ともはげしく、丁度我々がアメリカやヨーロッパを身内意識で考え気軽にビジネス旅行するように、かれらもまったく同じような感じで共産圏の中でつきあっているのが私にとって興味深かった。我々もあまり共産圏の国々を知らないように、彼らも又、資本主義国の国々をあまり知らないことは同じでこれが問題を複雑にしているのではないか。夕方、デッソウのレストランで会食、同じレストランでたまたま結婚式の披露宴とぶつかり、途中から一緒になって踊る。新郎新婦に折り鶴を折ってプレゼントし会の盛り上げに一役買う。ヒロシマの平和のシンボルというこの折り鶴のことはよく知っていて喜ばれた。このあと店を移して午前までビアホールでカンパイ。


デッソウ市内のレストランで(左) デッソウ市内のレストランと結婚パーティー(右)
皆と離れて私は朝早くデッソウ駅を発ちライプチッヒ経由でワイマールに着く。インターナショナルグループはウィッテンベルグへいく。切符はAIFで用意してくれる。東ドイツの汽車はのんびりしている。3時間でワイマールに着き、ゼミに参加していてワイマールに住み旧ワイマール・バウハウスの校舎を使っている5年制の建築学校の助手であるヨハン・ブァハン氏に出迎えてもらいワイマールを案内してもらう。ワイマール共和国の首都でもあったワイマールは今、大学町として賑わっているこぢんまりとした都市である。ちょうど日本の京都のような所。ワイマールはゲーテ、シラー、ハイネ、そしてリストが居たところとしても有名で史跡があちこちにある。J.S. バッハもこの町に若いとき9年間住んでオルガン曲を沢山作曲している。ヒットラーが建てた建物も残っている。

ワイマール市街
ヴァンデヴェルデの設計によるワイマール・バウハウスを訪ね、その時の実験住宅、ゲオルゲ・ムッヘとアードルフ・マイアーのデザインによるアム・ホルンの住宅も見る。ワイマール・バウハウスは建築のホッホシューレとして使われていて屋上のガラスがカーブからくの字になった意外は全く当時のままだと言う。アム・ホルンの家は今も人が住んでいて、中央はミュージアムとしてバウハウス資料が展示してある。この住宅は外見はシンプルであるが中に入ってみて素晴らしい建物だと感銘した。2つの四角を積み上げた形のこの家は中央は吹き抜けの居間になっていて、まわりに部屋がある。せり上がった居間の天井サイドより光が家にあふれ何とも言えない開放感を感じる。とても65年以上たった住宅とは思えない。現在でも住んでみたいと十分思わせる住宅で評判になった理由がよくわかった。この建物は実際に見てみないとこの良さは写真だけではわからないだろう。
昼食と夕食をブァハン氏の家でご馳走になり、氏の新しい住居を見せてもらう。ワイマールは古都だけにいろいろ建築制限があり、通りに面した表側の建物は伝統的なものしか建てることは出来ないがその内側で道路から一歩入った表から見えない所はモダンな建物も建てられるということである。この建物をみても住宅デザインのレベルが高いことがよくわかる。今、ワイマールは都市開発の真最中で古い建物を補修しながらきれいに塗装し直し、内側は全くモダーンにし直している。町並みがとっても奇麗なのはそのせいである。外側だけ見ると誤解する。中に入ると見違えるように奇麗である。こうして2週間プログラムの一週間は終った。
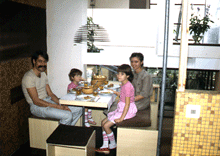
ヨハン・ブァハンファミリー

アム・ホルンの住宅

アム・ホルンの住宅の内部

アム・ホルンの住宅の模型
● 井上昇のいすの話-53 Part 4
ゼミナール・2週目
ゼミナールも2週目に入り月曜日から再び作業がスタート。昼食までには東ドイツの人もほとんど帰ってきた。忙しい人は仕事を片付けてから家からやってくる。月・火・水とグループ別仕事の中でさらに個々人のテーマを決め作業を進める。1週目の終わり頃にはテーマを決めつつあったが、2週目に入ってからは脇目も振らず、木曜日の午前11時の提出に向けて急ピッチで仕事する。ほとんど夜の11時前に寮に帰ることはない。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
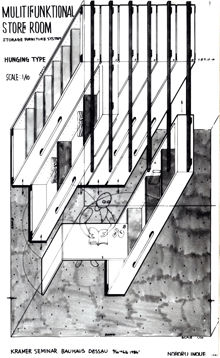
井上の作品
すき間一杯のキャビネットが手前に出てきて使わない時は収納する。
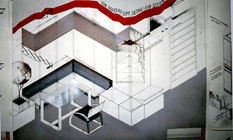
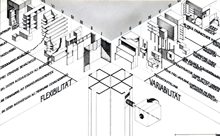
各グループパネル作品 各グループパネル作品
審査会と表彰式
オランダからのマネン氏はバスユニットシステムを、スダウ氏は照明と浴室内のドライヤーを、ハインツ氏とアンドレアはボックスタイプシステム収納を、エリカはコンパクトにスタッキング出来るシステム食器セットをヘルガは収納ケースをそれぞれ提案した。そして午前中、昼食前に本館3階の展示室に4グループとも展示した。木曜日午後に東ドイツの各地から6人ばかりの審査員が来て、4グループのメンバーがそれぞれに審査員にグループのデザイン意図、及びそれぞれ個人の一人一人の作品を説明する。そのあとゼミナールのメンバーが会場から締め出され、午後に到着したAIF長官ケルム氏を交え審査員だけで2時間以上念入りに審査する。
4時過ぎ、ブルマイスター氏の総評の後、はじめ1等2000マルク、2等1500マルク、3等1000マルクと順位を決めるはずであったが、審査の結果甲乙つけがたく、全チームに一律2400マルクずつ賞金と賞状がケルム氏のコメントをそえて授与された。
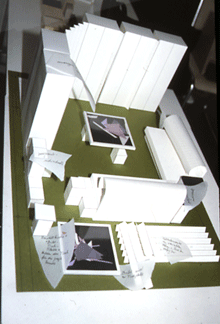
各グループ模型展示

マスコミに取り上げられたプロバガンダ写真。ケルムAIF長官、オランダからの参加者マネン氏、日本から私、東ドイツのスダウ氏。



審査委員と右端バウハウス館長その隣AIF・ケルム長官(左写真)
審査講評:バウハウス館長ブルマイスター氏(真中)
表彰式:ケルム長官からブアハン氏へ(右写真)
ゼミナール以後・ライプチッヒへ
金曜日朝、早い人は木曜日に三々五々帰り始め、外国の参加者と別れを惜しんで再会を約して別れる。私はスダウ氏と共に金曜日朝、AIF職員のルポレヒトさんにライプチッヒまで車で送ってもらい、スダウ氏の案内でユーゲント・スティールの建物、バロック、ロココ様式のもの、そして古いビルを改装している現場や彼の作品を見学した。バッハの居たトーマス教会にもより近くの店でバッハのレコードを買う。夕方寮に帰る。ブルマイスターさんが待っていてくれて夕食を市内のラートハウス(市庁舎)の地下でとる。夜はダンスの社交場になっていて、若い人、中年の人達が週末なので思い思いの洋装で着飾って踊っていた。アメリカや日本のように華やかではないが皆生活をエンジョイしているように見えた。ブルマイスターさんと話しているとき氏が言うのには東ドイツにはデザイナーと呼ばれる人がファッションや工業デザイン、そしてクラフト、グラフィックを含めてたった2000人しか居ないという。それが問題の第1。

バッハがいたライプチッヒ・トーマス教会内部
おわりに
東ドイツで学んだことは多かった、1つにバウハウス運動がドイツを抜きにしてはやはりあれだけのものを残さなかったろうと、現地へ行ってドイツの人と話していて感じたことである。ドイツの人が持つかたくなまでも本質を見極めようとする文化の背景と勇気とそれを常に潰そうとする勢力。バウハウス運動は近くの外国からも沢山の人が参加したが中心はやはりドイツ人である。インターナショナルな自由な雰囲気も大いにバウハウスをもりあげたであろう。7月21日夜、オスカー・シュレンマーの舞踏劇のフィルムを見る機会があった。西ドイツで当時そのままのコスチュームを再現し撮られたのだがすばらしいものであった。マルティン・ルッターの改革がその後の世界を大きく変えたように60年経った今もバウハウスの魅力は人々をひきつける。本当に本質的なものは時間が証明してくれる。そして時代の責任は常に当事者の次世代が負うものであることも少しく知ることが出来た。日本の今の繁栄もそれを享受している我々が作ったものでなく、我々の親の世代の結果を得ているものだということも解った。ということは親の世代の戦争は祖父の世代のつけが回ってきたことになる。今回なんといっても最大の収穫は東ドイツおよび東欧の人々と知り合い友人が出来たことである。そしてこうした小さなお互いの本音論が次世代の平和につながっていくことを知るのである。今回のゼミナールに行くことにいろいろお手伝いしてくださったJIDAの理事長はじめ理事と事務局の皆様はじめ、この情報を直接もって来てくださり助けていただいた岩手大学の長田謙一さん、そしてAIFのブルマイスターさんはじめ職員の皆様に深く感謝します。(JIDA 井上 昇)
以上が帰国してから1987年、今はありませんが『FP』というデザイン誌に寄稿した文章をそのまま転載したものです。

ゼミナールの時のバウハウス
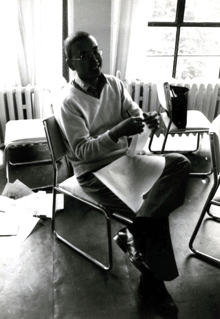
バウハウスセミナーで仲間が撮ってくれた写真

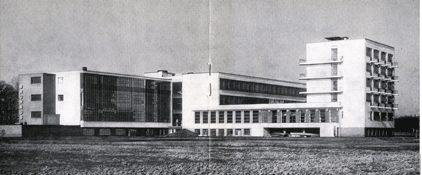
戦前のバウハウス時代の教員(左写真)と戦前のバウハウス全景(右写真)
左から校長ワルター・グロピウス、パウル・クレー、ライオネル・ファイニンガー、カンジンスキー夫人、副校長ワシリー・カンジンスキー
今、バウハウスセミナーを振り返って
今思うと、このバウハウスセミナーのたった3年後1989年、東ドイツ・ライプチヒのニコライ教会での「平和の祈り」から始まった言論・政治活動・出国の自由を求めるロウソクを手に持った静かなキャンドル行進が次第に拡大し教会外へのデモ行進へと発展。1989年10月9日、7万人にも膨れ上がった参加者が広場や通りを埋め尽くすという大規模なデモになり、東ドイツ平和革命の口火が切られることになります。それはチェコスロバキアの解放につながり、ハンガリーも独立。瞬く間に東ドイツ全土に広まった反体制運動はそのたったの1ヶ月後にベルリンの壁を崩壊させ、そのわずか1年後の1990年には東西ドイツが統一。ニコライ教会は「東西ドイツ統一革命の出発点」として世界史に記憶されます。実はそのニコライ教会の最初のキャンドル行進のなかにバウハウスセミナーで同じグループでその後親しく友人としておつきあいしていた建築家のスダウ氏が入っていたことをドイツ統一後、再訪したライプチッヒで当人から直接、熱く聞くことが出来ました。彼には奥さんの他に2人の息子さんがいて石の彫刻家。主に歴史的建築の修復の石の彫刻が主な仕事で日本にはない仕事。その息子さんと共にデモに参加したのですが、決死の覚悟での参加だったと言います。それを奥さんがとても心配して精神的にダウン、一時的にうつ病になったと聞かされました。それだけ共産圏でこのようなデモをすることは決死の覚悟が居ることは平和な日本では想像外の決断でしょう。ベルリンの壁を乗り越えようとしてどれだけの人が殺されたか。この時の東ドイツにはまだ密告制度が強く残っており自由のない時代です。このニコライ教会、後で解ったことですがバウハウスのセミナーの後半ライプチッヒに行った時バッハのトマス教会とこのニコライ教会をスダウ氏が案内してくれていたのでした。その時は随分立派な教会だなと思いましたがなんといってもバッハのトマス教会に夢中でしたから、ニコライ教会は余り記憶に残りませんでした。この写真が東ドイツ時代に撮ったニコライ教会の写真です。トマス教会よりむしろ立派な大きな華やかな教会でした。東ドイツの国としての崩壊、東西ドイツの統一、それに続くソビエト連邦の崩壊とそれまでソ連に抑圧されていた周辺の国々が独立し、現在のウクライナとロシアとの紛争にまで至るその出発点がこのライプチッヒのこのニコライ教会の平和行進が始まりでした。その中にバウハウスセミナーの仲間もいたのでした。東ドイツ時代の2週間の共産圏生活のなかで短期間ではありましたが西側の国では絶対経験できない色々な体験をしました。今となっては貴重な経験です。それは秘密警察の存在です。バウハウス寮での夜、海外を含む滞在者は夜、集まって西ドイツから入ってくるサッカーの試合に夢中でした。国境は閉じても電波は国境を超えて入ってきます。

東ドイツ・ライプチッヒのニコライ教会

ニコライ教会天井

ライプチッヒ、ユーゲントスチールの建物
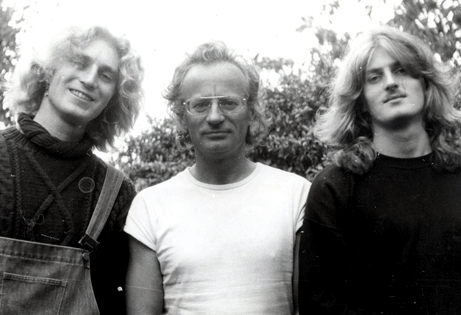
スダウ氏と2人の息子
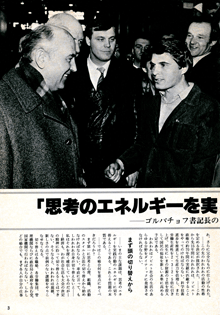
ソ連最後の大統領:ゴルバチョフ

バウハウス寮

バウハウス寮内部室内

東ドイツ時代のバウハウスゼミナール

東西ドイツ統一後再びデッソウ・バウハウスへ

チェコ・プラハ市内


プラハ市内、中央のレストランで食事をした。(左写真)
カレル橋、プラハで一番の名所(右写真)
● 井上昇のいすの話-54 Part 5
17年目の「椅子塾」
「ロイヤルティーよりもっと良い仕事」に戻ります。今年に入って4ヶ月ほど「いすの話」UPしませんでした。1月から私の会社の「腰の椅子 Awaza」の直営ショールームを西新宿にあるパークタワーOZONE4階に開設しました。「椅子とテーブルのギャラリー」です。新規ショウルームですのでスタートしてから気持ち的に余裕持てず、この「いすの話」も結果的にお休みしてしまいました。現在は7月です。スタートして6ヶ月過ぎ7ヶ月目に入りました。ショールームも軌道に乗り?余裕がでてきたところです。実は「椅子塾」も1999年開塾以来初めて休講にしました。17年目に入り75回目にして初めてです。その「椅子塾」も4月から再開し改めて75期生を迎え授業再開しています。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |


都庁から見えるパークタワーOZONE(左側写真) 「椅子とテーブルノギャラリー」OZONE 4階(右側写真)
両方とも丹下健三設計のビル
椅子塾と「腰の椅子 Awaza」の開発と販売
パークタワーOZONE4階の「椅子とテーブルのギャラリー」は私の会社 株式会社いのうえアソシエーツのデザイン・製造・販売している「腰の椅子 Awaza」シリーズを全種、展示し、見て座って頂く為に開設しました。最初の「Awaza-1」を発売してから10年目という区切りもあります。では椅子デザイナーの私がどうして椅子の販売に携わることになったか!今月からの「いすの話」は椅子のビジネスとも関係ありますので椅子のデザイナー自身がなぜ椅子の販売に関わることになったか?その経過を話すことにいたします。それは私の主宰している「椅子塾」を抜きに語れませんので「椅子塾」のことから話に入ります。



Awaza-1 Awaza-LD Awaza-LDR
1999年1月「井上昇の椅子塾」スタート
「椅子塾」は1999年1月、南青山で株式会社いのうえアソシエーツのスタジオを会場にスタートしました。私が55歳の時です。それまでも、社会人の為の「椅子の教育」の必要性は感じていましたがやるとしても60歳からと考えていました。それはこんな理由です。アメリカのクランブルック美術大学院に留学し、アメリカの美術学校と日本の美術学校の教育の落差に体験してみてそのあまりの違いに危機感を感じたことによります。これは言葉で説明しにくく、実際にアメリカに留学して数年過ごしてみる体験なしには日本にいただけでは理解できないでしょう。私はそう確信します。

クランブルック・アカデミー・オブ・アーツ

デザイン科におけるチャールズ・イームズの授業風景
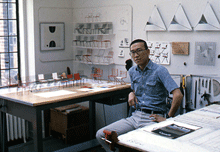
デザイン科スタジオにて
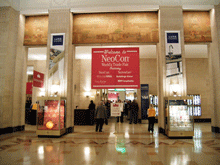
シカゴ・NEOCON全米家具見本市
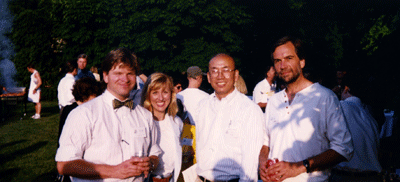

クランブルックの後輩・右端-ダン(左側の写真)、ダンのパブリックチェアー評価が高い。(右側の写真)
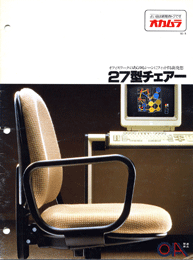
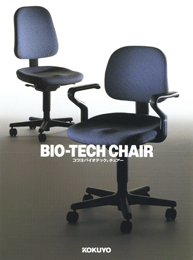

インハウス時代のO社のOAチェアー(左側)、K社のOAチェアー(中央)、I社のOAチェアー(右側)
日本の体型の椅子を学べる「場」
ライフワークとして椅子のデザインに携わることは決めていましたし、椅子のデザインの仕事がないとしたら「椅子のデザインを教える」仕事を始めようと決めていました。その最大の理由はアメリカ的「クランブルック美術大学院」の実践的デザイン教育を日本でなんらかの形でやりたいこと。人間年齢を加えていくと自分が経験したノウハウを他人に伝え社会のお役に立ちたいと願うことは自然の流れだと思います。大学で教えることも機会があればとの思いもありましたが日本では金銭的にはほとんど不安定なアルバイト的「非常勤」の仕事はあってもアメリカの年契約で教える教授職と違って、仕事があまりできなくても定年まで解雇されることのない日本では「教授職」としての就職の機会は年齢的にもほとんどありません。
それと反比例して、デザイン業ばかりでなく若い人の働く環境がひどい状態になっています。フリーターが65万人もいるという報道もありました。日本にとって一番の資源は「人材」です。その貴重な人材が埋もれている。アメリカでの体験から日本人は優秀な人材の宝庫です。その一人でも良いからなんらかの形でサポートしたい。そして同年代の世代は定年後、中国に行ってノウハウを教えている。なんで日本で日本の若者に教えないのか!家具業界もどんどん中国に生産の依頼を移し、日本の家具会社が危機に陥っている。日本の家具会社が無くなったら家具を作りたいという人の職場が日本に無くなり、家具デザイナーの仕事も日本でなくなる。これはなんとかしなければ!我々の叩き上げの日本人の世代が日本の将来を担う若者を鍛えなくて誰がやる。そして、いずれ中国に製造の依頼をしていても中国の人件費が高くなってきたら必ず又、製造の拠点は日本に戻ってくる。そのとき日本に家具を作る事業所、人材がいなかったら良くない。他人はどうあれ私は日本で日本の求めてくる人に、年齢、学歴、経験、男女に関係なく私の専門の椅子のデザイン、設計を学べる「場」を作ろう。それも短期で専門的に高度で集中的に学べる、実務家が教える「場」を。
世紀を超えて「椅子塾」
おりしも20世紀も終わりにさしかかっていて21世紀が始まる。20世紀と21世紀をまたいで、超えてその人材教育の「場」を作ろう!南青山の高い賃貸料を払っている(月、約25〜30万円)私のデザイン事務所の使っていない週末、土曜日、日曜日を有効に使って。日曜日は必ず休むことにしているので毎週「土曜日」、週一でスタートと決めました。そこでネーミングをストレートに椅子を学ぶ塾、「椅子塾」としました。その意味は皆さんご存知の「松下村塾」に習ってです。日本的教育スタイル「塾」、「師と弟子」その関係が日本では一番、趣旨にあっていると。期間はどうしようかと親しい友人の大学の先生に相談するとこんなアドバイスをしてくれます。「1クラス10人、期間10週、授業料10万円」?なるほど。
授業は、日本の美術大学で具体的にやっていない「椅子の人間工学」を体験的に学ぶ、「椅子の原寸図」を手書きで描く、「意匠登録」を自分で申請できるノウハウを教える、最後に授業の内容は講義や1/5の模型だけで終るのは面白くない。1/1のフルサイズの「木の椅子」を作るまでやろう!ずいぶん高いハードルです。そんな折り、仕事でも「I社」のエクゼクティブチェアの試作モデルを依頼し面識があった、ミネルバの宮本茂紀親方が「実物の椅子」を作るなら手伝ってあげようといってくれます。それ以前に1992年にデンマークで故ハンス・ウエグナーに会い、その後、「PPモブラー」の工場見学したとき家具職人アイナー・ペーターセンにあって「一流の家具デザイナー」になるには「一流の家具職人」とのコラボレーションは欠かせないと考えていたので日本でトップクラスの家具モデラーで、倉又史郎や喜多俊之、川上元美、佐々木敏光など日本を代表する家具デザイナーをサポートしてきた宮本さんの協力を得られることは願ってもない心強い言葉でした。あとで判ったことですが宮本さん自身が「Mプロジェクト」という椅子塾と同じようなことを13年やっていてそちらが終了したような時期でしたから「椅子塾」のスピリッツを応援してくれたのだと思います。
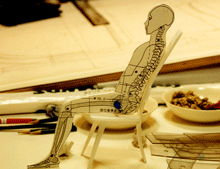
「井上昇の椅子塾」東京・南青山

「井上昇の椅子塾」第一期生授業

椅子の人間工学を学ぶのが第一目的
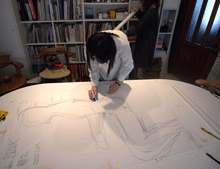
自分のボディゲージをとることから始める。
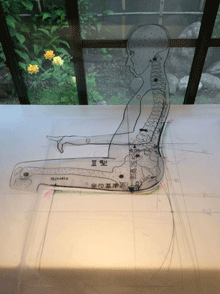
椅子の原寸図製図
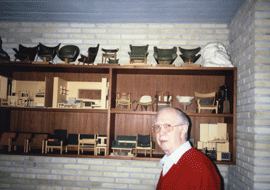
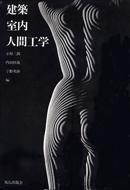
スタジオの故ハンス・ウエグナー(左側)

ミネルバの宮本茂紀親方
「授業の人数」と「授業の組み立て」
クランブルックに習って人数は絞り込み、スペースがそれほど広くないところに1/1のA-0の原寸図面を描くので場所をとります。10人はとても無理なので1クラス5人。期間は10週では短すぎるので3ヶ月、12回、1月、4月、9月スタートし年3回。授業料は人数を半分にしたので10万でなく、15万円。カルチャースクールでなく実務家が伝授する椅子のデザイン・設計の「プロスクール」にする為、塾費をやや高めに設定。学歴・経験・年齢・男女は関係ありませんが事前に「面接」することにしました。
2週目は椅子の人間工学を体験的に学ぶため各自の「実寸ボディーゲージを作成」日本人の胴長短足を体験するとともにボディーゲージを使って自分の椅子を作る。
3週目は椅子の原寸図面の模写。原寸図面を模写することにより椅子製図を体験。前半、各自の椅子の形が決まるまではじめに参加者のスケッチを提示してもらいみんなで意見出し合うクリティク
1回目から3回目の午後は東京の家具ツアーに行きます。現在の椅子塾はこんなショールームに行きますがこの解説付きツアーが椅子塾の特徴でもあります。
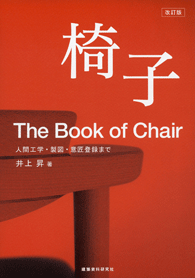
椅子塾の教科書
桜製作所(ジョージ・ナカシマの家具)、マルニ木工、ハーマン・ミラー(イームズチェアー)、飛騨産業、パークタワーOZONE(コンランショップ・北欧家具、椅子とテーブルのギャラリー、タイヨウの下(OZONE店)
2回目:五反田・目黒方面
日進木工、匠工芸、プランチ、センプレ本店、スタンダードトレード、タイヨウの下(目黒店)
3回目:青山・原宿方面
カッシーナ、hhp style com、Knoll、オー・ローズ、アイデック、フリッツハンセン、カールハンセン、家具蔵
4週目から各自のデザイン案を原寸図に描いていく。各自の1/1図面がまとまってきたらといあえず1/5模型にし立体化してみる。そこから又、1/1図面に戻り原寸図面にする。
5週目以降、2回目の1/5模型を作成し原寸図面と1/5模型をもって原寸の椅子を作成したい人で職人さんに頼みたい人はミネルバ・宮本茂紀親方に相談に行きアドバイスをいただきさらに修正箇所があれば修正。その後は各自が自分で作成したり発注する。12週目椅子塾最後の授業にパテント、自分で意匠登録の知識と申請の仕方を講義。修了証をお渡しして授業は終りです。


桜製作所・銀座ショールーム(左側)、 hhp sttyle com ショップ青山(右側)
授業は午後4時ごろ「コーヒー&スィーツ」のコーヒーブレイク
まさかコーヒーとスィーツが出てくるなんてと驚かれますがこれはアメリカのクランブルックのスタイルです。アイデアを出したり図面を描いたりで身体と脳が疲れます。適当にコーヒブレイクをとりながら甘いお菓子を摂取すると気持ちと身体がリラックスします。授業中にお菓子食べるなんてと日本では難く考えますがアメリカはその点、実にザックバランで自由なのです。形よりも実!でもこのコーヒブレイクと昼食を近くのレストラン巡りしながらの「しゃべりまくり」が塾で一番好きな楽しい時なのです。授業は12回ですが塾生は社会人が多く仕事の都合で休んだ場合の補習として1回増やし13回で終るケースがほとんど。
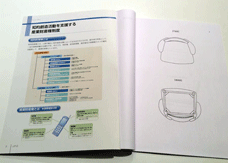
意匠登録申請書類作成


椅子塾名物:コーヒー&スィーツ(左側)、手描きによる1/1椅子図面製図(右側)

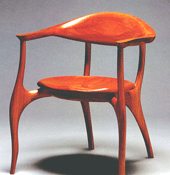
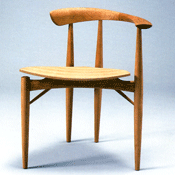
塾生の椅子作品:牛田裕也氏(左)・高橋元氏(中央)・神田剛志氏(右)

椅子塾10周年記念展「300 Chairs」パークタワーOZONE
● 井上昇のいすの話-55 Part 5
「椅子塾」-2
1999年1月に「椅子塾」をスタートし17年目。75期を終えて9月スタートまで休みに入りました。75期までやってよくもここまで続いているものだとの感慨はあります。「椅子塾」の場合、3ヶ月区切りのスタートなので夏季塾も入れると年4回やっていることになります。3ヶ月の募集で、すぐその次の募集に入る。それでいて75期の今まで一人も来なかったことは1回もないということがとても不思議です。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |

『室内』誌
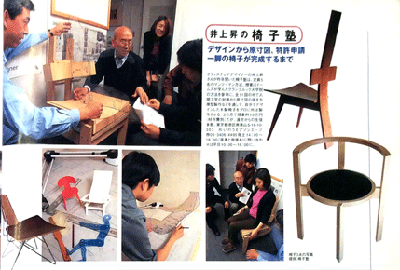
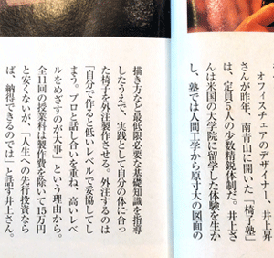
『エルデコ』誌、記事および記事文章
「椅子塾の本」発刊
『室内』誌が休刊になるまで最低限の広告は出していましたが休刊になってからは外部の雑誌にはいっさい広告は出していません。そのかわり、椅子塾生の作品を展示する「椅子塾展」をほぼ毎年開催しそれがブログやネットで拡散し実質的に広告の代わりになったこと、「椅子塾」5年目に東京・本郷の出版社「山海堂」の編集者が来て「椅子塾」の本の出版の企画を打診してきました。それから2年後『椅子 The Book of Chairs 人間工学・製図・意匠登録まで』が出版され、それが全国の書店、国会図書館を含む図書館に蔵書されそれをみて応募者がくることになったのだと思います。この『椅子・The Book of Chairs』は出版から2年ほどで4版を重ね、瞬く間に5,000部を突破することになります。
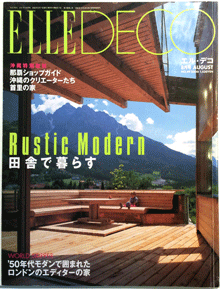
『エルデコ』誌
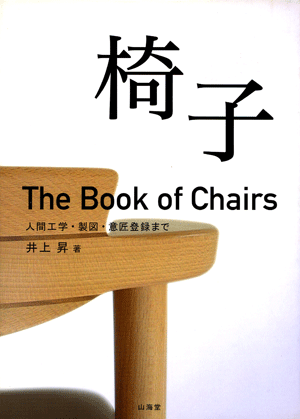
『椅子 人間工学・製図・意匠登録まで』初版:山海堂



5周年記念「100 Chairs」展、展示会場(左側)と参加椅子塾生(中央)、青山スパイラルガーデン(右側)
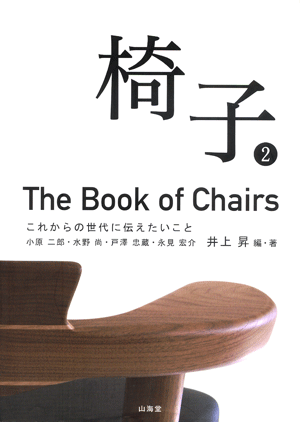
『椅子2 これからの世代に伝えたいこと』山海堂

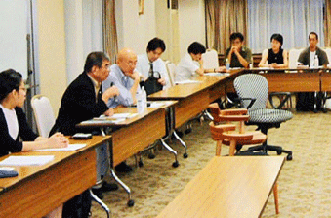
「椅子塾セミナー:椅子の人間工学」小原二郎(左の写真)、「椅子のパテント」水野尚(右の写真)


「椅子塾セミナー:椅子のデザイン」長大作(左の写真)、「椅子の製造」戸澤忠蔵(右の写真)
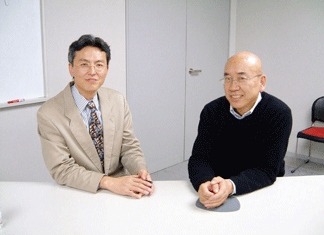
「桜製作所とジョージ・ナカシマ」永見宏介
出版社の倒産
「椅子塾」の本の半分は塾生の作品をまとめて収録し1冊目50作品、2冊目41作品、合計91の椅子の作品が収録されています。「山海堂」の編集者と、3冊目は全部、椅子塾生の作品、約80〜100脚をまとめて出版しましょうということでその準備も続けていましたが、その出版社の「山海堂」の経営が行き詰まり中止に。100年以上の歴史がある出版社がまさかの倒産するという今の出版事情の苦境は同情します。ネットで情報はえられますがじっくりと繰り返し読むことが出来、後世に思想なり技術を残すことの出来る「本」の重要性は今後も変わらないと思いますが、本の出版がとても難しい時代に入りました。「山海堂」が倒産したことで2冊分、特に最初の5000部ほどがでた本の著作料100万円ほどが頂けず、なんと債権者に。それはそれで残念ですがそのことより、好評だった1冊目の「椅子・The Book of Chairs 人間工学・製図・意匠登録まで」の出版が不可能になったことのダメージが大きすぎます。なんとかして再発行したいと「山海堂」破産管財人に問い合わせると本の「発行権」は「山海堂」の財産なので1冊10万円、2冊あわせて20万円で発行権を売り渡しても良いとのつれない返事。「時は金なり」早く発行権を買い取り次の出版社をさがしたいとのことで20万円を支払い権利を取得。著作料が貰えないばかりか自分の書いた本を取り戻す為にさらに出費。踏んだり蹴ったりとはこのこと、何とも複雑です。部数が出ていたので著作料も入るとの期待とは裏腹にさらに出費して!このとき本を出版するとはほんとにタダ働きにちかいのだなと痛感。
改訂版の発刊
さて発行権は取得しましたが次の発行して頂ける出版社を見つけるにあたっては何社かに絞りました。その時の条件は絶対倒産しない出版社を選ぶということでした。候補の中からとりあえず当たってみようと最初に日建学院を経営している「建築資料研究社」に打診したところ会って頂けることに。本の価格を下げることと追加のページを補填することを条件に「改訂版」「椅子・The Book of Chair 人間工学・製図・意匠登録まで」のみ出して頂けることになり、2冊目の本は再販できませんでしたが一番重要な1冊目が出版できたことは感謝です。改訂版」は表紙のデザインは変えず表紙の色を赤にすることで継続性を表現し出版。改訂版も日本全国の図書館に収蔵されています。「山海堂」時代で5000部ほど、「建築資料研究社」の改訂版で3000部ほど。合計8000部ほどが出ています。学生さんばかりでなく木工家、家具メーカーの開発部や設計の皆さんに購入して頂いていて皆さんのお役に立っているようで当初の目的は果たせているようです。
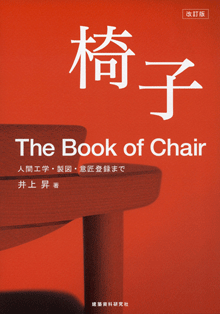
『椅子 人間工学・製図・意匠登録まで』改訂版:建築資料研究社
椅子塾と椅子の本の目的「椅子の人間工学」
「椅子塾」のそもそもの原点は、椅子の設計ノウハウを学んで自立したビジネスを立ち上げる、又はプロを目指す人をサポートする社会人の為の塾という目的です。その目的の為にはどうしても「日本人の椅子の人間工学」のことを伝え、学べる機会を作ることが必須で、欠かせません。このことを外して椅子のデザインを学ぶ、売れる椅子を作ることは「椅子のプロの立場、視点」から見て考えられません。日本だけでなく世界でも常識のことですから。
今の日本の美術大学で椅子を学ぶ学生に「椅子の人間工学」が学べる機会を作っているでしょうか。ほとんどないと思います。その理由は教える側にその知識と体験がないことです。もう1つは人間工学でも最近はもっと難しい実験に取り組んでいて「椅子のプロトタイプ」のようなレベル、段階では研究論文にはならないと思います。でも我々、椅子の設計家、実務家にとっては「椅子のプロトタイプ」のような完結で実用的なデータが一番大切なのです。「椅子の人間工学」を学ぶ上で私の場合はとても恵まれた環境にいました。11年勤務していた「O社」の開発部時代、コンピューター(OA)の事務用椅子の開発・デザインに当時の千葉大学小原二郎研究室で部外者ながら産学協同のプロジェクトとして「椅子の人間工学」を直接、小原先生から指導、教えて頂き、それを製品化の過程で座りの実験、検証をして頂き、そのOA椅子が100万台を超えるヒットになったことで体験として学ぶことが出来たことでした。ずいぶん贅沢な環境です。小原先生からも君は「椅子の人間工学」の免許皆伝だとのお言葉も頂きながら会社を辞めて先生をがっかりさせてしまったこともありましたが、私にとって小原二郎先生から学んだ「日本人の為の椅子の人間工学」がなかったらその後の椅子のデザイナーとしての成功はなかったでしょう。それは確実です。それだけに小原先生の理論を次世代に具体的に伝える責務があると考えるのです。
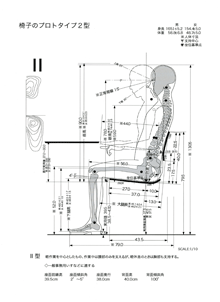
椅子のプロトタイプ

元千葉大学、小原研究室:小原二郎教授
恩師との出会い
高校時代は美術部で水谷春夫先生、武蔵野美術大学時代は豊口克平先生や佐々木達三先生、卒業して就職したO社では小原二郎先生、アメリカのクランブルック美術大学院では先輩のアメリカの椅子の人間工学の権威で椅子のデザイナー、Mr.ニールス・ディフェリエント氏との出会いなどずいぶん影響を受け学ぶことが出来たことは大変ラッキーだったとしか言いようがありません。
その中で椅子のデザインの要と言われる「椅子の人間工学」を小原二郎先生の外部弟子としての出会いは大きく、先生から「椅子の人間工学」を直接指導された恵まれた世代として次の世代に伝えることは先生に対する恩返しと位置づけそれで「椅子塾」を始めたのですが、塾に来れない人の為にそのことをまとめた本、「椅子・The Book of Chair 人間工学・製図・意匠登録まで」を出版したのです。
椅子の本の目的
本だったら密かに読める。勉強することが出来る。頑固でプライドが高くそれでいて不安を抱えている木工家も、企業の設計に携わる人も密かに読んで下さっている。うれしいことです。それで日本で製造された椅子のレベルがあがり収入の上がるお手伝いになったら社会的意味があります。それが「椅子塾」、「椅子の本」の出版なのです。発売以来8000部も売れた理由が意図したとおりになったようでうれしいです。北欧の椅子や名作椅子だけの特集の写真本と意味が違うのです。椅子の評論家の本ではありません。日本人のための椅子のデザイン、製作、販売で苦しんでいる人の為の実務家による実務家の為の本なのです。さらに本だけで判りにくい、もっと具体的に、小原先生からマンツーマンで指導受けたようにマンツーマンでその極意を具体的に学びたい。そういう方の為に開いて、実践的に伝授するのが「椅子塾」なのです。くどいようですが椅子の設計に携わる場合、「椅子の人間工学」の理論活用なしには難しいと思います。この座りの研究は世界的に行われていてこのそれらの研究データーを使わないという椅子の設計は世界的にないのです。世界中の学者、研究者が数千人の被験者から数十年にわたって取り組んでいて私たち設計者はそれをほとんどフリーで活用できるのですから使わせて戴くべきです。椅子の設計製造に携わる人は木工家も含めて謙虚にその知恵を有効利用すべきです。キット見返りがあるはずです。私の場合は小原研究室の椅子のプロトタイプを使わしていただきオフィス家具で400万脚、木製、オフイス用ラウンジチェアー、作業用椅子等を含めますと500万脚の椅子は全部この小原理論で設計し、数億円ほどは収入になっているでしょう。ですからこれだけお勧めするのです。椅子塾で3ヶ月で椅子の設計が可能なのもこのデーターを利用してこそ可能なのです。
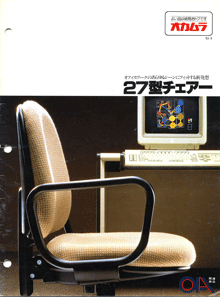
O社:エルゴノミクスチェア-27型

エルゴノミクスチェア−27型体圧分布
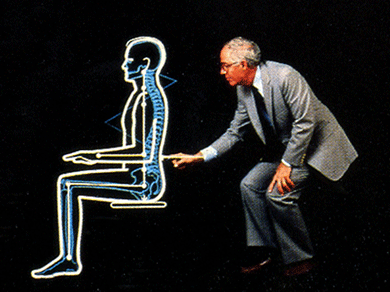
人間工学の権威で椅子のデザイナー:M.ニールス・ディフェリエント氏
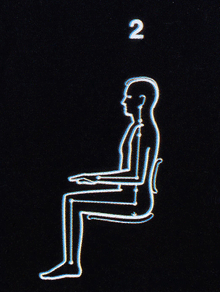
アメリカの椅子の人間工学:ニールス・ディフェリエント
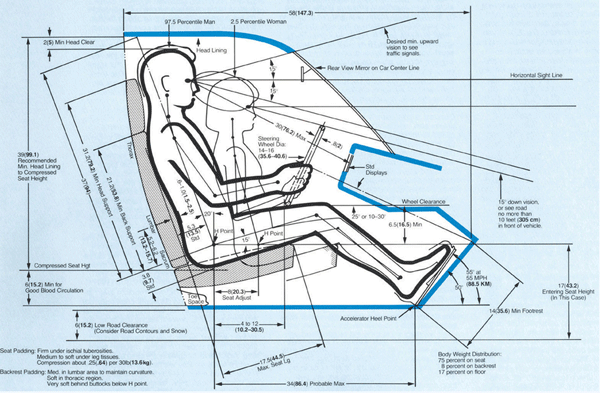
アメリカの椅子の人間工学:自動車のシート

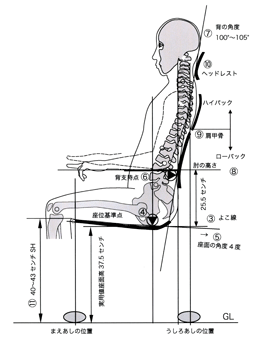
椅子塾展の椅子塾生作品(左側の写真)、椅子の人間工学の応用:井上昇(右側の写真)
● 井上昇のいすの話-56 Part 6
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |


75期椅子塾(左の写真) 富士見高原・ソバ畑(右の写真)
「椅子とテーブルのギャラリー」の開設
中でも一番気が抜けなかったのはやはり、西新宿、パークタワーOZONE4階に「腰の椅子 Awaza」の直営ショウルーム「椅子とテーブルのギャラリー」をオープンしたことです。
OZONEには10年前から「工房家具ギャラリー・匠の杜」代表、山口尚忠さんの工房グループに10年間参加させていただきOZONEでの活動の経験はあったと言え、グループ10工房参加の中の1/10の責任の気楽さ、出費の軽さの時代から、今度は自分が全責任をもって直接「椅子とテーブルのギャラリー」を運営、維持するのは全然違います。数百万円に及ぶ敷金、毎月数十万円支払い義務のあるショールームの維持。シェアースペース仲間の維持管理。朝10時30分から夜7時までの週6日の対応と接客。ほぼ1年たち経験も少し積んで落ちついて来た所ですが赤字には出来ませんからその運営は慎重でなければ務められませんし全く気が抜けません。御陰さまで無事2年目に入ることが出来そうです。

パークタワーOZONEの外観

パークタワーOZONEの内部


「椅子とテーブルのギャラリー」
「イームズ対抗、コンパクトラウンジチェア」の開発
イームズ対抗、コンパクトラウンジチェア「Awazaパーソナルラウンジ」の開発も私にとっては今年後半の大きなエネルギーと費用をかけたプロジェクトです。

Awaza パーソナルラウンジチェア

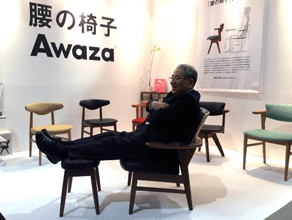
IFFT インテリアライフスタイルリビング展ブース(左の写真)、同ブース内の上野義雪教授(右の写真)
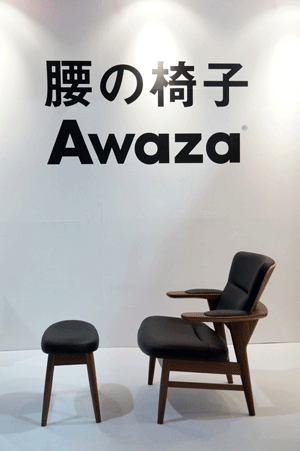

「Awaza パーソナルラウンジチェア」(左の写真)とイームズラウンジチェア&オットマン(右の写真)
小原二郎先生98歳のラウンジチェアーの人間工学の提案
このラウンジチェアーの開発は私のダイニングチェアー「腰の椅子 Awaza」を展示、販売している2カ所の販売店の店長さんから数年前から要望があったことが出発点です。
ひととおりダイニングチェアー、リビングダイニングチェアーの品揃えが揃い、会社として品揃上からも、もうランク一つ上のラウンジチェアーの開発の段階に入ったこと。ソファの品種のなかでもパーソナルラウンジチェアーの需要が高まっていること。そのプランを数年前から暖めていたそんな折、2年前に尊敬する小原二郎先生が98才の時、ラウンジチェアーの人間工学の最終プロトタイプの決定版をインテリア学会と岡村製作所の協力で冊子にまとめ発表され、直接お会いして講演を聴くことが出来たこと。
この小原先生の98才のラウンジチェアーの理論を製品化する、こんな素晴らしいことはありませんし、これは小原先生の外部弟子、私の椅子のデザイナーとして製品化することは私の役目だと直感したのです。さらに椅子の販売10年目の区切り、それ以上に「椅子の開発は格闘技」のジンクスもあり年齢的にも体力がまだある今、取り組む時期的タイミング。尊敬するチャールズ&レイ・イームズのアメリカでのクランブルク美術大学院の後輩として、日本人の小柄な体型と生活スタイルにあわせた、日本人の為のイームズラウンジ&ソファの様な本格的なラウンジチェアー&オットマンを作製、提案するという意味をこめてあえて「イームズ対抗パーソナルラウンジ」としました。

小原二郎先生講演案内

小原二郎先生講演会
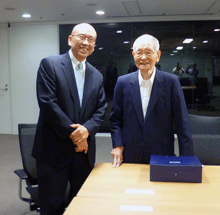
98歳の小原二郎先生とのツーショット
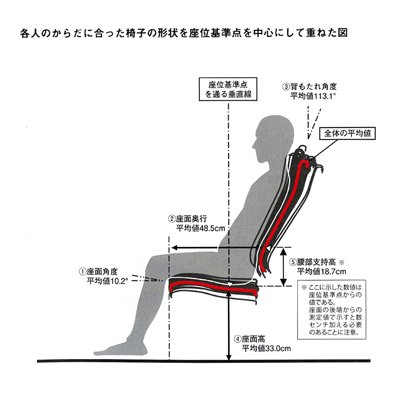
ラウンジチェアープロトタイプ・小原二郎:『椅子の科学を考える』誌、岡村製作所編より抜粋
繰り返しますが、パーソナルラウンジ&オットマンを他人に介在され、従う必要も全く無く、思い切り自分が小原先生が最後の決定版と言われる椅子の人間工学理論を取り入れ、新製品として椅子のデザイナーとしてだけでなく椅子のメーカーとして重量級の椅子を生産し、販売し、世に問うことが今出来る、そのような最高のタイミング、背景があるのです。来年の発売に向けて現在、修正図面化作業中です。
「木の文化フォーラム」での講演
12月12日午後2時から木工関係の多数の著作で知られる西川栄明さんのお誘いで、会場、渋谷桑沢での「木の文化フォーラム」、「人間工学の観点からの椅子のデザイン」のタイトルでお話しさせていただきました。日本での人間工学の師匠、今年100歳の元千葉大学・小原研究室、小原二郎教授の椅子の人間工学理論とそれを具体化した私の事務用椅子と木の椅子の作品、もう1人は2年前亡くなったアメリカ、クランブルック美術大学院での先輩で卒業生OB会長!アメリカの人間工学の権威で椅子のデザイナー、ニールス・ディフェリエント氏の理論と椅子作品を紹介しながら椅子の人間工学の製品開発における意味お話しさせていただきました。話の中では椅子の人間工学ばかりでなく「椅子塾」の話、意匠登録や契約書の話、椅子のビジネス、ハンス・ウエグナーにあった時のエピソードなどなど。
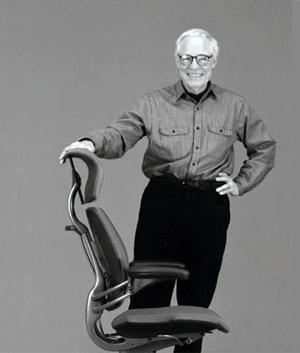
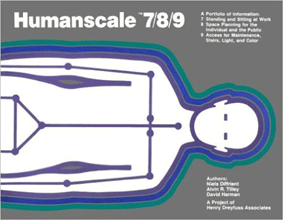
アメリカの人間工学の権威:故ニールス・ディフェリエント氏(左の写真)、アメリカのヒューマンスケール(右の写真)
 開発に40億円以上かけた人間工学の椅子。
開発に40億円以上かけた人間工学の椅子。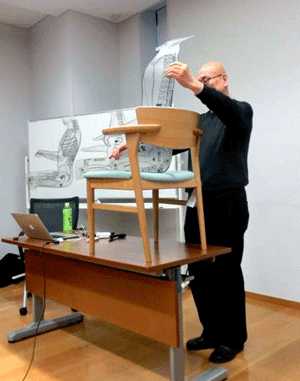
ボディーゲージを使っての説明
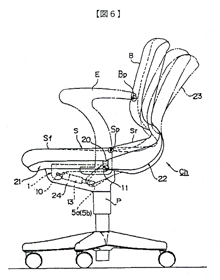 椅子のメカニカル特許
椅子のメカニカル特許2015年は、私にとりまして変化の多い年でしたが充実した年だったと振り返っています。皆様に取ってはどんな年でしたか。今年の暮れも築地場内市場にて正月の食材を仕入れにいきました。毎年恒例の年の瀬の習慣です。
来年はどんな年になるのでしょう。
70年続いた平和が続いて欲しいものです。
皆様に取りましても良き年となりますように。
勇気をもってチャレンジしてゆきましょう。
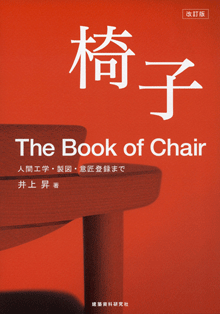
『椅子 人間工学・製図・意匠登録まで』改訂版:建築資料研究社
 築地場内市場
築地場内市場