● 井上昇のいすの話-58 Part 8
2017年がはじまりました。
椅子塾の話もすっかりご無沙汰していました。
毎月という時期も長年続いていましたがこれからは月にこだわらずコラム的な感じで椅子の話題を中心にアップしたいと思います。2017年もよろしくお願いいたします。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2012年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
19年目の椅子塾(1999〜)
6年前に20年いた南青山5丁目から南麻布に事務所移転したことで、現在は「Azabu ISUJUKU」という名称で続けています。今年は1月21日から「椅子塾」79期がスタートします。1999年1月に1期生がスタートして19年目。想定外の長さです。始めた当初は「BAUHAUS」が14年やっていたので塾生には14年はやめませんと言っていました。「椅子塾」は3ヶ月ごとのプログラムなので以前は年に4回、1月、4月、夏期集中塾、9月、とやっていましたが、「Azabu ISUJUKU」になってから現在は夏期塾はやっていません。青山「椅子塾」時代は定員5名、水曜日:午前クラス、土曜日:午前、夜間クラスと週にほぼ3クラスをやっていましたが、現在の麻布「椅子塾」は、土曜日のみ、午前クラス、定員4名の週に1クラスだけです。18年間のトータルの終了生は310名。
実は昨年の9月期だけ、応募がありませんでした。18年目にしてはじめてです。

杉山さんの椅子
「技術伝承塾」としての役割
主宰している側から見れば、「椅子塾」は、3ヶ月ごとに開催しているのですが、応募がなければ成り立ちませんから18年目にしてはじめて応募がなかった、反対に考えればよくも途切れなく続いたものだというむしろ感慨のほうが強いのです。それは「椅子塾」の立ち上げの目的である社会人むけ短期集中の「技術伝承塾」のニーズが潜在的に現在もあるということですが、おそらくこれから「椅子塾」のもつ意味性は今後も無くならないでしょう。
現在の私にとって「椅子塾」は応募がなければそれはそれで良いのです。椅子のデザイン分野で、理論だけでなく実践として、「椅子の人間工学」「製図」「知的所有権」「製造技術」を学者でなく、現場経験豊富な実務家で、現在も現役の者からマンツーマンで学べる、そのような「場」を必要としなくなる。本来はそういう状況が望ましいのですが日本の美術大学、専門学校がほとんど教育プログラムに「椅子塾」のような内容を入れていないので、社会に出てデザインの現場で問題にぶつかったとき「椅子塾」のような短期の集中の社会人学級があれば助かる人が少なからずいると私は18年の経験から思います。このような「実務塾」が日本にもっとあるべきです。
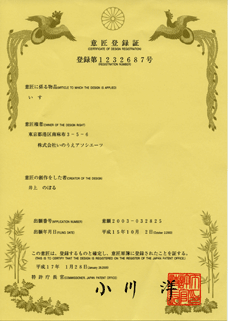
意匠登録・パテント
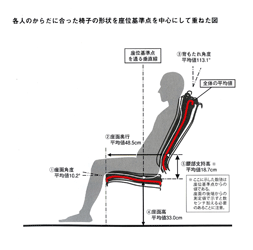

椅子の人間工学・小原二郎氏の98歳の研究(左の写真)、平行定規による手書きの椅子の原寸図を書く(右の写真)
「腰の椅子・Awaza」
現在の私は本業の12年前に「椅子塾」の活動の中から生まれた、家庭用ダイニングチェアー「腰の椅子・Awaza」の椅子の製造・販売が軌道にのり、全国35店舗に卸し、西新宿、パークタワーOZONE 4階に直営の家具のショウルーム「椅子とテーブルのギャラリー」を持っています。日本では椅子のデザイナーが自身で「製造」「販売」までやるのはあまりいないと良く言われます。形で言えば小さいながら、「椅子のメーカー」になったのです。それなりに忙しくそちらに集中したい。しかし、「椅子塾」はこちらも私にとってのもう1つのライフワークですから、可能な限り「椅子塾」の趣旨が必要な方、応募があれば開塾することにしています。これは1999年に「椅子塾」を始めたときの気持ちと今も基本的には変わりはないからです。「製図」はCADで皆さん出来るので別として「小原理論の椅子の人原工学」「椅子の意匠登録を自分で出す」この項目は今の学校では教えていないところがほとんどです。企業にて実務をやられている方は問題ありませんが、フリーでやられる人、他分野からこの世界に入ってこられた方は、一度はしっかり学んだ方が将来的に成功するには不可欠だからです。甘く考えてはなりません。スポーツにもルールがある様に、家具の世界でも踏み外してはいけないルールがあるのです。特に「人間工学」と「パテント」です。



Awaza LD(左の写真)、Awaza LDR(中央の写真)、Awaza MA01(右の写真)
現在の椅子塾
19年目の1月、即ち今月スタートの79期は3名の方が現在来られることが確定し、スタートします。
現在は「椅子塾」はほとんど宣伝していません。ツイッターで案内しているだけです。しかし、私の著者、改訂版「椅子・人間工学、製図、意匠登録まで」建築資料研究社、が8,000部以上売れていることでこの本をみて応募されてこられます。最近の応募される方は現在携わっている仕事、実務の必要上来られる方がほとんどで、家業の2代目、3代目、実務での悩みを抱えてこられる方が多く、趣味で来る以前の様な方はあまりいません。「技術伝承塾」といつているように具体的なノウハウを求めてこられ、新規事業の立ち上げや、実際に椅子を作る方、パテントの具体的実践の知識など本格的です。私は大手家具メーカーで長年開発に携わり、フリーとなってからも大手家具メーカーのデザイン開発をやっていたので、パテントを含む技術的なこと、デザインなど大抵のことは木の椅子も含めて体験と実績があるのでお手伝いできるのです。現在の椅子塾の内容は19年前と基本的に変えていません。1:椅子の家具ツアー。2:椅子の原寸製図。3:椅子の人間工学。4:1/5椅子模型製作。5:椅子のパテント。6:椅子の実物製作。12回の授業内容はこんな感じです。
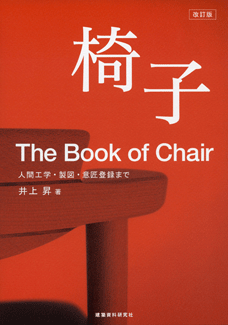
椅子の本

毎週岡山から通ってこられた、77期近藤さんの作品
Azabu ISUJUKU 授業スケジュール
1:午前/座学(椅子の本:建築資料研究社)
午後:フィールドトリップ-1
2:アイデアスケッチ ボディゲージ作製
午後:フィールドトリップ-2
3:アイデアスケッチ 椅子の原寸図模写-1
午後:フィールドトリップ-3
4:アイデアスケッチ 椅子の原寸図模写-2
5:アイデアスケッチ 椅子の製図 ボディゲージを使ったラフ図面
6:椅子の製図 ボディゲージを使ったラフ図面
7:椅子の製図 ボディゲージを使ったラフ図面
8:椅子の製図 完成図面-1
9:椅子の製図 完成図面-2
10:椅子の製図 完成図面-3 椅子の1/5模型作製
11:椅子の製図 完成図面-4 椅子の1/5模型作製
12:椅子のパテント。 原寸椅子の発注。
座学は私の著書:改訂版「椅子・人間工学、製図、意匠登録まで」建築資料研究社をテキストにし、その内容を詳しく解説するプログラムになっています。
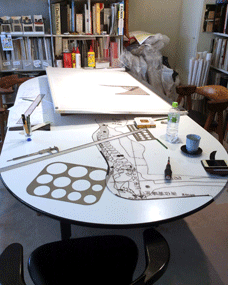
椅子塾授業風景-1
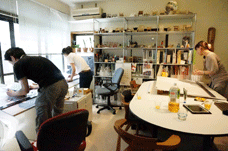
椅子塾授業風景-2
家具ショールームフィールドトリップ
最初の1〜3回目の午後は3回に分けて都内の家具のショールームを解説付きで訪問。これが人気です。私にとっては3ヶ月ごとに都内の家具ショールームを18年間みていることになり、木製業界の動向が新製品も含めて拝見させて頂くことになっているのです。ついこの間立ち上がった新しい会社が20億の売り上げの会社になったり、あんなに盛んだった話題の家具会社が今は経営者が変わりかっての勢いは無かったり、撤退したり、栄華盛衰を間近に見てきました。

桜製作所:銀座ショールーム
ボディゲージ
2回目の「ボディゲージ作製」は参加者各自の座った姿勢のボデイーの形、シルエットを取り椅子の設計に使うのです。「胴長短足」の現実を体験することになり椅子塾ならではの楽しい時間です。
椅子の原寸図
3、4回目は椅子の原寸図面の模写です。応募者は椅子の原寸図を描いたことがないので、サンプルの椅子の原寸図面を「模写」し椅子の図面を描く体験をしてもらいます。それまでに各自が自分の作りたい椅子のスケッチを描き、それをもとに自分の作りたい椅子の図面を描いて行く作業に移ります。5〜9回までは各自のデザインしたい椅子の原寸図面と格闘して頂きます。椅子のデザインは格闘技なのです。やっていただくとわかります。逃げがきかない真剣勝負。
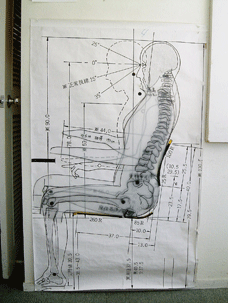
ボディーゲージ


椅子の模写用の椅子(左の写真)、椅子の原寸図(右の写真)
1/5椅子模型
10〜11回は自分でデザインした原寸三面図を1/5の縮尺図面にコピーし、バルサで模型を作ります。ここで一気に立体になってきます。
椅子のパテント・実物椅子の製作
12回は椅子のパテント、自分で自分の意匠、デザインを守るために特許庁に「意匠登録」を弁理士さんに頼まず、自分で申請する、書類の書き方、申請方法を学びます。
10〜12回の間に、原寸の実物の椅子を作りたい方は、ミネルバの宮本茂紀さんにみんなで会いに行き一脚の椅子を作って頂くのです。(費用は塾生持ち)
この繰り返しを18年間、78回やってきたのです。
以前はそこで作った椅子を「椅子塾展」で発表し塾生みんなで楽しみ、交流するのです。実際にはこの展示会で発表した椅子がメーカーの目にとまり、製品化に至ったり、海外に留学する時の作品になったり、家具メーカーに就職するプレゼンになったり、自分で作り(委託)自分で販売する人など様々です。今では日本ばかりでなく海外で活躍している修了生を見さして頂いているのは良いものです。日本における椅子の分野での影のサポート。それが「椅子塾」の目的なのです。私にとっては充分楽しませて頂いています。「親切は人のためならず」全部こちらも助けられているのです。
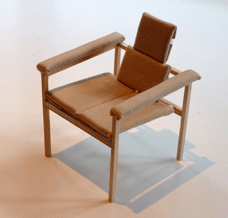
椅子の1/5模型(右の写真)

椅子の意匠登録
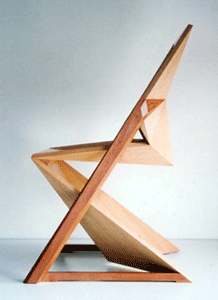

実物の椅子:牛田裕也さんの作品
2017年1月14日 「椅子塾」塾長 井上 昇