● 井上昇のいすの話-32 Part 2
昨年の12月は椅子の話忙しさにまぎれて休んでしまいました。2013年新たな年を迎えスタートします。
イリノイ州ベロイトのホームステイ先、農家ホルメスに見送られて、シカゴ経由でデトロイト郊外ブルームフィールズヒルズにあるクランブルックにもどります。寮に入る事にしていたので入学手続きの前の日に到着、その日は学校の近くのモーテルで1泊。翌日、朝、クランブルクの事務室に行くと新入生が三々五々来ています。英語学校と違い全米各地から集まって来た男女学生に混じって東洋人が少し目につきます。入学手続きを済まして男性寮へ。寮は単身寮と2人寮の2タイプがあり人気がある単身寮はすでに2年生が独占。新入生は2人寮が割り当てられます。軍隊と同じです。私は25、6歳のプリントメーキング、即ち版画科の学生と一緒の2人部屋。クランブルクに入学前、イタリアに留学していた事があるという事で、普通2年生に与えられるティーチングアシスタントという奨学金付きの役割を1年生からもらってえらい自信満々のお兄さんと一緒!。とても気の良いお兄さんですがとても女性に持てるタイプで時々部屋を占領され外で待たされる事もしばしば。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストンへ」 | |
| 2013年06月29日(金) | |
| 「クランブルック2年目」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

Cranbrook Academy of Artゲート



クランブルック事務局と校舎 短い秋の紅葉・メープル 冬のクランブルックキャンパスにて家族と
アメリカの学校は2セメスター、2期制(秋、9月期、新年、1月期)でどちらからでも入学できるという自由度があります。1年在学し、1年休学したあと復帰するという自由度もあり日本とずいぶん違います。冬学期から入る人は少なくやはり9月から入学する人が多いのは日本の4月入学とにています。

Cranbrook Academy of Art
キャンパス
Fall Term Registration September 10(M)
Fall Term Begins September 11(T)
Thanksgiving Recess November 22,23(Th,F)
Fall Term Graduation December 20(Th)
Fall Term Ends/Winter Break Begins December 21(F)
Spring Term Registration January 21 (M)
Spring Term Begins January 22 (T)
Spring Break Begins March 21 (F)
Classes Resume March 31 (M)
Good Friday April 4(F)
Spring Term Graduation May 22(Th)
Spring Term Ends December 21(F) May 23(F)
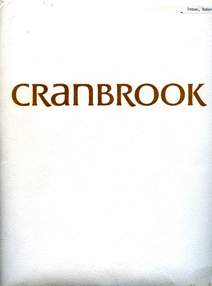
クランブルック授業計画ファイル
クランブルクは大学院大学なので通常の授業というようなプログラムはありません。クランブルクは、デザイン、版画、建築、絵画、彫刻、彫金、写真、テキスタイル、陶芸の9学科があり先生は各科に1人ずつ、デザイン科のみ2名。学生も各科10人以内しか入学させない小さな学校です。クランブルックの特長はアートスクール!デザインも写真も全部アートとして取り組む基本方針があります。

最近のクランブルックガイダンス
デザインはアートと違うという人はこの学校には1人もいません。このデザイン学科の初代指導者がチャールズ・イームズでその生徒がレイ・イームズになるのです。ですから我々デザイン科の卒業生はレイの後輩になるのです。小さな学校だけにその絆は端で見るより強いといっていいでしょう。
私の入学時のデザイン科の教授はマイケル・マッコイ&キャサリン・マッコイ。マイケルが3D、立体、インテリア、プロダクトデザインを担当し、キャサリンが2D,平面、グラフィックデザインの担当。驚いた事にマッコイ、通称マイクは私と同じ年、キャサリン、通称キャシーは一つ年下。最初の驚きは唯一の担当教授が同い年とは!何ともはや!
しかし、建築科の教授は2歳年下の33歳!この建築科の教授がダニエル・リベスキン。現在建設中のニューヨーク ワールドトレードセンターの跡地に立ちつつある高層ビルの建築家になるのです。
デザイン科の授業は教授と話し合いながら自分のテーマを決めていく自主授業スタイルを取っています。デザイン科1、2年合わせて20名、約半分が2D,3Dと分かれるので1、2年合同でも立体が10名程度なので毎日一緒にやっている感じですがただ1年目の新入生は、グラフィック、ディスプレイ、照明器具の課題や、本を5冊よんでレポートを提出などの課題の他に1年のはじめと2年目のはじめだけは、みんな初顔合わせなので、仲間意識を高める為に最初の授業のみグループ課題を出し、その課題をチームでリサーチからはじめ討論し、プレゼンモデルを共同で作成し、そのチームの代表が発表するというプログラムからスタートします。私の時はデトロイトのインターセクション、即ち、ある特定の交差点を選び、その問題点を現地でリサーチし、分析し、改良点を洗い出し文章化しモデルまで作成しました。

クランブルック時代のデザイン科教授:チャールズ・イームズと建築家教授:エーロ・サリネン
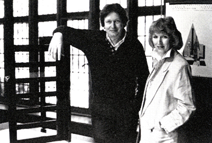
教授マイケル・マッコイ&キャサリン・マッコイ
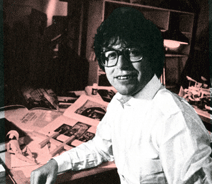
建築家教授:ダニエル・リベスキン
それでも楽しい事も。入学してグループワークが終わっての10月、授業の一環のニューヨークトリップに出かけます。
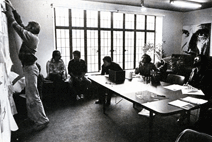
デザイン科の授業風景:2年先輩のクラス

教授マイク・マッコイとノルのデザイン部長ジェフ・オズボーンと院生の私。皆同い年35歳。
ニューヨークトリップ
10月のニューヨーク、マンハッタンではデザイナーズサタデイというニューヨークにある大手家具会社(ノル、ハーマンミラー、スチールケース他)や店が展示会を同じ時期に開催し、それらの家具ショールームやデザイン、建築スタジオを訪問、見学しながら夜は家具ショールームでパーテイーが開かれそれらに合流。特に、クランブルックはハーマンミラーやノルと関係が深く卒業生が多く働いています。そんな事でノルでのパーティーはクランブルクの同窓会の観を呈しており、ニューヨーク在住の家具関係者の他、クランブルックの沢山の卒業生、ノルの創立者、フロレンス・ノルも来て大盛り上がり。日本では考えられない程の華やかなハイステータスなパーテイーです。
そんなニューヨークトリップも終わり家族を迎えての最初の冬は零下10度の銀世界。学校とアパートと幼稚園の往復の日々。アパートに移ってもいつ帰るか解らないので家具は最低限に抑え、サルベーションアーミー、救世軍の所からただ同然で家具を仕入れ、あとは捨てられている建材を拾って来てテーブルにしたり。アパートは家具がないので室内運動場の様、まさにバラック生活が続きます。
2013年1月5日 井上 昇

椅子のデザイナーでクランブルックの先輩デビット・ローランドのオフィス訪問

アルバート・カーン建築事務所訪問
● 井上昇のいすの話-33 Part 2
何はともあれ12年ぶりのクランブルックでの学生生活をすごします。理由はどうあれ生活の基盤を作る30代半ばで家庭を持ち子供までいて、職をなげうっての自費留学など当時も今も普通の常識から考えればとても非常識な行動である事にはかわりはありません。さらに資金計画も十分でなく!今振り返っても無茶な行動をとったものだとは思いますが、私にはどうしても達成したかった、考えていた目的がありました。それは「独立」です。会社の中で自分の将来のポジショニングが全く見えない中でただ家族の生活の安定の為だけに、このまま自分に与えられたたった一度だけの人生を会社内で我慢して過ごす事が良いのか!(ほとんどの人はそうしているし、それが日本の家庭人の常識です。)自分に取ってはノーの結論を出したのです。次にそしてもし独立するとしたら、すでに海外のキャリアを元に活動している同じ家具分野のライバルと戦って行けるのか!これもノーです。その先輩達がイタリアに行っているのなら長年の苦手の課題である英語の勉強もかねてアメリカへ行こう。そう思っていたときクランブルックの情報が入り、試しに会社に内緒でアプライしていたら入学許可が出たので決断したのです。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストンへ」 | |
| 2013年06月29日(金) | |
| 「クランブルック2年目」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |
年齢も独立するなら35才がリミットとこれも同じ会社から独立した信頼する先輩から聞いていたので。辞職した大手家具会社の創業社長もとても心配してくれて、社員に戻れば2年間の留学費用を全額持つからとのありがたい手紙もいただきましたがご辞退しました。もし戻ればもう会社を辞めれなくなる。会社をやめる最大の理由は「独立」して自立したかったからです。2年間の留学費用を出していただいた上で会社を辞めれば道義的に同じ家具業界での信用がなくなる。このほか、留学後、元の勤め先の会社から仕事をいただけたらとの淡い期待もありました。創業社長が帰って来たら挨拶に来なさいとの言葉もあったからです。仮に仕事をいただけなかったとき、ライバルメーカーの仕事をしたとしても自費留学だったら後ろ指さされなくて済むという計算もありました。実際にはそうなりました。将来の活動の自由と信用を優先したのです。これは大正解でした。
帰国後,前にいた会社を訪問し社長にお会いし順序はふみましたが結果的に仕事は頂けませんでした。そこでしかたなくもといた会社のライバルメーカーの仕事をする事となった時、義理を欠かずに仕事をする事が出来、将来が開けたのです。仕事は信用が何よりも優先します。
留学資金と費用
それではどう私費留学の資金を工面したか!これも無茶な話ですが、なし崩しに義父から2年間の家族留学費用1,200万を借金しました。結果的に応援してくれたのでしたが、帰国後、10年かけて完済しました。

冬の Cranbrook キャンパス
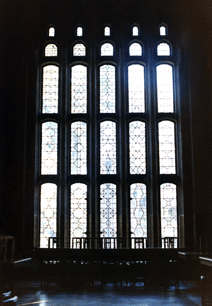
同じ敷地内 Cranbrook 高校の
学生食堂
義父曰く「可愛い娘と孫を人質にとられて応援するしかないだろう」。それとこういう事も「お互い困っている時は助け合おう」とも。その約束は「義父母の老後のケアーを最後まで看取る」という事をわたしなりに実行して約束を果たしたと思っています。今思えば私が留学した時期の日本はバブル経済の全盛期で義父母はまだ若く支援するだけの経済力があった時でした。その意味で留学時期としてはラッキーな時期だったともいえますし、義父母に取っては結果的に強制貯金させた事と裏腹に日本のバブル経済がはじけたあとの不景気なとき貯金が全額戻ったことになり?良かったんではと勝手な理由をつけたりしました。
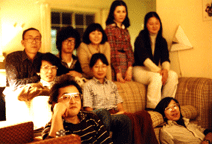
我が家での同時期の日本人留学生の集まり

デトロイト:フォードミュージアムでのパレード

フォードミュージアム
開拓時代トレイン

フォックスヒルズアパートメント
拾ってきたドアーをテーブルに改造

デトロイト:モーターショー

冬のアパート周辺・2階の窓からの景色
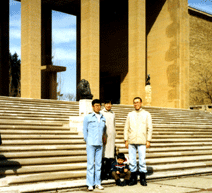
クランブルックに来てくれた元会社の先輩と
そんな留学生活を送る中で一つの決定的とも言うべき体験をします。会社にいた時、一緒に仕事もし親しくしていた営業の先輩が独立し、デトロイトに訪ねてきて、一緒に同じミシガンのシカゴに近いジーランドにあるハーマン・ミラーの本社と工場見学にいこうと誘われます。すでにアポイントメントは日本で取ってあるということで2人で自宅から5時間の距離にあるその工場見学にでかけます。
1階の受付で挨拶をすませ、2階のショールームを案内してもらいその家具のショールームに一歩、脚を踏み入れた時のなんともいえない衝撃と感動。イームズ家具を中心とするそのインテリアの素晴らしい事!ただただ感動の一言につきます。家具デザインってこんな素晴らしい世界なのか!なんと素晴らしい仕事なのか。その時、心に確信しました。光が射して天の啓示にちかい体験です。自分のやっている家具のデザイン、それも特に椅子のデザインとはこんなにも素晴らしい世界なのか。仕事なのか!それが可能ですでにやっている人がいるではないか!と
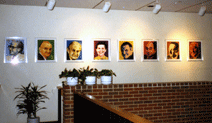
ハーマン・ミラー本社2階の
顔写真パネル

イームズチェアとイームズテーブル

アーゴン・チェアー

アーゴン・チェアーを生産している工場
1年目の秋、確かニューヨークトリップの前、素晴らしい出来事が!デザイン科の2階の窓から下を見ると、黒い服を来たレイ・イームズが笑って手を振っているではありませんか。もう1人の年配の男性とともに。クラスメイトも感激で大騒ぎです。そのあと、2人が我々のスタジオに廻ってきます。前年、チャールズ・イームズが亡くなり。イームズ夫妻の時のハーマン・ミラー社内の担当デザインディレクター、ボブ・ブレークと一緒にジーランドのハーマン・ミラーを訪ねたあと久しぶりに母校のクランブルックに立ち寄ってくれたのでした。私のスタジオにもきてくれ、しばらく話します。記念写真取ったのがこの写真。私が日本人であるというと、私も日本が大好き、日本に行った事がある。素晴らしい体験だったと高い声でいいます。(marvelousマーベラスを連発)日本の人形、おもちゃ沢山持っている。クランブルクが終わったらどうするのかというので、希望としてはアメリカで働けたら少し働いて日本に帰るというと、帰るときアメリカの南部をドライブして(大陸横断)して帰る事をすすめる。素晴らしい体験が出来るはず。そしてロスのベニスにある「901」スタジオにも来なさい!あこがれのイームズが目の前にいる。それも先輩として。信じられない!この出会いも留学しなかったらなかったこと。
2013年2月13日 井上 昇
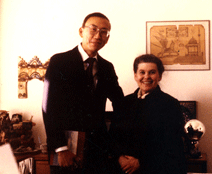
レイ・イームズとスタジオで
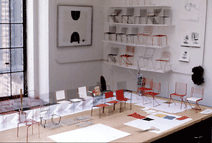
クランブルックの個室スタジオ
● 井上昇のいすの話-34 Part 2
話はもどってクランブルックでの生活を述べてみたいと思います。最初は1年間の留学でもと考えていた事は事実です。しかしクランブルクでの生活がはじまりアメリカでの生活が実際にはじまってくるとその一年はあっという間に過ぎてゆきます。そして学校生活を送るうち、ビザが有効な2年間いれるならいて何とかして卒業までいたいと思う様になりました。1年では修士はとれませんが2年いればとれます。もともと修士を取る事が目的でなく2年間のアメリカ滞在が目的でしたが、周りは修士を取るのが目的のクラスメイトばかりです。ちなみにクラスメイトのアメリカ以外の留学生、特にアジアからの留学生は一部の例外を除いてアメリカに仕事を求め移民が目的の人がほとんどという事も解ってきます。そして2年目は1年目は無理だったスカラーシップもとれそうな事もわかってきました。家族もきて生活も落ち着いて来るとこんな経験は今後一生で2度と出来ないだろうと思うと希望は確信に、そして実行に!
1年目の課題
1年目は夢中でグループ課題、共通課題のディスプレイ・グラフィック・照明器具・ニューヨークフィールドトリップなどになれない英語とも絡まって夢中で取り組むうち、すぐクリスマス休暇に入ります。アメリカでの初めてのそれも雪に埋もれたクリスマス。私の家族が住んでいたクランブルックのあるブルームフィールドヒルズ市は、デトロイトにおけるお金持ちがたくさん住んでいる地域でデトロイトのベバリーヒルズともいわれる所です。GM:ゼネラルモータースやフォード・クライスラーなどの経営者や高級社員などのエリートが多く住み、アーサー・ヘイリーの小説「自動車」の舞台になった所としても有名なところです。この地域は小さな湖や池が沢山ある所で自宅の中に湖があるという家は珍しくなく、学校の近くにフランク・ロイド・ライトが設計した住宅も何軒かありその中に有名な「スミス邸」もあります。クランブルックの敷地の中にも湖があり雁の群れは日常的にいますし(見かけによらずけっこう獰猛、糞公害に悩まされる)白鳥も浮かんでいます。そんな高級住宅が沢山ある地域ですからクリスマスシーズンの各家の飾り付け・イルミネーションは趣向を凝らしていて、家族で車に乗りその飾り付けた美しい家々を見て回るのはまさにディズニーランド!買い物に行くモールというショッピングセンターもクリスマスシーズンはサンタも出て来て家族持ちには楽しい所。日本では見れない楽しさです。こういう所が家族留学の良さでしょうか。


クランブルックキャンパス内の壁面ギリシャ彫刻(左側)と湖:キングスレイク
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストンへ」 | |
| 2013年06月29日(金) | |
| 「クランブルック2年目」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |
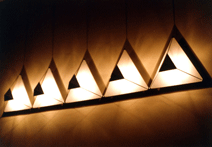
照明器具課題
壁面トライアングル照明
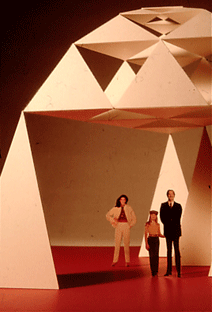
ミュージアムのディスプレイ課題
三角形の立体組み合わせ
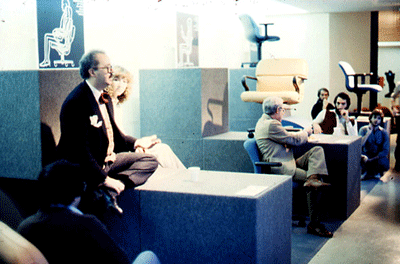
ミュージアムでのノル社の展示とセミナー。外部講師によるセミナーは大学院の必須授業。
クランブルックの先輩でアメリカにおける椅子の人間工学の権威で椅子のデザイナー、
ニールス・デフェリエント氏の椅子の展示。
抽象造形演習-1:ワイヤーによる彫刻
私は高校の時から油絵を描き始め武蔵野美術大学時代もその後も絵を描いていました。それは高校時代の美術部の仲間と先生とのグループ展を会社に入って社会人になってからも28歳頃まで続けていましたが、会社が忙しくなるにつれ中断し7年以上止めていました。私にとっては絵を描く事が椅子の創作に変わっただけで2つの事は創作という趣味でもあり実務でもありながらも共通性があります。絵は平面芸術(2D)ですが椅子は立体芸術(3D)、使える彫刻という捉え方です。その絵もただ景色や人物、静物を自己流にかくいわゆる印象派的な絵画を描いていてもマンネリと限界もあり、パウル・クレーやワシリー・カンジンスキー、ジャクソン・ポロックやピエット・モンドリアンのようにいつか抽象絵画に踏み出さなくては絵を続けられないというジレンマが久しくあり、それも絵を中断していた理由でもありました。
現実には生活の糧を得る忙しい会社つとめの中でお金にもならない絵を描いてじっくりと抽象絵画を描く試行錯誤などという事も端から見ればただの暇つぶし、趣味としか見えませんが、しかし、私にとっては抽象的な創作の表現手法を手に入れるという事は絵だけでなくデザインの創作にとっても作品の質を上げる上で欠かせないことと思っていました。その為には仕事を離れての自由な時間が欲しいと思いつつもそんな時間は会社つとめでは全く無理とあきらめていました。
その実験を期せずしてクランブルックの自由課題で出来るという事になったのです。さらにクランブルックに来る理由の一つに、前の会社の開発部で入社以来6年目にして念願の開発部に移れ、好きな椅子を業務として出来た5年間、入社以来の遅れていた時間を取り戻すべく夢中で創作を続けていてエネルギーを出し切っていました。今後、この椅子の創作を仕事としてまた続けて行くとしたら、まず出し切ったエネルギーの充電と、帰国後、今後10数年つづくであろうこの先のエネルギーを貯めておく必要があると考えたのです。それにはそれまでの仕事の経験から今までとは違った「造形の自分なりの手法」を持たないとやって行けないとの思いがつよく感じていた時で、方向が見えないなりにダメ元でやってみる事にしたのです。
チャールズ・イームズがクランブルックで当初、始めたのが「Experimental Design」実験デザイン。この意味と私の意味と同じかどうかは別としてごく単純な事から取り組み始めました。「無」から「有」を取り出すのが創作だとすると良いと思う事をトライアルすることからはじめるしかありません。まわりからなんといわれようと!たとえ幼稚でも!
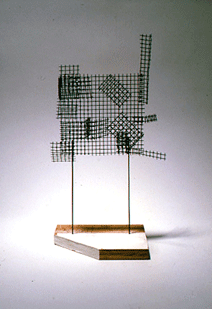
ワイヤー彫刻-1:空間演習
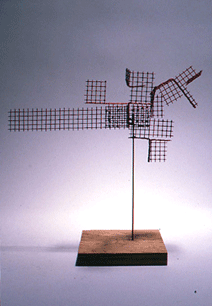
ワイヤー彫刻-2:空間演習
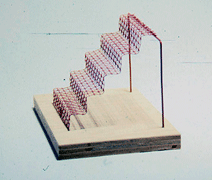
ワイヤー彫刻-3:
空間演習「ステップ」
抽象造形演習-2:平面と立体演習
まず平面(2D)から。
西洋は石の文化といいます。日本は木と紙の文化といいます。西洋の形はジオメトリック、即ち幾何学です。その形の基本は、○と□と△。日本は自然の形、現象を形に取り入れます。その二つの共通の原型、形とは!
平面の点・線・面は共通です。2000年前も現在も変わらないものは今後2000年経っても変わらないでしょう!タイムレスの造形を作るとすればタイムレスの形にすればタイムレスになります。椅子も同じです。
点と面はさておき、線の形から徹底的に拾いだして行きました。まず、1本の線。太い線もあれば、細い線もあります、何本も並べればストライプの模様が出来ます。そのストライプの線を90度で交差すればグリッドが出来ます。斜めにすれば違った形。カーブを付けた線では色々な模様が出来ます。線を点にすれば雪の様に美しい水玉模様が出て来て、小さな水玉は小紋になります。グリッドの反転は四角のパターンになります。そんな形を10cm四方の紙に書き付けてどんどん壁に貼って行きます。

クランブルックキャンパスの窓:
ステンドグラス
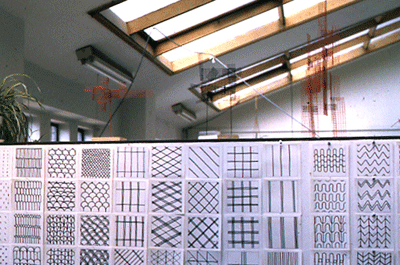
平面演習:線のパターンの洗い出し
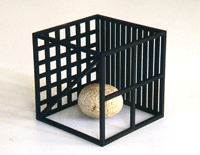
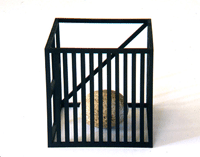

写真説明:2Dから3Dへ:ストライプ&グリッド・水平・垂直・斜め・ナチュラル
抽象造形演習-3:ワイヤーチェアー演習
次にその意味を受け継ぎつつワイヤーネットで形を作って行きました。紙の様にカットしたり、曲げてみたり。それを彫刻やレリーフにしてみます。黒や赤の塗装を吹き付けると空間造形に見えてきます。その後、そのイメージを1/5椅子らしき椅子の模型に置き換えてみて色々と試してみます。最後に1/5模型と同じイメージのものを実物の大きさにスチールロッドを使って一脚製作。当人は大まじめにやっていますが、端から見たら椅子のおもちゃか、ただの遊びのようなものに見えていたと思います。美術学校というのは大学院といえども端から見れば大まじめにゴミをいっぱい作っているような所です。これが一年後期のやっていた私の取り組み。あっという間の1年の後期も終わりに近づき、2年に進級するには各自が所属する科の担当教授を除いた各科の8教授による個別の進級判定審査がありその時にこのやって来た取り組みを説明します。その審査がとうらなければ2年生に進級できません。
期末、各個室スタジオに審査官!がやって来て彼らの質問に答えます。いまでも良く覚えているのは建築家の教授、ダニエル・リベスキンです。当時から建築のない建築家として注目され理論家として知られた人でした。クランブルックでもジューイッシュとしてその頭の切れの良さは目立っていました。日本でいうなら若き時の黒川紀章のような人といえばいえるかもしれません。彼の審査だけはとても緊張しましたが無事合格。ほっとした事を思い出します。という事で慌ただしい中にも5月、1年目のプログラムはおわり、9月までの新学期までの約4ヶ月の長期休暇に入ります。
9月までの新学期までアメリカの学校は夏休みに入ります。ほとんどの学校はその間閉鎖されるので学生寮も閉じ、出なければなりません。学生はその間、自宅に戻ったり、旅に出たり、アルバイトにいったりインターンシップに出かけたりそれぞれの休暇を取ります。大きな大学は夏期授業やサマーセミナーを組んだりもします。
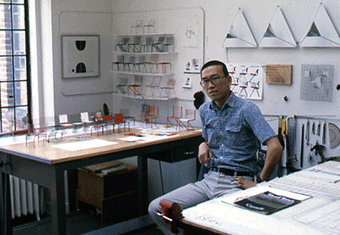
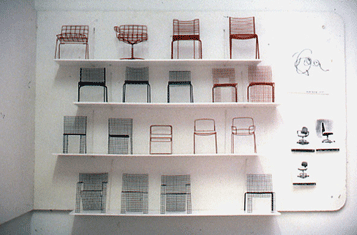
(写真左)1年目の個室スタジオ:各自に個室が割当られる。(写真右)ワイヤとワイヤーネットによる椅子モデル作成




1/1ハンドメイドフルサイズワイヤーチェアー:1年目の椅子作品
● 井上昇のいすの話-35 Part 2
アメリカの学校は9月が新学期なので日本でいう夏期休暇・夏休みというものはありません。ですから、夏休みの宿題という日本なら休んでいても何となく気になる縛りは全くありません。日本人がアメリカの学校に留学するとそのあたりの習慣から来る違和感を感じるでしょう。わたしもそうでした。一年目のカリキュラムが終わってクラスメイトもそれぞれ学校から去り、学校も閉鎖されます。といっても事務所とかアートミュージアム、博物館等は開いています。
この休暇の間、良い気候なので家族と一緒に英語学校のあるミシガン大学のアナーバーのキャンパスや大きな科学博物館へ行ったり、奥さんが日本人でアメリカの人と結婚し、親しくなった家族や、家内の幼なじみでアメリカで開業していて近くに住んでいる韓国出身の医者の友人等との交流も楽しい経験です。シカゴへは夏休みになってすぐの6月、アメリカ全米家具見本市「NEOCON」にも家族をつれいきました。シカゴでは元勤めていた大手家具会社の重役や営業の部、課長クラス、開発部の元上司、先輩、同僚も来ています。一年ぶりに皆と再会。久しぶりに会った同僚との再会は懐かしくもあり、またすでに退職しているので会ってもすでに過去形で複雑な思い。孤独さが身にしみます。シカゴへ行ったそのあと、ホームスティしたウイスコンシン、ベロイトのホルメスの農場へ。その先、イ−ストグリーンビレにあるフランク・ロイド・ライトのタリアセン・イースト等にも再度行きました。その旅行から帰ってから、留学中の一番大きい旅行、家族と岩手に住んでいた私の姉夫婦と一緒に、ワシントンDC、ニューヨーク、ボストン、とカナダ、ナイアガラフォールの10日間程のラウンドトリップに出かけます。ニューヨークには私の従兄、日系アメリカ人でフォトグラファーのカズ・イノウエ(井上和行)がマンハッタンの37丁目にフォトスタジオを構えており姉達をそこに連れて行くのも目的の一つでした。
カズ・イノウエは一時期、日系ファッションフォトグラファーとしてニューヨークで活躍していました。10数年ニューヨークの中心街にスタジオを構えるという事はそれなりの仕事と収入がなければ出来ません。第二次世界大戦中は、母と妹とマンザナール日系人収容所に収容され、朝鮮戦争にも従軍した体験の持ち主です。カズのことは追ってお話し致しましょう。
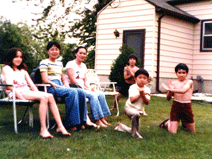
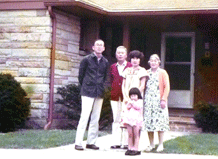
ミシガンの友人宅を訪問 ミシガンの韓国友人宅を訪問
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストンへ」 | |
| 2013年06月29日(金) | |
| 「クランブルック2年目」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

シカゴ市内で元上司と:NEOCON
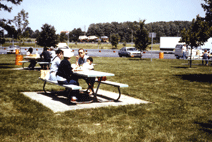
オハイオターンパイクパーキング
アメリカ東部ラウンドトリップ
道順はこんな感じです。
デトロイト(ミシガン)→クリーブランド(オハイオ)→
ピッツバーグ(ペンシルバニア)→ワシントンDC→
ボルティモア→フィラデルフィア(ペンシルバニア)→
ニューヨーク→ニューヘブン(コネティカット)→
アマースト、ボストン(マサチューセッツ)→
ニューハンプシャー→バーモント→モントリオール(カナダ)→
トロント→バッファロー(ナイアガラ)→ウインザー(カナダ)→
デトロイト(ミシガン)
 スミソニアン博物館
スミソニアン博物館
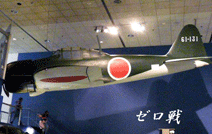 スミソニアン博物館:ゼロ戦
スミソニアン博物館:ゼロ戦
 ホワイトハウス
ホワイトハウス
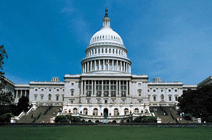 国会議事堂
国会議事堂
 シェファーソンメモリアル
シェファーソンメモリアル
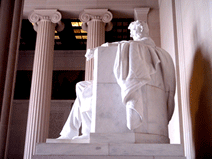 リンカーンメモリアル:お勧め
リンカーンメモリアル:お勧め
デトロイトからワシントンDCまでは約13時間。オハイオターンパイクを通って一気にワシントンDCまで運転を代わりながらドライブ。アメリカの夏は日が長く夜の9時頃ようやく暗くなります。朝も明けるのが早いので早朝、デトロイトを出発しドライブインで休みつつひたすら走ります。アパラチア山脈をこえて夕闇が迫る頃ワシントンDCに到着。モーテルに宿泊。翌朝、ワシントンDCツアーでは、ホワイトハウス、国会議事堂、リンカーンメモリアル、ジェファーソンメモリアル、スミソニアン博物館を中心に官庁街と大きなミュージアム巡りです。モールといわれる所が主な見学先。アメリカに来たら一度は来る所でしょう。ホワイトハウス・国会議事堂は必見です。大きなリンカーンの座像があるリンカーンメモリアルはアメリカの建国の歴史と自由を得る為にどれほどアメリカが血を流したかその事を体で感じる事が出来る所、お勧めの場所です。スミソニアンには月面着立船と月の石。リンドバーグの飛行機。それと日本の零戦を観ます。ジェファーソンメモリアルも行きました。ワシントンDCに車で行くと解りますが、モールの周辺はデトロイトと同じく下町であまり近づきたくない所です。ワシントンDCもアメリカの他の都市と同じくダウンタウンは荒れているという感じでした。ワシントンDCでは車のバッテリーが上がってしまい、パトカーに充電してもらったりハプニングもありました。2泊したあと、朝早く出発し、高速道路でボルティモア→フィラデルフィアを抜けてニューヨーク、マンハッタンへ。ワシントンDCから約6時間程で到着。マンハッタンは車の洪水で市内に入る時ビビりますが、なれてくれば東京と同じ。ニューヨークではクランブルックのニューヨークトリップの時滞在した、カズ・イノウエに教えてもらっていた52丁目イーストの安いホテルだが安全で場所が最高の小さなホテルに滞在します。
ニューヨーク
ニューヨーク、マンハッタンではお上りさんの通常コース、エンパイアステートビル、自由の女神、国連ビル、メトロポリタンミュージアム、SOHO、ワールドトレードセンター、ウオールストリート、ニューヨーク近代美術館(MOMA)等見て回ります。



トレードセンタービル 自由の女神 ユニオンスクエアー:カズのスタジオの近く
カズ・イノウエ(フォトグラファー)
その他、目的のカズ・イノウエの37丁目にあるフォトスタジオへ。当時カズは主に有名ファッション雑誌や化粧品会社のコマーシャルフォトを手がけており、ニューヨークでもトップクラスの写真家に混じって写真を撮っている日系写真家でした。ニューヨークでの写真家の競争は激しく17年間第一線で日系カメラマンとして活躍したのはパイオニアに属するのではないでしょうか。当時、まだ写真小僧というニックネームがついていた無名時代の篠山紀信がニューヨークに来たとき交流があったことカズから聞いています。
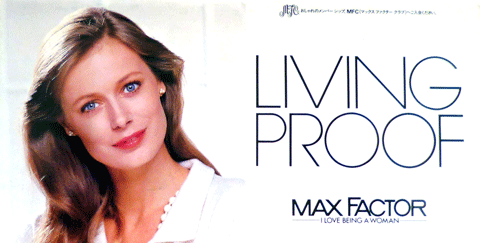 故カズ・イノウエの撮影写真と化粧品カタログ
故カズ・イノウエの撮影写真と化粧品カタログ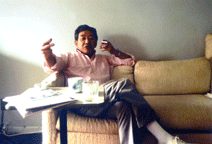 故カズ・イノウエ
故カズ・イノウエカズの体験からアメリカのフォトグラファーの仕事の取り組み方が聞け、ニューヨークというよりアメリカでのでの仕事の仕方も理解することができます。カズもしばらくVOGUのファッション雑誌や、化粧品などの仕事にも食い込んでいました。しかししばらくすると、編集者が変わったり写真のスタイルが飽きられるかすると、他の写真家に頼むということはよくあることです。ニューヨークには世界中から才能ある一攫千金を夢見るアーチストが沢山集まってきます。Aランクの仕事は報酬もよいので仕事があるうちは大金持ちになるが仕事が途切れると収入が無くなります。仕事が無くなると一挙に貧乏になるということはこういう事情です。Aランクを狙うことを目的にするなら、Bランク、Cランクに絶対苦しいからといって手を出さないこと。もし手を出したら、そのアーチストは2度とAランクには戻れないこと。ということはAランクのアーチストはひたすらAランクの仕事が来るまで我慢すること。我慢=仕事しない=貧乏になる!。この厳しい現実を耐えたアーチストのみAランクの仕事と報酬と賞賛を受け取れる。そのリスクとの付き合いがあこがれのニューヨークで仕事すること。カズも多額の費用をはらって自前のスタジオ37丁目に17年も構えていたことをみても戦後の日系2世フォトグラファーとしてのカズの苦闘がどんな物であったか忍ばれます。
そんなおり、スタジオを訪ねたのでした。カズの奥さんはスタイリストでカズの仕事の才能あるパートナーでした。カズからはこんなことも聞きました。女性のモデルはアメリカ人より北欧のモデルから選ぶことが多いと。その理由は肌の白さ、きめの細かさ。アメリカは日差しが強いので残念ながらアメリカのモデルは肌が荒れている場合多いと。またこんなことも、日本は良いね!アーチストも一度、良い仕事して認められるか、名が知られると先生になる。その後、実力が落ちても先生、先生と認めてもらえる。アメリカはそうではない。アメリカは競争社会で若い時いくら良い仕事をしてもその後、実力が落ちると誰からも尊敬されない。ちやほやされない。そこが日本とアメリカの違いだね!と。カズはその後、日本でのマックスファクターの広告写真などの仕事もしていましたがその後、ロスアンジェルス、ハンティントンビーチの実家に戻り60代後半、肺がんで急遽したのが残念でなりません。
カズの父親が私の父の10歳上の叔父・井上次郎で明治26年、1893年生まれ。久留米の屋敷の裏がブリジストンの創始者、石橋正二郎(1889年、明治22年生まれ)の屋敷があり、叔父は石橋正二郎の4歳年下。子供の頃は同じ町内での遊び友達、ガキ仲間として缶蹴り遊びをよくやっていたということを父からよく聞かされました。叔父はその後、神戸大学を卒業後、祖父の代で手放した屋敷を買い戻すためアメリカに出稼ぎに行き苦労した後、カルフォル二ア州スタックトンでレタス農場を経営、事業が軌道に乗った時期に交通事故で他界。その後、残された母親とカズ、妹はそのままアメリカに残り、戦争中、マンザナールの日本人収容所で生活。戦後、ロスアンジェルスに移り日系2世として成長。朝鮮戦争に従軍中、日本で奥さんとなる女性と知り合い、アメリカで苦労しながらもフォトグラファーとして成功。ニューヨークではアービング・ペンらとも交流があったこと聞いています。

井上次郎叔父・和行・久代・叔母

井上次郎叔父葬式:カリファルニア州スタックトン
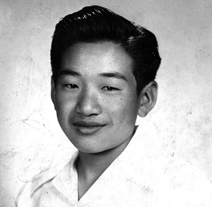
井上和行:14歳

イームズ・ラウンジチェアー
● 井上昇のいすの話-36 Part 2
ニューヨークではカズ・イノウエ夫妻とも会い交流を深めた後、朝早くニューヨークを出発。次の目的地であるボストンをめざしてドライブの旅はつづきます。ボストンへ行くにはコネティカット州ニューヘブンを通過するので有名なイエール大学に寄ります。ここの大学キャンパス内には建築家ルイ・カーンの設計した有名な図書館があってそれを見学。

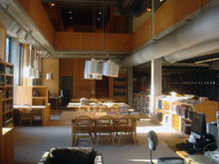
イエール大学:ルイス・カーン設計の図書館外観(左側)とその内部(右側)
その建物を見学し感銘をうけしばしの休憩をとった後、ルート91を北上。途中ハートフォードを通過して、コネチカット州からボストンのあるマサチューセッツ州に入ります。さらに北上、スプリングフィールドを過ぎて、ノーサンプトンから脇道へ。ボストンに入る前に私にとってどうしても寄りたい場所がありました。ボストンの西、マサチューセッツ州、アマースト。
アマーストにはアマースト大学があり、北海道大学の前身、北海道札幌農学校、初代教頭ウイリアム・スミス・クラーク博士の出身校です。(日本では「Boys,be ambitious」の言葉で有名な人物)そしてこのアマースト大学は明治時代、日本人では、新島襄、内村鑑三が若い時、学び滞在した大学としても知られています。内村鑑三は私の人生で最も影響を受けた人の1人でその著作はほとんど読んでおり、今から120年前の明治の時代、新島襄も含めてアマーストに滞在したその地に機会があればその同じ地に立ってみたかったところです。アマースト大学は他のアメリカの大学と同様、夏期休暇に入っていて学生はほとんど見かけませんでした。しかしキャンパスを散策し、構内の建物を外から見たほんの数時間のアマースト大学滞在でしたがとても満足でした。日本の地球の裏側、時間は短くても日本から遠くはなれたこのアマーストの地に120年前の内村鑑三、新島襄と同じ場所に立てたのですから。さて寄り道したアマーストからボストンに行くにはルート91で少し下ってスプリングフィールドに戻り、ルート90に入ってボストンまで一直線です。夕方ボストンに到着です。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年06月29日(金) | |
| 「クランブルック2年目」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

マサチューセッツ州アマースト大学

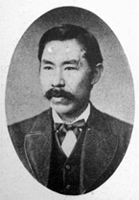
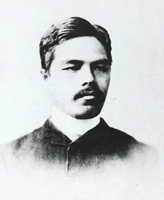
ウイリアム・スミス・クラーク(左)、新島襄(中)、内村鑑三(右)

1875年当時のアマースト大学
ボストン
ボストンでは市内観光をしました。州会議事堂は初めてボストンへ行く人は皆行く所。アメリカの独立戦争ゆかりの場としてアメリカのルーツを味わえるマサチューセッツ州らしさ、ボストンらしい雰囲気を味わえる所です。そのあと、ボストンと言えば何といってもハーバード大学見物。世界最高峰の大学のキャンパスに行き、東部地区特有のシックで重厚な建物群、キャンパスを散策しショップでハーバードグッズ(Tシャツ)を買いました。その他、食事とショッピングにクインシー・マーケットをのぞき、ビーコンヒルと言われるイギリスの町並みの香りがする住宅街を散策。アメリカの中でも東部、マサチューセッツ州は他のアメリカの州と比べ町並みが全然違います。アメリカで歴史とイギリスの町並みを感じられる楽しく美しい町です。日本で例えるならアメリカの京都と言える場所でしょうか。郊外にはケネディー家の別荘地がある事で有名なケープコッドや。メイフラワー号で有名なプリマスもありそれだけに保守的で白人文化圏とも言える所です。
ボストンの町は中部、西部のアメリカと違ってイギリスの雰囲気が濃厚です。歴史の浅いアメリカにあっては歴史を感じる町です。

ボストン州会議事堂
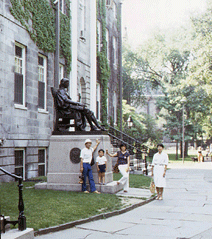
ハーバード大学キャンパスジョン・ハーバード像の前で

ボストン:姉とクインシー・マーケット

ボストン:ビーコンヒル
ボストンからモントリオールへ
ボストン滞在の後、次の訪問地ナイアガラフォールめざして北上。ボストンからナイアガラの滝に行くには、バーモント州を通り、カナダに入りモントリオール経由、トロント、ナイアガラというルートをドライブです。バーモント州はただひたすら走り、モントリオールにて宿泊。モントリオールはきれいな町です。カナダは町の中心部がアメリカと違って治安も良く、アメリカと比べると別世界です。モントリオールの夜の町の散策に出かけましたがにぎやかでヨーロッパの街にいる感じです。当時のアメリカの都市では夜の散策等ほとんどありえません。(今のアメリカは少し違っています)。モントリオールでは本当に久しぶりに日本と同じく、治安を気にする事なくリラックスして夜の食事と街歩きを皆で楽しみました。モントリオールは、カナダ独立前フランスの植民地だった街。フランス語が共通語であった所なのでフランス語の会話が聞こえるだけでなく、町の人々の服装や雰囲気がなぜかマイルドでフランスの町にいる錯覚に陥りました。それと、気がついた事は、町に繰り出している人たちの身長が低い事。これもアメリカと違う景色です。モントリオールに泊まった後、次の目的地トロントへ。

モントリオール

オンタリオ州トロント
トロントも綺麗な治安の良い街です。トロントでは美術大学時代の先輩がいてそのお宅を訪ねました。トロントは日系人の多い街です。トロントで一泊後、ナイアガラに行くにはトロントからハミルトンという街を経由してナイアガラの街までドライブの走行距離的にはいったん戻る感じです。ナイアガラの滝はアメリカとの国境が滝の半ばにあってアメリカ側にある滝をアメリカ滝、カナダ側にある滝をカナダ滝と分けます。人気があるのはカナダ滝の方で観光ルートとしてはカナダ滝が人気が高くお勧めです。ナイアガラの滝の観光は、昼の雄大な大瀑布もスケールが大きく楽しめますが、夜のライトアップされた滝もまた美しく人気です。ナイアガラの滝はアメリカでは新婚旅行の人気スポットとして有名ですが実際にみてみると、その水量の多い事、凄い迫力です。そばに立つと滝に吸い込まれそうな感覚に陥ります。都会の真ん中にある滝としても不思議な楽しい滝です。現地に立ってみるとアリゾナ州のグランドキャニオンとナイアガラの滝がアメリカで最も人気のある観光地である事に納得します。

ナイアガラの滝:凄い水量

ナイアガラの滝:夜景

カナダ・ウィンザー市から
デトロイトを望む。
● 井上昇のいすの話-37 Part 2
長い夏の休暇も終わって9月から2年目の新学期が始まります。余裕のなかった1年目と比べアメリカの車社会の生活習慣にもなれ余裕と緊張が入り交じった2年目の新学期。Cranbrookばかりでなく、全米の学校がBack to Schoolで活気が戻ってきます。新学期の9月はまだ暑いながら秋の気配が感ぜられる中、同期のクラスメイトも三々五々学校に集まってきます。新入生も1年前の我々の様にアメリカ国内ばかりでなく海外からの留学生も緊張したおもむきで入学してきます。2年目は上級生で先輩としてえばっています。


カール・ミレスの彫刻「ヨナ」(左側)とクランブルックミュージアムでのサマーショー:真中が井上の作品展示(右側)
ちなみに私の10人の同期生の中の留学生と言えば、カナダのクリストファー・オズブコ、レバノンのレイラ、日本(私)の3人。先輩では香港(エリック・チャン)後輩では、ドイツからアンジェラ・ヴィーガンド、フイリピンからルシール・タナザス、台湾からティンシン・シェイ、香港からゴードンの4人。他学科のクラスには、イギリス、ブラジル、タイ、韓国、香港、等。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年07月26日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

後輩と:真中より右へアンジェラ、井上、ティン、ゴードン

クランブルック独身寮
スカラーシップ
ボスカラーシップに関して言えば留学生はハンディーがあります。その理由は私が留学した時は、留学生は入学時に在学中の2年間の授業料を払えるという事を証明する証明書を提出しなければなりません。例えば銀行口座の預金で払える裏付けの証明書か支援者(親)の確実なる証明書類等。それに比べて母国であるアメリカの学生は入学時にスカラーシップを確実にもらえるか否か確認の上、学校を選ぶことも多くこの点でも留学生は成績だけではなくスカラーシップに関して言えば入学時にハンディーがあるといっていいでしょう。でもこれは致し方ない事です。私も授業料の1/3のスカラーシップをティーチングアシスタントという名目で頂く事が出来ました。その仕事はクラスメイト、後輩が模型等を作る時アドバイスしたり手伝うということのティーチングアシスタントです。額としては1/3の免除は多い方ではありませんがスカラーシップを頂けてうれしかった事は事実です。告白しますがそれではその模型をつくるお手伝いを沢山したかといえば、あまりしなかったというのが事実です。理由は自分の作品をつくるのに忙しいこと、家族留学だったのでキャンパスにいる時間が昼間の時間帯が多く、他のクラスメイトは昼はのんびりしたり、リラックスしていて夕方から夜、スタジオにいる事が多く、時間帯が噛み合なかった事や、1台しかない車で家族の生活もみなければならなかったという事も理由ではありました。同期のグラフィック専攻のクラスメイトは昼、デトロイトのデザイン事務所で働きながら授業料と生活費を稼ぎ、夜、学校に来るという人もいて、毎週、月曜日の朝10時、クリテックでクラス全員が集まるとき以外ほとんどすれ違いという仲間もいるというのが現実。でもその中で立体専攻や仲の良い仲間はそれぞれに集団を作り助け合って行く、そこが大学院という自由度のある所でしょうか!
それとこんな事もありました。入学したとき2年生で先輩だったはずの人が後輩として入学して来た事です。どうしてといったら1年在籍し、1年休学して働き、授業料が貯まったので入って来たという事。アメリカの学校はそんなことができるんだとびっくり。日本では考えられないそのシステムの自由さ。自立したその生き方!建前より実質と独立を尊ぶアメリカの学校の素晴らしさ。ちなみにこの魅力的な先輩で後輩の女性は後に、一時期、シリコンバレーにあるアップルコンピューターのグラフィックデザイン担当部長として来日した事があり、宿泊先のホテルオークラまで迎えに行き、日本人のクランブルックOBを集め、レストランで会食し飲食費は全部、彼女が支払った事もありました。
もう1人の1年先輩で親しくしてくれていたマイケル・ヘンシェスも一時期、ニューヨーク近代美術館(MOMA)のグラフィックデザイン部長として勤めていて彼と連絡をとってMOMAを訪ねたとき彼の館内のオフィスに案内されインサイドの彼の仕事の事を直接聞く事が出来たこと等、クランブルックのネットワークの凄さに卒業後も驚くばかりです。

クランブルック図書館

版画科のスタジオ:2年目専攻した。
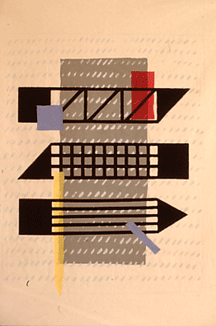
版画に挑戦:シルクスクリーン
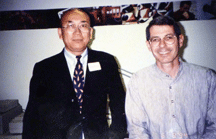
ニューヨーク近代美術館(MOMA)
事務所内でマイケル・ヘンシェスと
2年目の授業と卒業制作
2年目の授業も1年目と同じく後輩が入って来ていくつかのチームにわかれグループワークから始まります。そして恒例の10月の家具のイベント:デザイナーズサタディに合わせてのニューヨークフィールドトリップ。その〆はSOHOにあったKnollのショウルームでのパーティー参加。クランブルックのOBが沢山集まり同窓会が盛り上がります。9月半ばから始まった授業も共通イベントが終わると間もなく11月にはいり、雪の季節に入りクリスマスシーズンに!そして約1ヶ月の冬期休暇。1年目と違い時間が慌ただしく過ぎます。アメリカの卒業式は5月なのですぐ卒業制作のテーマを年内に決め課題に取り組まないと時間的に間に合いません。2年生と1年生と違う所はグループワークとトリップが終わると各自卒業制作に向けてのテーマに移ります。卒業制作のテーマを教授と相談しながら進めて行くことになるのですがそれぞれのオリジナリティーのテーマが求められて行きます。

ニューヨークフィールドトリップ
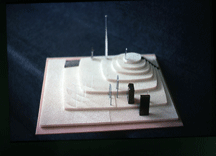
グループワークの模型
チャールズ&レイ・イームズ、フロレンス・ノル、エーロ・サリネン、ハリー・ベルトイア、デビット・ローランド、ドン・アルビンソン、ニールス・ディフェリエント。テキスタイル分野では大御所、ジャック・レナー・ラーセン、その椅子デザイナーの伝統校に在籍した日本人の椅子デザイナーとして続く事が私の願い・目的です。それで大変なリスクを取りここに来たのですから。
特にハリー・ベルトイアのワイアのチェアーは彼がクランブルク彫刻科の教授であったとき、この同じキャンパスで創作したものです。彼のワイヤーを作った彫刻も大好き。クランブルクに留学しさらにベルトイアの作品を身近に(クランブルクミュージアムに展示されている)接するうちにベルトイアに魅了されていきました。
私もハリー・ベルトイアにならってクランブルクの卒業制作には実物のワイアーチェアーを作ってみたいと思いました。1年目に人間工学の1型のワイアーのダイニングチェアーを作っていたのでさらにラウンジチェアーから6型、チェースロングーからベンチ、テーブルまでトータルで作る事と!ベルトイアーに倣って同じ、ミシガンのデトロイト郊外のこのクランブルクの彼と同じ場所でワイアーチェアーを作ろう!テーマは決まりました。
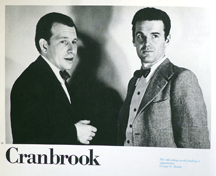
エーロ・サリネンと
チャールズ・イームズ

ハリー・ベルトイア
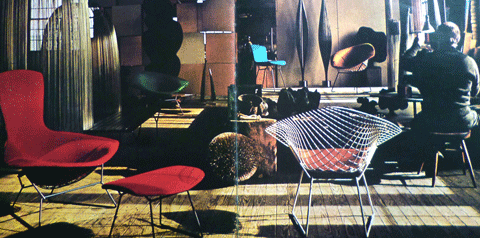
ハリー・ベルトイアとスタジオ
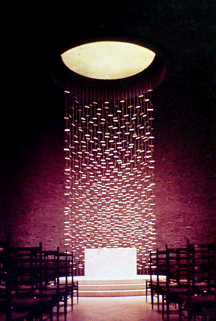
ケンブリッジ MIT大学:
チャペルのベルトイア彫刻

ベルトイアチェアー
● 井上昇のいすの話-38 Part 2
年が明けた2年目の冬、ミシガン州はアメリカの中でも北部に位置する事もあり冬の1〜2月、寒さが厳しい時は平均マイナス10度前後、ブリザードが吹くとマイナス20度以下になる事もあります。ただ日本の雪と違い寒いので積もる事なくさらさらしています。暖房もしっかりしているので室内は学校もアパートも快適。という事で外に行くのは買い物か学校の行き帰りという事であとはクランブルックの自分専用のスタジオにこもってひたすら課題と取り組みます。英語の方は相変わらず苦労しながらも日常会話にはなれ留学生仲間やクラス仲間とのキャンパス生活と、家族とのアメリカ生活を楽しみながら卒業制作に集中して行きます。
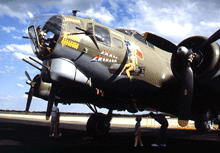

B-25爆撃機:アメリカではこんな飛行機が見れる(左側)冬のクランブルックキャンパス(右側)
1月、図面を描く事は考えず、アイデアスケッチからワイヤーネットを使って1/5モデルを気の向くままフリーハンドで作っていきます。5月には卒業になるので4月中にすべてを完成せねばなりません。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |
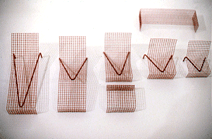
ワイヤーネットによるハンドメイド縮尺モデル

ワイヤーチェアー製作風景:木枠ゲージとワイヤーとアセチレンバーナーとロウズケ棒
アメリカと日本との工作環境の違い
アメリカと日本と違う所、それは工作道具、溶接の簡単な日曜大工セット、等が気軽に安く手に入る事です。今は日本でもD2とか東急ハンズとかそれに近いものはありますが、アメリカ生活した経験のある方なら理解できるとは思いますがその質とバリエーションが半端でないのです。これはアメリカ人の気質と環境に寄る所が多いと思います。アメリカでは一戸建てはもとよりタウンハウス、アパートメントも含めて地下室があります。それと母屋とは別に車を入れるガレージがあって、作業スペース・場所はたっぷりあります。そしてアメリカ人は日曜大工が大好き!趣味をこえてプロに近い強者がいっぱい。たとえば車の場合、日本車は嫌いだという人がいます。その理由は日本車は故障しないから修理する楽しみがない、必要がない、だからつまらない?という人や、住宅の建て増し、修理、模様替えは全部自分でやるという人が沢山います。一つには自分でやった方が経済的という事もありますが、趣味としてやる楽しみを他人にお金払ってまでと考える人も多いのも事実。人によっては自分で自分の家を立てる人もいます。開拓者魂がいまも根づいている。そのニーズに応えるべくホームデポという大きなストアでは家具はもちろん、建築資材であるドアー・サッシ窓は勿論、トイレから風呂場・下水管に至るまで何でも買うことができます。そしてそれを加工する、工作機械・バンドソーから電動ノコギリ・溶接の道具までほどほどの価格で手に入れる事が可能です。日本と比較するとどう違うかといいますと、日本の場合、木工場で本格的に使う工作機械はあります。あと、簡単な工作に使うシンプルな工作機械はありますが、アメリカの様にアマチュア以上プロ以下のパワフルな中間の日曜大工向けの道具が全くありません。ここが大きく違う所です。充分な作業スペースと本格的な日曜大工のパワフルな道具。何でもそろう色々な道具、たとえばハンドボンベタイプのロウズケ溶接のセット。卒業制作で調達した材料、製作に使った簡単な道具類、日本でも手に入りそうにも見えますが実は大変難しいのです。この環境はアメリカでは当たり前の事が日本では当たり前でない事が多く、ものずくりのベンチャーを起こす若い人に取っては大きな大きな差になるはずです。今はアメリカでも屈指の企業であるアップルコンピューターもスティーブ・ジョブが車のガレージから起こした事は有名な話ですよね!という事で私もクランブルックのデザイン科の教室の地下室にひたすら籠って約8週間、ほぼ毎日1人で実物のワイヤーチェアー作りに没頭しました。このような誰からも拘束されない時、自由な時間は留学する以前、会社に勤めていた時はもとより、留学から帰国してからも厳しいフリーランスの緊迫した時間の中で持てたことはありません。今もそうかもしれません。その意味でサバティカルタイムとしてのクランブルックのこの2年間半の留学期間は経済的には私にとって最悪の時ながらも自由に活動できた最高の時だったのです。人生にこんな時って滅多にないですよね!お金は後で取りかえせるかもしれません。しかし、時間は取り返せません。人生の時間配分は勇気が必要です。
全7タイプワイヤーチェアー&テーブル完成
計画しつつかつ気の向くまま人間工学のプロトタイプにそって作ります。最終的に製作した椅子は次のアイテム。計画した椅子全部を作ることが出来、間に合いました。
1)ラウンジチェアー、2)ハイバックラウンジチェアー、3)オットマン、4)チェイスロングチェアー、5)車付き、背の角度調整付きロングチェアー、6)3人掛けベンチ、7)ワイヤーロー丸テーブル、8)チャイルドラウンジチェアー、合計8個。それぞれのタイプの木ワクのジグを作りワイヤーをクギで止め縦横のステールロッドをワイヤー固定しつつ、ハンディ−タイプ、アセチレンバーナーでロウズケし、後ではみ出たステールロッドを鉄ノコギリでカット。アルミの脚を取り付けた後、最後に木製の木をはかせブラックとホワイトのペンキで塗装。椅子が出来たら上にのせるクッションの作成です。

(椅子のプロトタイプ4型)

ラウンジチェアーと
レッドファブリック

ラウンジチェアーと
ブルーファブリック

ラウンジチェアーと
イエローファブリック

ラウンジチェアーと
フルカバリング

ハイバックラウンジと
フルカバリング

ハイバックラウンジと
オットマンクッション付き
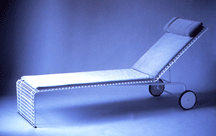
車付き、背の角度調節付き
ロングチェアー
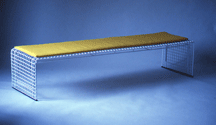
三人掛けベンチと
クッション付き

チェイスロングチェアーフルカバリングクッション付き
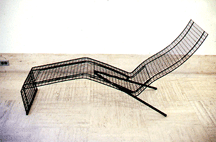
チェイスロングチェアー
ワイヤーフレーム
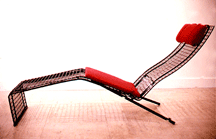
チェイスロングチェアーと
クッション付き
そのショウルームがデトロイトの中心部、例のアメリカの自動車会社「GM」ゼネラルモータースの本社がある同じビルのモール内に Knollのショールームがありそこで購入しました。クランブルクから片道40分程の距離です。中に詰めるクッションはホームセンターで購入。座面の中はパンチカーペットを芯としてそのまわりに薄いクッションとプラスチックの綿を巻いて作り、背は薄いクッションとプラスチックの綿、ヘッドレストも背と同じく丸めて整形して作成しました。ミシンがけは全部自分でやりました。Knollのファブリックはウールとナイロンの混毛。カラーも良く、黄色の平織りとモケットの赤と青の2種類。絵画と同じく色の3原色を選びました。

クランブルック中庭にて、全アイテムと私
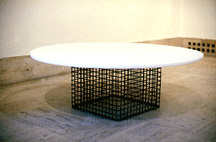
ワイヤーロー丸テーブル

チャイルドラウンジチェアー含む
全アイテム
海外と日本のテキスタイル事情
椅子に取ってクッションのファブリックはとても大切です。「孫にも衣装」というごとく人間は中身より外側の見栄えに影響されやすく、それ以上に肌に接する部分になる触感は椅子の価値をも左右するのです。このファブリックのデザイン、クオリティーにおいては日本は良き伝統がありながら欧米に著しく遅れています。その1つの原因は才能あるデザイナー、テキスタイルメーカーがないのではなく、ファブリックデザイン及びファブリックデザイナーがその創作において生活できるロイヤリティーの支払いの習慣がないことによります。現実には社内デザイナーがあちこちの売れているテキスタイルを適当にアレンジしながら製品化していて、今でも良い椅子張り布を欲しいと思えば海外、イタリアやデンマーク・アメリカ・フランス等から購入せざるを得ません。しかし、質も良いかわり価格は高いのです。その高い理由はその創作者であるテキスタイルデザイナーのロイヤリティーが入っているからです。でもこれは椅子も同じです。製品のデザイン料をしっかり払う。そして良い製品が会社をいい業績に導く。これがよい会社の循環です。今の日本でもこのルールを取ったことによって会社が劇的に変化したケースが沢山あります。身近なところでは徳島の「宮崎椅子製作所」等もそのひとつです。
● 井上昇のいすの話-39 Part 2
卒業の課題は最後の追い込みで形になりつつあります。自費留学でお金もないなかともかくも椅子の伝統あるクランブルックのキャンパスで自分で作りたいと思ってた椅子を会社の仕事でなく、生活の為でもなく卒業制作で思う存分作れたということはとてもうれしく贅沢な時間でした。帰国してからも20年間こんな時間はもてませんでしたが今は違います。今は自分でデザインしたい椅子を自分で決めて自分で製造し(委託)自分で販売していますから自分で作りたいという椅子をクランブルックの時と同じく作れるようになりました。今は木の椅子ですが素晴らしい日々です!
クランブルックの2年目は他の学科も学べるというクランブルック特有のシステムがあります。そこでプリントメーキング(版画)の授業を選びました。校舎が同じビルで2階がデザイン科、1階がプリントメーキング。同期生の西田有輝さんがいます。それと先生がカナー・エバーツ。親父タイプで包容力があり才能も抜群。日本でなくアメリカのアーチストに直接学べるチャンス等そうあるものではありません。それ以上にそのプリントメーキング科の設備の凄い事!リトグラフに使う石板が沢山あるのです。日本では今でもこんなに環境の整った版画設備を揃えた所はないでしょう。そこがアメリカの学校なのです。日本の精神主義と違いアメリカは良い意味にも悪い意味?にも物質主義です。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年07月26日(土) | |
| 「卒業制作に向けて」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |
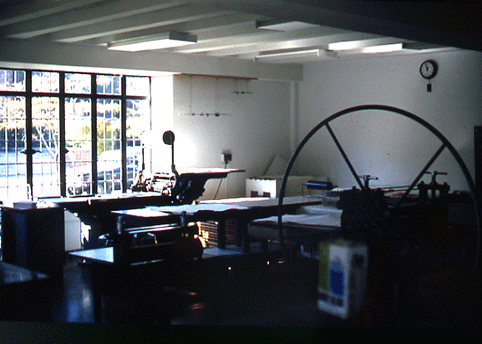 プリントメーキングスタジオ
プリントメーキングスタジオ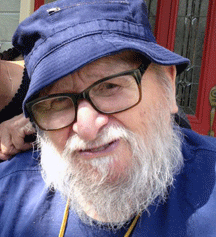
カナー・エバーツ元教授
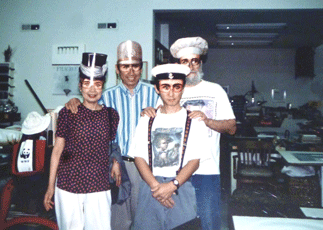

シルクスクリーンは何にでも印刷できるので和紙の他にアクリルミラー板、綿キャンバス等に印刷して作品を制作。私の気持ちの中ではまず、点・線・面のパターンと西洋の造形の基本形である、○・△・□(丸・三角・四角)の組み合わせ。色は3原色、赤・青・黄色の組み合わせで平面の絵を印刷し、それを立体のオブジェにし、そこから椅子の形に発展させ椅子をデザインする。その原型であるアートとしての版画に挑戦したのです。その版画を徐々に3D、即ち立体へ。最初はワイヤーチェアーに発展しましたので今度はシステムベンチ、システムソファーへ。
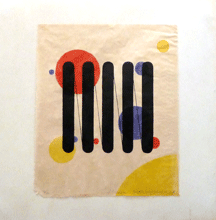
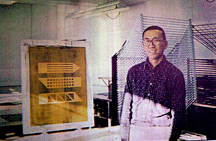
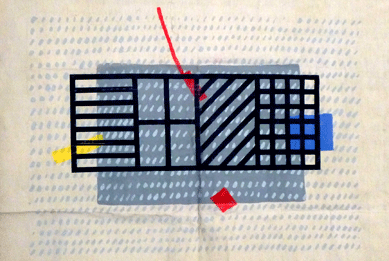
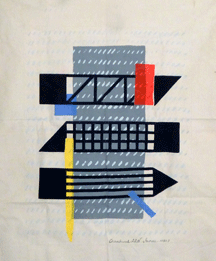
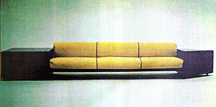
ソファーベンチ」
あと私の時はそのスタート時期でしたがアメリカのデザイン界では先に述べた隠喩としてのデザイン表現手法「プロダクトセマンテックス」にもトライしました。私の場合はアメリカの高速道路の標識を支えるパイプの構造支柱の形をソファベンチに取り入れてみて模型を作ったりしました。今ではすっかり蔭を潜めていますがこの隠喩というデザイン手法は実際にはよく使われているのです。別の表現でいえば「かわいい」「セクシー」「クール」「日本的」等はこの隠喩の別の形かもしれません。
私に取って版画を少しだけですが専攻したのは素晴らしい体験でした。その理由はその後今に至るまで版画を製作していませんし(版画は印刷の設備がないと難しい)その教えていただいた先生、カナー・エバーツと彼がクランブルックを去り、ロスアンジェルスに戻ってからも度々あい交流が続いているからです。
海外で働くことと海外に留学する事の大きな違い、それは人脈だと思います。ある一定期間、学びの場で共に学び、食事を共にし、共に助け合い、良い意味でのライバルであったり仲間であったり、まして海外から言葉も苦労しながら助けられたり助けたり、自由ながらも狭いキャンパスで卒業までの苦楽を共にするという共通体験の中では働く会社では得られない何かが生まれます。ましてクランブルックのような少人数の学校ではその密度は高いと私は思います。しかしそうきれいごとばかりではありません。後輩の中では不倫関係で子供をつくりそれが留学の目的だったのではというケースもいたり!みな若い男女の独身の学ぶスクールでは将来の伴侶を求めて入学する人もいるでしょうし、入学と同時に同棲し卒業と同時に別かれてそれぞれの仕事を求めてアメリカ中に散って行く。そういう学生もアメリカでは多い事も事実です。学園生活でのイベントとしてはハロウイーンの仮装パーティーが特ににぎやか!子供は外で家々を訪ねあるきますが学生はキャンバスの寮内でのお祭り。バニーガールが沢山出て来たのには驚きましたが日本と違って白人のそれも若い美術専攻の美人ぞろいのバニガールはどんな感じか想像にお任せします。男子学生も普段は髭もじゃで服もラフでどちらかというと乞食?に近い服装が普通なクラスメイトもタキシード等の服で仮装して来ると全く別人。実にかっこ良く洋服はつくづく白人の服なんだという事を認めざるを得ません。欧米人と日本人を含む東洋人は如何に体格が違うか、スタイルが違うか一緒に生活していると思い知らされるのも留学の体験の一つです。
しかし、悪い事ばかりではありません。彼らと同じキャンパスに2年間共に生活しているとこんな事にも気がつきます。少数ですが若いお嬢さん方も太りやすい体質の方、脂肪がつきやすい方が多い事。これはアメリカの食生活にも寄るのでしょうが暑い夏にはTシャツや短パンで過ごす事が多いのでそれがよく観察できるのです。すらりとした脚を想像しますが脂肪がまとわりついてぶよぶよ形の脚の人!私は「椅子のデザイナー」なのでどんな体型、体重の方が椅子に座るのかどうしても人間の体型に目がいってしまいます。欧米人にとって椅子に座っての快適な高さ、角度、大きさ、寸法とわれわれのように小柄で、胴長短足の日本人との違い。外国に旅行でなく、滞在型で長期間いるといやでも目に入ってきます。アメリカに留学後、展示会を見にヨーロッパ、特にドイツとイタリア、デンマークに何度もいく機会があり、東ドイツではバウハウスセミナーで2週間デッソウ・バウハウスに滞在したおりでは東欧諸国の人とも会う機会があり、その関係でチェコやハンガリーにもいく機会がありましたが、ヨーロッパの人とアメリカとは同じ白人でも体型が似ているようでもありながらずいぶん違うという事も感じます。その土地、土地での食生活が人間の体型を変えて行くのだと思います。でもただ一つ言える事は小柄な日本人には小柄な日本人向けの椅子が快適な生活を送ろうとすれば絶対必要だと確信した事です。これは今も全く同じです。こんな事を体験しながら卒業制作も無事完了し、クランブルックミュージアムでの卒業制作展にワイヤー椅子を展示。卒業式を迎えるばかりになりました。
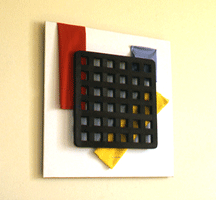 「グリッド+3原色布立体絵画」
「グリッド+3原色布立体絵画」
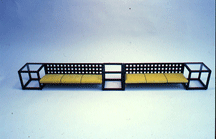 「グリッドシステムベンチ-1」
「グリッドシステムベンチ-1」
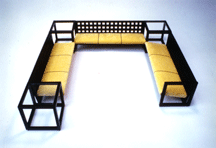 「グリッドシステムベンチ-12」
「グリッドシステムベンチ-12」
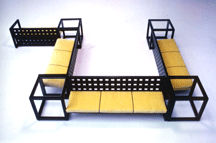 「グリッドシステムベンチ-3」
「グリッドシステムベンチ-3」
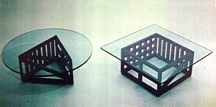 「グリッドテーブル」
「グリッドテーブル」
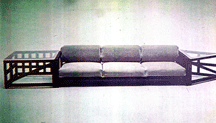 「グリッドソファー&テーブル」
「グリッドソファー&テーブル」
● 井上昇のいすの話-40 Part 2
アメリカの学年の終了は5月です。9月の紅葉の時に学期が始まり初夏に終わる。修士論文を卒業制作の作品写真をもファイルし編集、作成します。それを専攻の科の教授に提出しサインをもらいます。今はパソコンでまとめますが、私のときはタイプライターです。そしてその卒業論文ファイルは卒業生全員、クランブルックの図書館に永久保管されます。私が死んでも保管され続けるでしょう。そしていつでも閲覧できる様になっています。私は日本人ですから日本の留学生の先輩の卒業論文、ファイル等も閲覧し、参考にしながら作成しました。日本で知られた名前では建築科の卒業生の中に「槙文彦」氏がいます。槙さんはクランブルック卒業後、ハーバード大学の大学院に行かれています。
美術の大学院大学ですから各科の全員の卒業制作をキャンパス内のクランブルック・ミュージアムに展示。最後に卒業式で一人一人名前を呼ばれ、学長から修士号(MFA・マスター・オブ・ファインアーツ)の卒業証書を受け取り、2年間のクランブルックでの学業生活は終わります。2年、正確には9月に始まり5月に終わりですから1年と8ヶ月の大学院の生活に終止符を打ちました。2年生の後半は卒業制作のワイヤー椅子7脚の製作に夢中で過ごし、滑り込みで完成と同時に卒業制作展。卒業式も終え卒業するという留学の目的は達成です。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年07月26日(土) | |
| 「卒業制作に向けて」 | |
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |


クランプルック・ミュージアムでの卒展:1981年
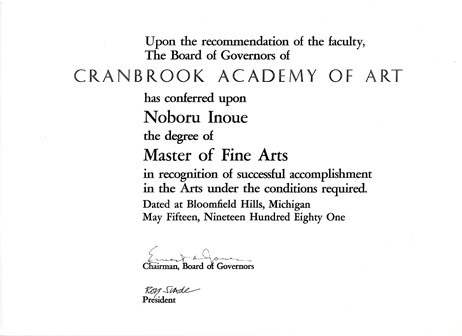
クランブルック卒業証書「MFA・修士」
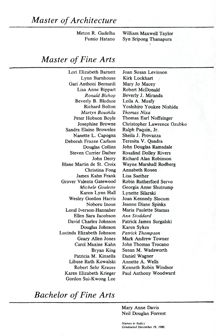
全学科同期73名の卒業生リスト
私の名前は、左下から14番目
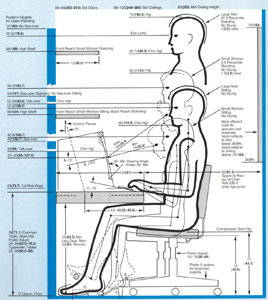
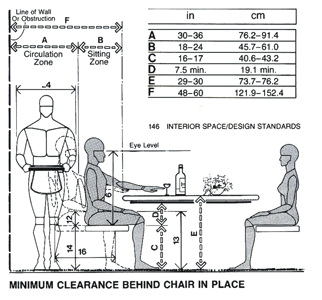
卒業式が終わるという事は卒業後の生活が始まります。アメリカのクラスメイトはそれぞれに就職をさがし、ニューヨークや地元に戻ったり大学の教員になるべくジョブハンティングに散って行きます。留学生にはアメリカの大学院に在籍すると卒業後半年間の滞在ビザが許可されます。クランブルックに来るアメリカ人は修士号を取るのが目的で大学の教員になる事をめざす人が多く、留学生は就職して滞在ビザを取得しアメリカに移民する事を目的にする人が多い事が現実です。ですから日本人は留学後帰るというとなんで帰るのと度々いわれました。私は可能なら卒業後アメリカで仕事ができるならしばらく就職してから日本へ帰ろうかなとアメリカに留学する一般の日本人と同じ考えでいました。しかし、クランブルック在学中に私のデザイン科の担当教授、マイケル・マッコイと同じミシガン州立大学出身で仲のよい、アメリカの大手家具メーカー、ノル・インターナショナル社のデザイン部長が、私の在学中、クランブルックに度々来ていて、私の卒業制作の椅子に興味を示してくれたことを幸いに、ノル社に製品化の提案を申請する事にしたのです。
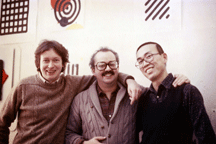 デザイン部長をはさんで教授と私
デザイン部長をはさんで教授と私クランブルック内にて。
3人とも同じ年
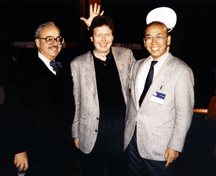
クランブルック卒業から5年後
ワシントンDCのデザイン会議にて
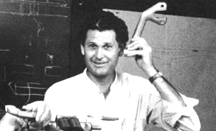
ドン・チャドウィック
後にビル・スタンプと共に
アーロンチェアーもデザイン。


ニールス・ディフェリエント
デザインのノルのベンチ

ニールス・ディフェリエント氏
とシカゴのネオコンで・10年後
いつまでも中途半端な形でアメリカに家族を抱えて滞在する事も出来ず、その限界もありある意味でケリを付けるためと、せっかくのノルのデザイン部長の配慮をありがたく受け止め、面接に行く事にしました。そこでもし万が一就職することになったとしたら、どんな所に住むことになるのかその場所の確認と、卒業後の久々のアメリカ東部のドライブ旅行をも兼ねてペンシルバニア州の東の外れにあるイーストグリーンビレに家族と一緒にいくことにしました。イーストグリーンビレはアメリカでは中東部、ミシガン州デトロイトと違ってフィラデルフィアやニューヨークに近くアメリカ独立の建国の地、東部に属します。人種問題抜きに考えられないアメリカという土地柄から考えると、日本人という立場からはカリフォルニア州に住むのは日本人も多く、それほど人種的偏見は少なく、むしろ日本人はまじめで優秀というイメージが比較的、定着して住みやすいといわれていました。日本の会社の駐在員ならまだしも、一般の日本人が東部、それも大都会ではなく郊外の町に住むのは何かと難しいと私の留学した当時はそんな雰囲気がありました。

ペンシルバニア州ピッツバーク

ペンシルバニア州アレンタウン
そのドライブの途中に私達の家族にとって行きたかった所、訪問したかった所があります。一つ目は途中のピッツバーグの郊外にあり、フランク・ロイド・ライトが設計した最高傑作の一つ、フォーリングウオーター(落水荘)と二つ目は南北戦争最大の激戦地、古戦場ゲティスバーグです。

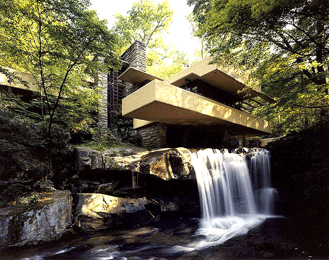

フランク・ロイド・ライト設計:フォーリングウォーター(落水荘)
● 井上昇のいすの話-41 Part 2
いすの話、10月号は就職旅行の続きを描く予定でしたが、ここでどうしても書きたい事が出てきましたので少し中断して書く事にします。人生の中では様々な人と出会います。35才で会社を辞職しクランブルックに留学しなかったら絶対出会えなかった人は沢山いますが、その中でもアメリカで、レイ・イームズに次ぐ椅子のデザイナー、アーロンチェアーのビル・スタンプ以外で最も影響を受け、交流できた尊敬するニールス・デフェリエント氏をもう少し詳しく紹介したいのです。というのも、依頼されていた大学での講義「椅子と人間工学」の内容を日米比較で話そうと編集していて、アメリカの椅子の人間工学の第一人者で椅子のデザイナーの現役でもあるニールス・デフェリエント氏のことをネットで検索していましたらなんと今年の6月8日に85才で亡くなられていました。知らなかったとはいえとてもショックでした。最近はアメリカに行っていないのでお会いする機会もなく過ごしていましたが、ネット上では良く拝見していたのでいつまでも元気と勝手に思い込んでいたのです。クランブルック留学中はもとよりその後、9年前まで20年間毎年アメリカに行き、特に6月のシカゴ、ネオコン全米家具見本市は欠かさず行っていたのでそこでよくあって話したりしていました。その他、卒業後、2回クランブルックでのOB会、日本に来日したときの案内など折に付き合う機会が多くありました。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年07月26日(土) | |
| 「卒業制作に向けて」 | |
|
|
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

Knollベンチ・日本の成田空港でも使われている。
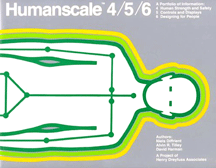
アメリカのヒューマンスケール
研究者の一人
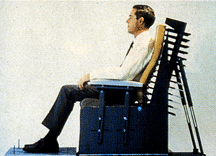
旅客機シートの研究と設計
ヘンリードレフス事務所

Knoll デフェリエントチェアー
1979年、51歳
しかし、本当のおつきあいは、日本に帰って来てからでした。私が帰国後の3年目、大阪の大手オフィス家具メーカーから事務用椅子をデザインする機会がありそれが、結果的に300万脚の生産をする大ヒットの椅子になるのですがデザイン契約はロイヤリティーではなく一回限りの支払い。さらにカタログには創作者である私の名前はどこにもありません。当時も今も日本ではこれが普通なのです。しかし、これがアメリカやヨーロッパでは、椅子のデザイン契約はロイヤリティーが通常のこと、創作者のデザイナーの名前がカタログばかりでなく生産された椅子、一つ一つに誰がデザインしたかクレジットを明記するのが普通です。日本と違いアメリカで事務用椅子のデザインをする事は椅子のデザイナーにとってトップレベルのスターデザイナーのデザイン領域という認識があります。ですから私が私がデザインした事務用椅子のカタログを持参し、アメリカの、デフェリエント氏を含むアメリカのデザイナーの友人にみせたところまず第一の質問が凄いね、ロイヤリティーが沢山入って良いね!といううらやましいという反応です。しかし、カタログを見るうち、inoueの名前がどこにあるの、なんでないのという質問に変わります。日本ではロイヤリティーは難しく、名前入らないのが普通というとこんな質問に変わります。あーそうか!日本人は物まねやっているんだ、だからロイヤリティー契約もしないし、創作者の名前も載せないんだと。軽口たたいたり、軽蔑の態度に出てきます。
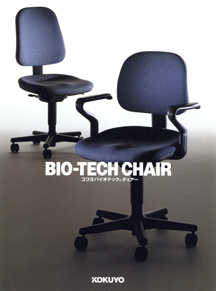
1984年、日本の大手オフィスメーカーK社から発売された私の帰国後のオフィスチェアー
こういう事を言ってくれるのは親しい友人のデザイナーだからでその他の部外者ははなから軽蔑の態度を向けられます。その時、私がどんなに傷ついたか想像にお任せします。日本という国はそんな国なんだ、そういうデザイン後進国なんだ!と馬鹿にされたようなものです。そこで私はもの凄く傷つきました。それは2つのことにです。1つは椅子のデザイナーとしての自分の未熟さと、ふがいなさ!2つ目は日本が個人の創作を尊重しないそんな東洋の後進国であると侮辱された事。海外経験すると一部の例外者を除いて、日本を愛する愛国者になります。自分が馬鹿にされてもそれは我慢するとして、愛する日本が馬鹿にされたら日本男子としてそれはもう我慢が出来ません。少なくも私はそうです。そんなとき当然、面識もあったニールス・デフェリエント氏にも私の椅子カタログを見せた時、こんなアドバイスをしてくれました。決して忘れません。「椅子のロイヤリティー契約はアメリカでも以前からあったものではないんだよ。私達デザインビジネスに関わるデザイナーが団結し、結束してクライアントと交渉し、大変な努力をしたのち勝ち取った契約なんだ。アメリカでもそうしたのだから日本が現在そうでないなら日本でもデザイナーが結束してそのようにしなければそう成らないよ。だから日本もそういう契約が出来る様に日本のデザイナーがアメリカの様に結束してそういう契約が可能になるよう戦いなさいと!そして、あなたが最初にやるべきです」。このアドバイスは決して忘れることができない言葉と成りました。デフェリエント氏から私に直接言われた言葉、アドバイスとして、その後の私の椅子デザインビジネスの「格言」として一生を左右する言葉となりました。
その背景にはもし日本が世界で一流の先進国として自認するなら「契約」も先進国と同じでなければ先進国とは言えない。それはとても恥ずかしいという事ということがあります。愛国者としての日本の為に「日本で欧米と同じ契約で仕事をする」その価値は十分あると思えたしそれが私の使命と確信したのです。アメリカに行かなかったら、アメリカに留学して友人を持たなかったらこんな事すら気付かなかったでしょう。


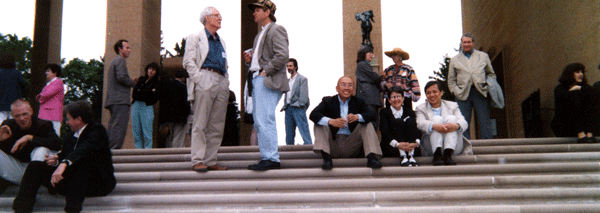
1994年クランブルックキャンパスでの同窓会
その後、K社以降、日本で私の事務用椅子のデザインは大手オフィス家具会社や天童木工、今の木の椅子のデザインビジネスも含めてほとんどロイヤリティー契約か又それ以上の契約でしか仕事をしていません。反面、ロイヤリティー契約できなければ仕事はしないということになり実力の衰えもあるのでしょうが、仕事はロイヤリティーでというと日本では仕事は来なくなってしまいました。しかし、デフェリエント氏のアドバイスを日本で忠実に実務に実行した事で3億円以上の収益を上げ、日本で本格的な量産の椅子で最初で最後の事務用椅子のデザイナーと成りました。そしてそれは今でも「木の椅子」で続いています。
クランブルックの大先輩でもあり、椅子の人間工学のアメリカでの師匠、そして84才で死ぬまで椅子の現役のデザイナーでありつづけたニールス・デフェリエント氏のご冥福を祈ります。ありがとうニールス・デフェリエントさん。あなたの粘りのスピリッツを日本で受け継ぐ事を誓います!また、天国でお会いできるのを楽しみにしています。
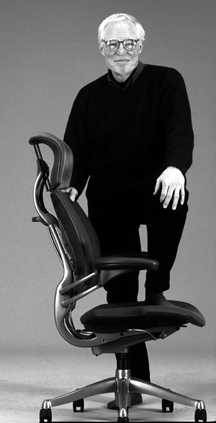
NIELS DIFFERIENT
1928-2013


第一作 フリーダムチェアー 1999年71歳


第二作 リバディチェアー 2004年76歳(左側)、 第三作 ワールドチェアー 2009年81歳(右側)
● 井上昇のいすの話-42 Part 2
ピッツバーグ経由で,フランク・ロイド・ライトの落水荘も見た後、フィラデルフィアの北にある小さな街イーストグリーンビレに到着。日本で言う郊外の小都市です。ノル社の家具工場の隣、敷地内にデザイン開発セクションの別棟があります。場所を確認した上で、近くのモーテルに宿をとります。見知らぬ東部の簡素な田舎町という表現が当てはまり、もしかしたらこんな所に住む事になるのかしらん!まだ就職するか、出来るかどうかも全くわからないのに、まわりの景色に何となく心細さを覚えながらのイーストグリーンビレ滞在です。
Knoll社訪問
翌日、家族をモーテルに残し、手紙で予約していた時間に車で、1人、ノル社の工場に行き、工場のそばのデザイン室を訪問。驚いた事はそのデザイン室のある別棟は外からはあまりさえないごくありふれた、どちらかというとノル社の華やかなイメージとは随分ちがう質素な質素な建物です。しかしドアーを明けて一歩なかに入ってびっくり。そこにはあの素晴らしいノルワールドの世界が目の前いっぱいにひろがっているではありませんか。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年07月26日(土) | |
| 「卒業制作に向けて」 | |
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年12月30日(月) | |
| 「帰国へ」 |

East GreenvilleのKnoll社の工場

Knoll社の工場内部
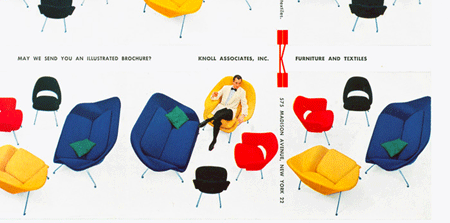
Knoll社のイメージ広告

Knoll社のショールーム
その後、ノル社の名作家具、椅子を作っている工場の中を丁寧に案内、説明してくれました。1年前にハーマンミラーの工場を見た後なのでハーマンミラーと並ぶデザインでは定評あるノル社の工場見学は興味津々。訪問前は面接の事で頭いっぱいで工場まで見れるとは全く考えていなかったので、このノル社の工場見学ツアーは生涯忘れられない素晴らしい体験となりました。今でもはっきり目に焼き付いています。
ノル社の工場ではクランブルックの教師だったハリー・ベルトイアのワイヤーチェアーの製作現場や、フロレンス・ノルデザインのあの素晴らしい大きな大理石テーブルの製作の様子が目の前に広がっています。見学中、グリーンの大理石の楕円テーブル天板が完成し、それを男性4人で目の前を運んでいる時、突如バラバラに割れて、オー、ノーという声とともに崩れ、がっかりした叫び声、ため息が聞こえます。ノル社の大理石テーブルはとても綺麗ですが作るのは大変だなーと見学しながら思った事でした。そして工場見学を終えた後、開発セクションのディレクターに見送られノル社を後にし家族の待つモーテルに戻りました。

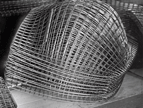
フロレンス・ノル デザインの大理石テーブル:ワイヤーチェアーの工場現場

ハリー・ベルトイアの
ワイヤーチェアー
ノル社を訪問した翌日、ノル社のガーデンチェアーシリーズのデザイナーとして有名なリチャード・シュルツ、愛称、ディック・シュルツさんがたまたま開発セクションに来ていて前日お会いしたこともあって自宅に来ないかとのお誘いを受け、家族でお宅を訪問。シュルツさんはノル社の工場の近く、同じイーストグリーンビレに居をかまえ住んでいたのです。田園の中の広大な敷地の中に住居があり、天気がよかったので庭のテラスで飲み物とお菓子の接待を受けました。息子さんが日本でホームスティしたことがあり、大変お世話になったので、感謝も兼ねて私たちが日本人ということでそのお礼もあって招待したとのこと。家の前の広い庭の中を野うさぎが飛び跳ね、それを犬が追いかける。絵本の中に出てくるような光景が庭には広がっていました。
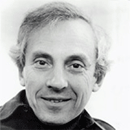
リチャード・シュルツ氏

シュルツ氏デザインの
ガーデンチェアー
ゲティスバーグ
2泊のイーストグリーンビレ滞在の後、デトロイトに向けて帰ります。その途中、同じペンシルベニア州、ゲティスバーグ市にあるゲティスバーグ国立軍事公園によりました。南北戦争の古戦場として有名なゲティスバーグは広大な公園で、南北戦争当時使われていた大砲があちこちに配置されていて古戦場特有のもの悲しさを味あう事ができました。この悲惨な歴史の上に今のアメリカがあることが訪問者に良く理解できる様になっていました。しかし、ゲティスバーグは観光地化されていて、来る時立ち寄ったフランク・ロイド・ライトのフォーリングウオーター(落水荘)訪問ほどの感激はなく広大な戦場跡の要所を短時間でみたあとひたすらデトロイトへドライブ。アメリカ中東部ハンティングジョブのトリップは終わります。
 ゲティスバーグ国立軍事公園
ゲティスバーグ国立軍事公園
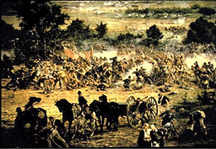 デティスバーグの戦い
デティスバーグの戦い
ノル社の訪問を終えてミシガンの自宅に戻り考えました。ノル社の社内でデザイナーでなく、職員として、製品開発のディレクターの仕事が果たして自分に出来るのか!、又やりたいのか?。答えはNOです。まず社内でのコーディネータとしての仕事をするにはアメリカ人と対等の交渉が出来る語学力が必須です。それは私には無理です。次に自分が一番やりたい椅子のデザインをする為にアメリカに留学、ここに来たのに本来のそれが出来ない。それで良いのか?答えはNOです。私は日本でノル社と同じ規模の大手家具メーカーで11年働いた経験があるのでたとえアメリカだとしても同じような仕事はもうやりたくないしやる意味はない。そして、すでに年齢的に37才になっている状況下で、デザイナーでない仕事を数年働いた後、40才過ぎて新たにデザイナーとして日本で仕事ができるか?これも答えはNOです。遅すぎる。すでに2年、仕事からはなれ、実務からもはなれて自分のデザイン実績が残せない仕事に時間を裂く事はプラスにならない。

現在のイーストグリーンビレ
Knoll社工場

アパートから見えるミシガン州の
冬景色

クランブルック学位授与式。一人一人が学長から卒業証書を呼ばれて手渡される。
● 井上昇のいすの話-43 Part 2
帰国と決めてからまた忙しい日々が始まります。家財の整理とそして帰国の費用の工面。できるだけ生活用具は慎ましやかにしていて家具らしい家具は持っていませんでしたがそれでも2年半の生活でいつのまにか増えているものがあります。その第一は学校での作品。全部すてることは出来ず、卒業制作を含めクランブルックでの作品や必要最低限の生活用具を残した後の家財を梱包し、3ヶ月かかる安い船便で送ります。そして日本からアメリカに来る前、家族に約束したことを果たさねばなりません。それはロサンゼルスのディズニーランドに連れて行く約束です。今では日本にもディズニーランドはありますが当時はアメリカだけです。ロサンゼルスには先に書いた、第2次大戦時、マンザナールの日系人収容所に収容された体験を持つ義叔母が海沿いの町、ハンティントンビーチに自宅を持ち、従姉と生活しています。帰国時に泊まって行くように誘われていたので日本に帰るとき義叔母の家に滞在する事、アメリカに来る時から決めていました。フォトグラファーで従兄、カズ・イノウエの実家です。ロサンゼルスには私にはもう一つ大きな目的がありました。サンタモニカの隣、ベニスビーチにあるチャールズとレイの事務所、「901」スタジオ訪問です。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2012年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2013年01月05日(土) | |
| 「クランブルック入学」 | |
| 2013年02月13日(水) | |
| 「キャンパス生活・独立」 | |
| 2013年03月07日(木) | |
| 「クランブルック生活」 | |
| 2013年04月10日(水) | |
| 「一年目の夏」 | |
| 2013年05月10日(金) | |
| 「ニューヨークからボストン」 | |
| 2013年06月29日(土) | |
|
|
| 2013年07月26日(土) | |
| 「卒業制作に向けて」 | |
| 2013年08月31日(土) | |
| 「プリントメーキング」 | |
| 2013年09月30日(月) | |
| 「卒 業」 | |
| 2013年10月28日(月) | |
| 「デフェリエント氏を悼む」 | |
| 2013年11月30日(土) | |
| 「East Greenville」 |
いざ車を手放してみるとアメリカでは自分の車がないということは翼がない鳥と同じでとても不自由です。帰国準備のわびしさはひとしおです。しかし、1年後輩で台湾からの留学生の親しい友人がその後の諸々の手助けをしてくれて助けてくれました。単身で留学して来た彼は在学中、寂しがりやで学校ばかりでなく私の家族とも何かとおつきあいしていたので私たちの困っている時、親身にサポートしてくれました。こちらもこれはとても助かりました。日本では海外の友人はなかなか出来ませんがアメリカの学校に留学することで台湾や香港、タイ、フィリピン等の同じアジアの友人が出来たのです。海外に留学することでアメリカ、ヨーロッパだけでなくアジアの友人も出来、彼らをとうしてその国の事情、友好と理解を深めることが出来、これはとても貴重な体験になるのです。話せる親しい友人がいればその国に対する理解度が深まります。その意味で日本の政治家、教育者は若いときに海外の留学を経験すべきです。これは理屈でなく体験と経験をとうして他国に対する思いやりと狭い偏狭な視点から離れ、世界の友人との交流から彼らの考え方、日本の外から見える違った発想、意見を聞けるメリットはとても大きいのです。
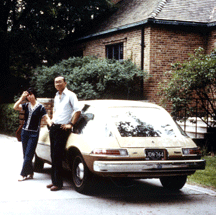
私のアメリカンモータース社
「ペーサー」

アメリカンモータース社
「ペーサー・ツートン」

アメリカンモータース社
「ペーサー・イエロー」
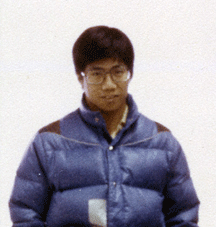
台湾の後輩で親友のティン
荷物も全部日本に送り、車も売却し、アパートの鍵も返し、年も改まった1982年の1月早々、2年半滞在した思い出深いミシガンを去る日が来ます。朝、ポンティアック市に近いブルームフィールドヒルズ市のアパートからデトロイト空港迄、台湾の後輩に家族3人と荷物を車に乗せて送ってもらい空港で見送られ別れを告げました。約5時間のフライトの後、夕方、雪のデトロイト空港から雪のない暖かいロサンゼルスの空港に到着。空港には前もって知らせておいたので義叔母が車で迎えに来てくれました。

ロサンゼルス・ハンティントンビーチ


マンザナール強制収容所(左側)、ロサンゼルス・ディズニーランド(右側)
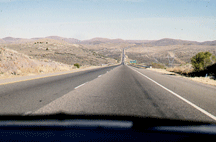
アリゾナのハイウエイ
ロサンゼルスは車なしでは一歩も外へでれません。といって義叔母の足でもある義叔母の自家用の車をいつも使う訳にもいきません。そこで日本に帰国の時のこと考えて、空港でレンタカーを借りることにしましたがここで困ったことが起きました。レンタカーを借りるときクレジットカードがいるのです。クレジットカードがないと車を貸してくれません。その時は無職でしたし日本ではまだカードを持つという習慣のあまりない時代でしたからあいにくカードは持っていきませんでした。それ迄は現金とトラベラーズチェック、ミシガンの銀行の小切手、現金で済ませていましたからそれで済んでいましたが、クレジットカードがないとまるで信用がなくアメリカでは何も出来ないということの現実を知らされます。アメリカにおいてクレジットカードは身分保障の意味も兼ねているのです。みかねた義叔母が保証人になってくれて、年取った義叔母のカードでレンタカーを借りることが出来ました。この出来事は無職の信用のなさ、不自由さ、やるせなさを十分味わいました。
そしてレイ・イームズからのサゼッションのデトロイトからロサンゼルスまでの大陸横断の旅を実行出来なかったかわり、2週間のロサンゼルス滞在中、4泊5日でアリゾナ州のグランドキャニオンとフェニックス市にあるフランク・ロイド・ライトのタリアセン・ウエストを見に出かけることにしました。ロスからフラッグスタッフ経由でグランドキャニオンに直行。壮大なグランドキャニオンの風景を堪能した後、フラッグスタッフに戻り南下してフェニックスへ。途中の景色は映画の西部劇でみるような乾燥地帯とロックマウンテンデザート地帯。まさに東部とは違うもう一つのアメリカがありました。

アリゾナの州境

すれ違った幌馬車隊

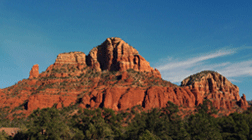
グランドキャニオン(左側)、アリゾナの山々(右側)

アリゾナのドライブ
フェニックスでフランク・ロイドライトの学校、タリアセン・ウエストを見学。タリアセン・ウエストはライトが冬、ウイスコンシンから移動しここに学生と共に過ごしたところです。タリアセン・ウエストもそうですが建物は学生と共に手づくりで作った建物でそう立派といえる作りではありません。しかしその空間は広くフランクロイドライトが建物ばかりでなく家具迄設計し魅力溢れるインテリアが広がっています。アリゾナの砂漠気候にあった赤茶けた塗装がとても印象的です。ウイスコンシンのタリアセン・イーストとタリアセン・ウエスト。どちらが好きかといえば私はタリアセン・イーストです。タリアセン・ウエストはイーストが本家とすると別荘的な要素が強いように思います。
フェニックスから、さらにメキシコに近いツーソンにも寄りました。ここは軍事博物館が有名でしたが見れませんでした。そして途中の街を見ながらロサンゼルスに帰りました。このアリゾナ行きは緑の多い中部、東部とは全く違うアメリカのもうひとつの世界が見れます。このアリゾナ州への旅も東部と同様、広大なのでほとんど毎日ドライブが中心の旅でした。そしてアリゾナの旅からかえってもうひとつの大きな目的の訪問地「901」スタジオにレイ・イームズに会いに1人で行くことになります。

タリアセン・ウエスト外観

タリアセン・ウエスト内観

タリアセン・ウエスト外観

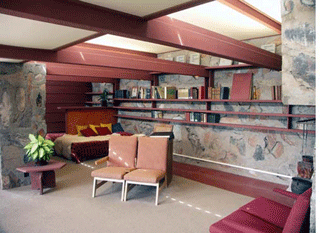
タリアセン・ウエスト内部インテリア(左側)、同 寝室インテリア(右側)