● 井上昇のいすの話-25 Part 2
現在の私の日々の仕事は、木製椅子「腰に優しい」ダイニングチェアー「AWAZA」の販売と新製品の開発、椅子の設計のノウハウを伝授する塾「椅子塾」、その他、椅子に関するセミナーを、企業や大学、工房等のイベントでしたり、ときたま依頼される業界紙誌等への寄稿などをしながら過しています。椅子の販売も椅子のデザイナー自身が生産、販売まで手がける事は日本ではとても珍しく、日々、チャレンジングな、スリリングな日々を過しています。2012年から事務所を青山から麻布に移し、青山で13年続いた椅子塾もAzabu ISUJUKUという形で14年目をスタートしました。塾生との対話の中で改めて、「椅子とは何か?」「何で椅子なのか」、現在までの私と椅子の関わりや、椅子から派生した日本や海外、それぞれの出会いと体験から「椅子の話し-Part 2」として連載するのも椅子のデザインを志す人の何らかな参考になれば意味があるのではないかと思い始め連載することにしました。この文章も「椅子の話しPart 1」と同じく、思いつくままに気楽に書き付けて行くもので気楽に読んで頂ければという程度のものです。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2012年05月02日(水) | |
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 | |
| 2012年06月01日(金) | |
| 「就職」 | |
| 2012年07月07日(土) | |
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 | |
| 2012年09月15日(土) | |
| 「会社を辞めアメリカへ」 | |
| 2012年10月10日(水) | |
| 「デトロイトへ」 | |
| 2012年11月20日(火) | |
|


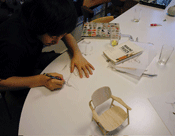
Awaza-LDR 回転イス Awaza 1型 椅子塾
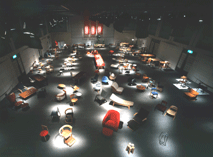
椅子塾展「300Chairs展」
新宿パークタワーOZONE
今から考えると高校、大学の学生時代から椅子をデザインしたいという事は全くありませんでした。ただ、工業高校の機械科を卒業後の浪人時代、横浜、桜木町の近く、紅葉坂にある神奈川県立図書館に1年間、入り浸っていた頃、そこの木製の椅子がとても良く、強く印象に残った程度。浪人時代は私にとって、人生で一番苦しい時でしたから余計強く印象に残ったのかもしれません。この椅子が水之江正臣氏が建築家、前川国男の事務所の所員としてデザインした天童木工の名作椅子である事は後で知る事になります。1年浪人してなんとか武蔵野美術大学、工芸工業デザイン科に入学しました。

水之江正臣氏デザインの椅子




スポークチェアー 豊口克平先生 スバル360 佐々木達三先生
名前をいえば高校は、美術教師で芸大、日本画科出身、結城素明門下の日本画家の水谷春夫先生、大学は豊口克平、佐々木達三、両大先生、社会人になってからは、人間工学のパイオニア、元千葉大学、小原研究室の小原二郎先生。「椅子塾」をやっているのは小原二郎先生から手ほどきされた、初歩的「椅子の人間工学」を私がとても恵まれたように、後輩で、若い方、必要としている人に伝える必要があると考え、その学びの「場」を提供するために始めたのです。
必要な人が必要な時に「椅子の人間工学」を学べる社会人学級、それが「椅子塾」です。
2012年4月5日 井上 昇
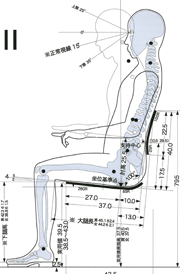

椅子の人間工学と小原二郎先生
● 井上昇のいすの話-26 Part 2
私にとって椅子の魅力に取り付かれたのは、武蔵野美術大学を卒業して、大手オフィス家具メーカーに勤務してからというのが現実です。そして、そのオフィスメーカーに就職するというのも突然決めた事でした。それが後々尾を引くのですが。もともと、飛行機が大好きで飛行機の設計、開発に携わりたいとの単純なあこがれを小さい時から夢に描いていました。しかし、あまり勉強が好きではなく、大学進学は考えず、手に職を付けるには工業高校が自分には向いている、そして、工業高校の機械科に進学すれば飛行機の設計にも携われるのではないかと単純に考え横浜市立鶴見工業高校、機械科に入学しました。小さい時から絵を描くのが大好きで工業高校へ行けばその好きな絵も仕事に生かせるのではないかとのこれも甘い期待がありました。工業高校へ進学した人はわかりますが、工業高校のカリキュラムは実に沢山あって、1年目は絵画の授業はありましたが2年目からはなく、実習が目白押しです。旋盤、鍛造、木型製作、鋳物、機械製図、流体力学実験、機械設計の授業等々。実習は機械油にまみれまさに工場の現場実習そのものです。アルバイトも古河電工での電線工場やクラスメイトの町工場でのプレスあとのバリ取り作業とか、どちらも悪臭と危険な工場現場での仕事の日々。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2012年04月05日(木) |
| 「はじめに」 |
| 2012年06月01日(金) |
| 「就職」 |
| 2012年07月07日(土) |
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 |
| 2012年09月15日(土) |
| 「会社を辞めアメリカへ」 |
| 2012年10月10日(水) |
| 「デトロイトへ」 |
| 2012年11月20日(火) |
| 「ホームステイ」 |

鶴見工業高校・機械製図の授業(右下白:井上)

横浜開港百年記念会館の油絵
高校2年
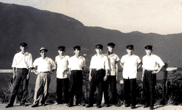 水谷春夫先生と神奈川県高校夏期絵画箱根合宿(左・井上)
水谷春夫先生と神奈川県高校夏期絵画箱根合宿(左・井上)
美術部の仲間と開港百年記念会館
中央
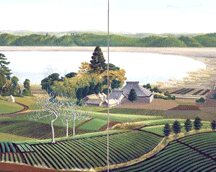
高校の恩師・水谷春夫先生の芸大時代での日本画
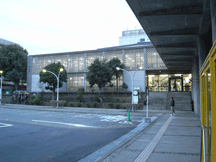
神奈川県立図書館・階段でいつも並んだ場所
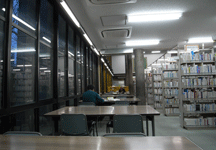
現在の図書館内部・内装は昔と全然違う

武蔵野美術大学時代の油絵・湘南の二宮海岸、まだ西湘バイパスは出来ていず美しい海岸だった。
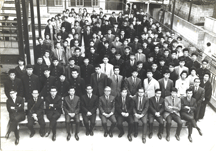
武蔵野美術大学の入学記念写真(吉祥寺校舎、正面中央、原 弘教授)
武蔵美に入学して授業が始まると私は見知らぬ人ばかりでしたが、皆は和気あいあいとにぎやかです。そこでクラスメイトにどうして皆知っているのと質問すると、こんな質問が帰って来ました。お前さんはどこの美術予備校にいっていたんだ。後でわかった事は、クラスメイトのほとんどが美術予備校出身で、1浪と2浪が多く、現役と3浪が少しずつ。ほとんど都内の予備校で一緒だったとか。地方出身の受験生は東京の美術予備校で勉強するため上京、ほとんどが下宿生活の経験者でした。それではみんなよく知っているわけだ。なるほどね。
私は美術大学受験専門の美術予備校がある事も全く知らなかったし、教えてくれる仲間、先生にも恵まれていなかった。それで美術予備校に行かなかった。独学で勉強したとクラスメイトに答えると、お前、美術予備校いかないで武蔵美によく合格したなとの返事。その後、武蔵野美術大学では良き師匠、仲間にも恵まれ、大学生活を送り、就職したわけです。美術大学では好きなデッサンや彫刻、彫金や陶芸、ガラス工芸。そしてインテリア、工業デザインの基礎を学び沢山の思い出を残して無事卒業。デザイナーの道を進む事になりました。
2012年5月2日 井上 昇

入学時:鷹の台キャンパスでクラスメイトと

4年:鷹の台キャンパス,工芸工業デザイン科のクラスメイトと(中段、右端)
● 井上昇のいすの話-27 Part 2
いつの時代も就職は大きなテーマです。選択の仕方では、大きく人生の方向が決まると言っていいでしょう。それは、今も昔も変わりません。今は以前と違って就職難ですし、就職しても定年までと考えることも難しい時代です。派遣などという職業形態は昔にはなかった働き方で精神的にはとてもリスクがあります。
デザイナーの場合、人によっては就職せずアルバイトの延長でそのまま独立する人もいないわけではありません。しかし日本ではやはり将来、独立するにしても、会社に所属するにしても、まず会社に就職し、仕事の仕方、人脈、キャリアを積んで、信用を得るというのが一般的です。大多数の人はそのまま一度きりしかない人生のほとんどをその所属する組織、会社や教育機関、役所で終わります。生活の安定、退職後の年金などを考えると今でもこの道が一番です。そして、大手の会社や商社、銀行等が製造業より、中小企業より給料やボーナス、年金もよく、現役時代だけでなく、退職後もこの現実がはっきり現れます。これは事実です。しかし、以前と違い、今の状況は大手だからといってとても案心できる時代ではなくなりました。
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2012年04月05日(木) |
| 「はじめに」 |
| 2012年05月02日(水) |
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 |
| 2012年07月07日(土) |
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 |
| 2012年09月15日(土) |
| 「会社を辞めアメリカへ」 |
| 2012年10月10日(水) |
| 「デトロイトへ」 |
| 2012年11月20日(火) |
| 「ホームステイ」 |
サラリーマン・デザイナー時代
23才の時オフィス家具メーカーに就職しました。その会社はその当時まだ従業員500人ほどのそれほど大きい会社ではありませんでした。今では2、845人規模の製販一体の大きな会社になってます。しかし、最初から家具メーカーを目指したわけではありませんでした。
もしこの時、自動車メーカーに合格していたらもちろん椅子のデザインもやっていないでしょうし人生も大きく大きく変わっていたでしょう。現実の人生の進路は見方によって偶然の積み重ねのように見えたり、希望どうりいかないで裏街道ばかりのつらい道を歩かされているようにもみえますが、後で振り返ってみればそれはそれぞれにとって一番ふさわしい仕事が与えられ、導かれていると私は思います。たぶん、自動車会社に勤めていたら「独立」ということは私の場合、不可能だったと思います。
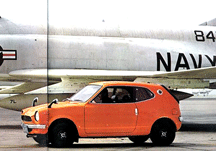
ホンダZ360
就職先を交換した同期生がデザインに関わった車。
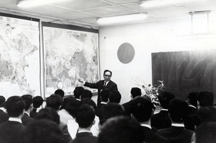
オフィス家具メーカーの入社式。
創業社長の訓示。

入社後の研修合宿・同期生と共に
(後列、左から1番目)
ストア・スペースデザイン部時代
そういう経過でオフィス家具メーカーに就職しました、就職試験はスケッチ・作品提出・筆記試験・面接だったように思います。何とも心もとない記憶ですが会社としてはその時デザイナーは採用する予定はなかったものの、入社したいとの応募が少なからずあったので急遽、入社試験を実施したことをあとで聞きました。私は工業デザイン科をでているのと、面接官が開発部長でしたので合格通知をもらった時は当然、開発部のデザイナーとして採用されたものと思い入社まで疑いもしませんでした。入社まで家具のことも自分なりに勉強し、同じ同業者であるアメリカのハーマンミラー社や、ノル社、チャールズ&レイ・イームズの作品を知り、学生時代に『工芸ニュース』という雑誌の大ファンで、豊口克平先生や剣持勇の活躍も知っていましたから同じ世界で仕事ができると期待に胸が膨らみ、1人で勝手に意気込んでいたわけです。しかし、現実は当人の希望と大きく違っていました。
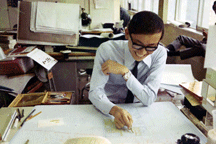
スペースデザイン部時代。
ガリガリにやせていた。

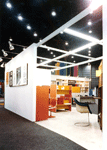

展示会のディスプレイ(大胆に) 「グッドリビングショウ」(晴海展示場)ディスプレイを担当した大きな展示会。


商社のオフィス内 オフィスインテリア
商品ディスプレイデザイン エグゼクディブ木製デスクを設計した。
 アメリカ、NOVA展
アメリカ、NOVA展ディスプレイ賞をいただいた。
しかし、常にその会社の本業の家具の製品デザイン、椅子のデザインがしたい、そのために開発部に行きたいとひたすらに考え、悶々として仕事をしていました。開発部に行けないのならこの会社にいる意味はなく、毎年、辞めることばかり考えていました。そのことを察してくれていた同僚の先輩は「我慢が大事」、最低でも3年は勤めなければ信用されないぞと慰めてくれたり、励ましてくれたり今思えば良い同僚、先輩に恵まれていました。でも気が晴れません。大学の同期はそれぞれ就職したメーカーで工業デザイナーとして活動しています。自分だけがその世界から希望とは裏腹に離れていく毎日の生活に焦るばかりです。そこで、自分は工業デザインの世界から離れない為に、会社の仕事とは別に、個人でも応募出来る工業デザインのコンクールに挑戦することにしました。自転車デザインコンクール、機械デザインコンクール、等に応募、50%の確率で、佳作、3等賞等、受賞。それが会社の社内広報誌などで最初は取り上げられ社内ではちょっと知られた「顔」「存在」になっていました。しかし、その当時の日本で、工業デザインコンクールの最高峰は、毎日新聞主宰の「毎日工業デザインコンクール」です。コンクールにチャレンジしたことある人は理解出来ると思いますが表彰式に出席しますと、佳作や、3等賞は1等賞に比べて、賞金もさることながら表彰式での、対応、華やかさ、意味、が全く違います。コンクールは1等を取らなければ意味がないのです。オリンピックの金メダルと同じです。佳作や3等賞ばかりいくらとっても仕方がないので、焦点を「毎日工業デザインコンクール」一本に絞りチャレンジ。そして、コンペにチャレンジしてから4年目、「毎日工業デザインコンクール」、B部門の特選1席を獲得。この賞の獲得が私の職業人生を大きく変えてくれることになりました。
2012年6月1日 井上 昇
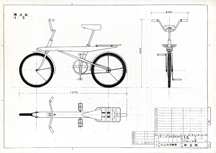
自転車コンクール:3等受賞作品
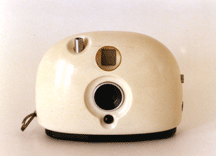
機械デザインコンペ:佳作受賞作、
コンパクトカメラ

毎日デザインコンペ:B部門特選1席
受賞作品・フロートユニット
● 井上昇のいすの話-28 Part 2
「毎日工業デザインコンクール」授賞式が皇居横の毎日新聞本社であり、招待状がきて出席。授賞式の席に着席すると我々一般部門のA部門、B部門の受賞者の他に、現役で活躍し、功績を認めて表彰する「毎日デザイン賞」という表彰式も同時にあり、名のあるデザイン界の重鎮が座っています。雰囲気としてはそちらの方が重みが大きく、我々コンクール受賞者はその後の席につき、デザイン界の重鎮の「毎日デザイン賞」の表彰を観て後、表彰を受けました。ということで、私の前に座っていた人は椅子のデザインで有名な、長大作、水之江正臣、松村勝男の御三家とそれぞれの奥さん。その他にテキスタイルの大御所、粟辻博と奥さん。私はデザイナーの駆け出し、それも自分の望んでいるデザインのポジションにほど遠いところにいた時でしたからそのスターの後ろ姿は、まばゆいばかりの光景です。今でもそのシーンははっきり覚えています。

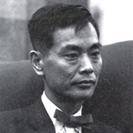
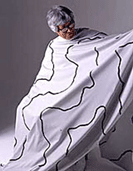
左から長 大作・松村勝男・粟辻 博
| ● バックナンバー |
|
タイトル
|
| 2017年のいすの話 |
| 2016年のいすの話 |
| 2015年のいすの話 |
| 2014年のいすの話 |
| 2013年のいすの話 |
| 2011年のいすの話 |
| 2010年のいすの話 |
| 2012年04月05日(木) |
| 「はじめに」 |
| 2012年05月02日(水) |
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 |
| 2012年06月01日(金) |
| 「就職」 |
| 2012年09月15日(土) |
| 「会社を辞めアメリカへ」 |
| 2012年10月10日(水) |
| 「デトロイトへ」 |
| 2012年11月20日(火) |
| 「ホームステイ」 |

テレホンスタンド
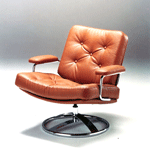
第1作目
ラウンジチェアー(Gマーク)
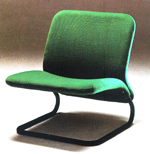
第2作目
製品になったが売れなかった失敗作
私は11年で会社を辞めましたが、同期の営業の人達で定年までいた人は、ほとんど部長や、取締役までなっていることをみても会社とはそういうものと思いました。

第3作目
パイプラウンジ
ベストセラーチェアー

第4作目
システムタンデムシーティング
ベンチ
新しく上司になった先輩はデザインより管理に向いていたタイプだったこともあり自分では前の部長のように自分で製品のデザインをしません。そこで、私の方から積極的に椅子のデザインをやりたい旨、申し出ます。それもしつこく。そのしつこさも効果があってパブリックチェアーのデザインをして良いことになりました。30歳にして念願の椅子のデザインを担当することになったのです。その喜びは当人でしかわからないと思います。椅子のデザインを目指して7年目、その念願がやっとかなったのですから。ですから私のライフワークである椅子のデザインは、30歳から始まりました。「自分は人より10年遅いと考えれば、焦る事はない」との、恩師である佐々木達三先生からの訓示もロースターターの私にとって、焦りながらも多いに慰めとなった言葉です。恩師というものは有り難いものです。
椅子をデザインするにはそれをする時間と形にする試作費用が必要です。担当するということは、時間も試作費も使えることを意味します。もちろん上司の承認を得てのことですが。30の時から椅子をデザインしまくります。3〜4ヶ月で一作のペースで。全部が製品になるわけではありません。しかし、万を持してデザインした第1作目のラウンド・ラウンジチェアーがいきなりGマークに選定されます。これはラッキーなことでした。2作目がボツ。3作目のラウンジパイプチェアーがGマークは取れなかったもののヒット商品になります。4作目は3作目のタンデムシーテイング。5作目はソファ。6作目はその木製タイプ。7作目のパイプソファは製品になったものの短命商品。その他、丁度、デンマークのカジュアルなチェアー「イノベーター」がとても人気があり、外部デザイン事務所、渡辺力さんの事務所と組んでカジュアルな椅子を担当。私はパイプ椅子の方をデザインします。この企画は大失敗に終わります。成功率、コンペと同じく50%程でしょうか。
そんなことをして2年ほどたった頃、念願の事務用回転椅子のデザインプロジェクトが企画され、その担当を任されることになぜかなります。それが、日本で初めてのコンピューター用事務用椅子、OA(オフィスオートメーション)チェアー、後に「27型」と呼ばれる事務用椅子です。その当時、日本でもIBMが日本で汎用コンピューターを販売し始めます。今の若い方に取っては信じがたいことですが1台、数億円、数千万円もする時代でした。そこで使う事務用椅子がそれまでの安っぽい事務用椅子では様になりません。それまで、デスクと事務用椅子の価格差はデスクの1/2が椅子の価格でした。高くてもせいぜい2万円どまり。それが、価格が倍、4〜5万円台の高級な人間工学に基ずくOAチェアーのニーズが日本でも出て来たのです。
アメリカでは一足先に、ハーマンミラーやスチールケース社で開発されたエルゴノミクスチェアーがよいビジネスになっていました。この流れは日本にも来る。私が勤めていた会社はいち早くIBMを導入していましたし、アメリカの家具会社の製品ライセンス生産をもやっていましたから先見性がありました。
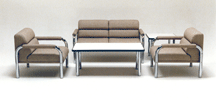
第5作目
パイプソファ
ベストセラーソファ
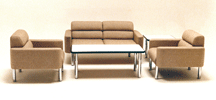
第5作目
パイプソファのバリエーション

第6作目
パイプソファの木製タイプ
座と背は共通

第7作目
ソファベンチ
あまりヒットしなかった。

第8作目
カジュアルパイプチェアー
キャンバスタイプ

第9作目
カジュアルパイプチェアー
フルカバリングタイプ

郵政省:仕分け椅子 6万脚納
この事務用椅子の開発が32歳から34歳の半ばまで担当します。この開発に関わったことで椅子の人間工学の研究が大きなテーマになります。そこで当時、椅子の人間工学の研究に意欲的に取り組んでいた、千葉大学・小原二郎研究室に座りの研究の指導を受けに研究室に通うことになります。具体的には千葉大学・小原研究室での人間工学研修に会社から派遣、自動車メーカーの人間工学を研究している人達やデザイン事務所の人達と一緒に研修を受けました。これが、私の椅子のデザインと日本人の人間工学との運命的な出会いになりました。小原先生にも目をかけていただき面倒をみて頂きました。それは私というより開発部の担当として将来的な弟子と期待して目をかけてくれたのです。
それを私は裏切ることになります。というのは、「27型」を完成させていくうち開発部での自分の位置が見えなくなって来たことです。元々、遅く開発部に遅れて来ただけでなく30代も半ばとなるとその後の進路を選択しなければならない時期にさしかかります。社内では管理職になるか、専門職になるか。管理職になるにはすでに3歳年上の優秀な部長がいます。といって、その当時の私の場合、専門職でこのままデザイナーを社内で続けていくとしても将来がとても不安定な状況しか見えてきません。そして、何よりも「27型」エルゴノミクスチェアーの開発に携われば携わるほど自分の実力のなさ、外国とのレベルの差がはっきりして、将来デザイナーとしてもしやっていくとするならもっと勉強をしなければとの思いが強くなっていくことを押さえることが出来なくなっていきました。30歳から4年間、椅子のデザインを猛烈にやって来てエネルギーを出し尽くしていたという飢餓感もありました。それで今度はエネルギーをどんどん吸収していかなければやっていけない状態に精神的に陥っていました。それには、ゆっくり休養を取りながら、学び直すこと。要するにサバティカル・タイム。リフレッシュの時間が欲しかったのです。しかし会社勤めの平サラリーマンには夢のまた夢。会社には1年間の留学制度がありましたが、行って来た先輩はほとんど辞めていきます。その理由は色々ありますが留学してかの国と日本の国との労働の価値観の差の違いに目覚め帰国後アダプト出来なくなってしまう。それが本当の理由ではないでしょうか。
2012年7月7日 井上 昇

27マネジメント:試作品
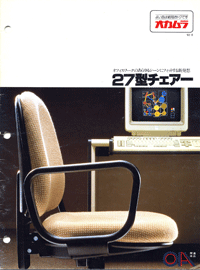
27チェアーカタログ

27チェアーと
IBM仕様チェアー(左)
● 井上昇のいすの話-29 Part 2
「椅子の話」8月はお休みしてしまいました。京都夏期塾で一ヶ月、四条、烏丸からほど近い新町通り奥の路地町家で「Kyoto ISUJUKU」をしていました。京都駅から歩いても30分ほど、京都の一番良い場所で京都の伝統的町家に住んで、椅子塾をし、伝統的な技・食・家・工芸に属する家具作りを工房を訪ねたり、見学したり、京都を見てまわりました。旅行と違って滞在すること、生活することで京都を生活から、肌で感じる、このことが一番の目的であり、また成果でした。最後に京都椅子塾・課外授業がありイタリア、ミラノ在住のイノダ・スバイエ+INOUE、ジョイントセミナーには京都、大阪から30人もの人が集まり良い締めくくりになりました。この京都滞在一ヶ月はある意味で、久しぶりのサバティカルタイムとなりました。長い間、仕事を続けるとしたら、時々、サバティカルタイム=休養が体にとっても脳にとっても必要です。エネルギーを出す一方ですといずれエネルギーは枯渇してしまいます。時々、充電が必要なのです。以前の私は、会社を辞めて、2年半のデトロイト郊外の大学院留学がそれに当たりますし、それ以後20年、毎年行っていた6月のアメリカ出張がそれに当たります。サバティカルタイム=休養!。長く仕事を、ハイレベルで続けるとしたら、クリエーターには必要不可欠なのです。
ということで本題に戻ります。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
|
|
| 「はじめに」 | |
| 2012年05月02日(水) | |
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 | |
| 2012年06月01日(金) | |
| 「就職」 | |
| 2012年07月07日(土) | |
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 | |
| 2012年10月10日(水) | |
| 「デトロイトへ」 | |
| 2012年11月20日(火) | |
| 「ホームステイ」 |
会社を辞めアメリカへ
もう、32年前のことになりますから私が会社に在籍していた時の社長や、上司、同僚もほとんど定年、もしくは亡くなられた方も多く、会社環境も今とずいぶん違います。今では転職は珍しいことではありませんが、以前は、会社をやめるというのは崖から飛び降りるというと少し大げさに聞こえますがそのぐらいの決断と勇気が必要な時代でした。終身雇用の時代で、会社の評価は勤続年数が評価基準の90パーセントほども占める時代ですからなおさらです。それも、結婚して子供もいるとなると!
このような事情もあります。会社で年齢的に35歳ほどになってくると人事の選別の時期に入ってきます。実務に残るか、管理の仕事に就くか!。その時は管理職の仕事は3歳年上の優秀な先輩がなったばかりでその方向の道はすでにありません。実務に残る方は立場上、管理する立場でなく管理される側になりますが日本の会社は伝統的に技術者はあまり重要視しません。
業績評価も減点主義的な傾向が強く、いくら業績を上げても失敗もすればそちらの評価の方が重視されやすい。仕事に精を出せば出すほど失敗もする訳で、成功は当たり前、失敗はマイナス評価加算されるということになります。ということは、何も仕事をしなかった人の方が失敗もない訳ですからかえって評価が高くなるということになります。日本の官僚と同じ処世術です。仕事が評価されるという期待があるから一生懸命やる者にとって、仕事やればやるほどマイナス評価が増えて行くという現実。ジレンマです。デザインという職業は専門職で会社の組織の中では主流にはなれません。しかし、デザインという仕事の良い所、素晴らしい所、それは独立できる職業ということです。
その当時、独立をするのだったら35歳がぎりぎりのリミット、年齢だと言われていました。いまも、私の経験ではかなり当てはまるかとは思います。独立するとしたらフリーランスになるわけですからもっと実力をつける必要があります。それと英語力も身につけなければなりません。その為には海外で勉強しなおすこと。会社の留学制度は1年で、帰ってきた先輩が2年はいたかったという話もよく聞いていましたから最初から2年はとの思いがありました。それとは別に留学でなく海外で働くという選択肢もないではありませんが、語学力で無理。2年滞在できるビザを取得するには2年制の美術大学院しか選択の余地はありません。フルブライトなどの留学支援制度を利用するには準備していた訳ではないのでとても語学力では無理。
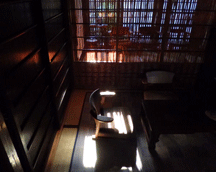
京都・路地町家の朝

京都夏期椅子塾
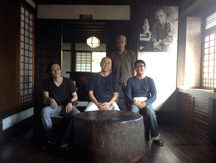
河井寛次郎記念館

京都椅子塾・課外授業
資料を取り寄せ、入学願書・推薦状を作品集とともに1月頃送ったところ、4月ごろ、ミシガン州アンナーバー市にあるミシガン大学付属英語学校に9月の入学前に学んでくるという条件付きで入学許可が届きます。その夏期講座の開始が7月1日。英語学校に入学の申請をして許可を得、6月25日の給料日、最後のお給料をもらって退職。ボーナスは7月10日、ボーナス日を目前にやめなければ英語学校に入学できないという悔しさを胸に、家具デザイナーとして20代と30代の半ばを過ごし、11年つとめ、育てていただいた職場を去った訳です。
入学の推薦状を大学時代の恩師、豊口克平先生と佐々木達三先生お二人に頼んだときの言葉。豊口先生は真面目に仕事すれば必ず食えるから心配するなと励まされ、佐々木先生からは会社勤めはお給料と仕事をもらえるんだから結構なことじゃないか、フリーランスは定年になってからやれば良いんだ、もったいないことしたなと!。
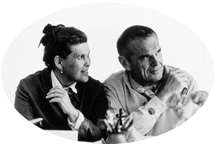
レイ&チャールズ・イームズ

イームズ・チェアー
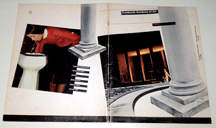
クランブルックの学校案内書

クランブルック校内
最後に私が担当した、OAチェアーの意匠登録申請で、創作者の名前に私の名前を入れて下さい。そういうと、社長は必ずそうする。約束するとのお言葉。実際に2年半後に帰国すると、その私が担当した日本で最初のOAチェアーがその大手家具会社の大ヒット商品になっており、Gマークの部門賞にも選ばれすごいことになっていました。しかし、私はもう社員ではありません。しかし、創作者の所に私の名前が入っていることを確認。このことがその後、私の椅子のデザイナーとしてとてもとても大きな意味を持ってくることになります。でも会社を去る時はそんなことは予想もしませんでした。
最後に辞去するとき、創業社長が玄関迄見送ってくれ、玄関に膝を付き、私の靴をつかみ、くるっとまわして履きやすいように置いてくれ、見送ってくれました。なんと言う対応。ただの平社員の退職の挨拶にこの対応。最後に帰国したら挨拶に来なさい!。
会社を辞めるということは親しい同僚とも別れることをも意味します。このことはとてもつらいことでした。送別会を他に留学する同僚と一緒に開いていただき、会社を離れたのでした。このあと、会社に勤めてお給料をもらいボーナスを頂くという生活は、一年間、短大の教授として在籍した例外をのぞいてなくなり、フリーランスの生活に入ります。
会社を辞めて悩んでる余裕もなくアメリカへの渡米準備に明け暮れます。その時は藤沢に住んでいたのですが、いつも散策していた江の島が見える鵠沼の海岸で、海の向こうのアメリカに思い馳せながら夕陽にくれる富士山、箱根の層雲山、二子山、伊豆の山々に別れを告げました。このとき以来14年間住んだ想い出ふかい湘南の海と藤沢と富士山ともお別れです。会社を退職し、無職になり、最愛の家族とも離れこれから2年間の先の見えないアメリカ生活、これで良かったのか、34才の時の決断です。
羽田には家族と会社からスペースデザイン部の同僚、大学の時の一番の親友の2人だけの4人に見送られて、思いリュックによろけながらゲートに入り、1人寂しく初めてのアメリカ本土に旅立ちました。円レートが270円の時です。
その後、この羽田まで見送ってくれた2人の親友はそれぞれ若くして病気でなくなり、一番の逆境にあって送られた当人が生き残っている、恩を返せないのが残念でなりません。
2012年9月15日 井上 昇
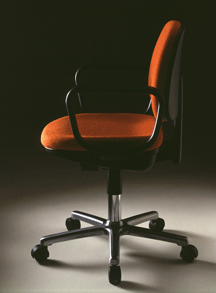
27型OAチェアー
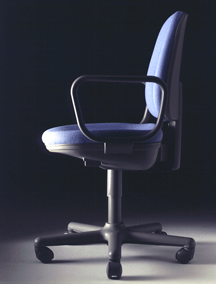
27型OAチェアー・ハイバック
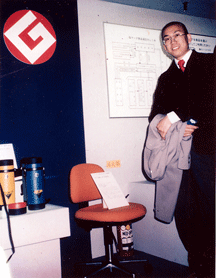
Gマーク部門賞受賞の横で
2012年10月10日(水)
● 井上昇のいすの話-30 Part 2 |
羽田を発ってサンフランシスコへ。デトロイトへの直行便がない時だったのでサンフランシスコ経由で行くことに。サンフランシスコ迄の飛行機の中は日本人もたくさん乗っていて外国へ行くという感じがしません。サンフランシスコ空港には夕方、到着。空港ではクランブルクで2年前に留学しデザイン事務所に勤めていた先輩が空港に迎えにきていただけるという予定だったのがなぜかタイミングが合わず会えません。初めてのアメリカということもあり、電話のかけ方もそのときはどうして良いかわからず、英語力のなさもあって、後で考えれば何ということのないことにパニクッテいたわけです。サンフランシスコに1泊して、その先輩と会って学校のこと等アドバイスをうけて、翌日デトロイトに発つ予定をたてていたその予定ができなくなり、急遽、ホテルに泊まることに。空港の案内所で相談し、身分相応に市内に安いホテルを予約。タクシーで夕闇の迫るサンフランシスコのダウンタウンの安宿に着き、お金を払ってチェックイン。しかし、食事に出ようと外に出ると、ホテル前には浮浪者がたむろしています。治安の悪い地区にホテルを取ったことにその時はじめて気づきます。そういえばホテルもよく見てみると殺伐とした雰囲気です。とたんに、そのままホテルに滞在することに危険を感じ、急遽、1時間でチェックアウト!タクシーでまた、夜のサンフランシスコ空港にもどり、航空会社にデトロイト行きの最終便に変更し乗りたいと必死に交渉。
| ● バックナンバー | ||||||
|
タイトル
|
||||||
|
||||||
| 2010年のいすの話 | ||||||
| 2012年04月05日(木) | ||||||
| 「はじめに」 | ||||||
| 2012年05月02日(水) | ||||||
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 | ||||||
| 2012年06月01日(金) | ||||||
| 「就職」 | ||||||
| 2012年07月07日(土) | ||||||
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 | ||||||
|
||||||
|
デトロイト行きに乗れることにほっとしている間もなく、若いハイヒール姿の美しいスチューワデスが最後の乗客荷物である私の重いリュックサックを片手でひょいと持ち上げ、飛行機直通の荷物台までスタスタ運び、投げ込む姿を見て、そのパワフルなプロ精神になぜか感動。荷物を確認後、急いで飛行機に乗り込みました。
サンフランシスコからデトロイトまでの国内便は当然のことながら日本人はほとんどいません。アメリカの奥地に向かっている!この時は英語もあまり話せず、見ず知らずのアメリカに単身で飛び込んでいく不安感と、この先のアメリカでの生活のことを考えると飛行機の中ではほとんど眠れませんでした。
この留学後、毎年20年間にわたってアメリカにほとんど一人で出かけ、レンタカーで全米各地を飛び回るのですが、最初のこのフライトの時の心細さだけは格別でした。

サンフランシスコ

タクシー

サンフランシスコ空港
クランブルックに入学する条件は入学前に英語学校に入ることでした。私が選んだのは、同じミシガン州の中でデトロイト郊外、アナーバーにある英語学校。ミシガン大学のキャンパス内にあります。ミシガン大学はリングスティック、即ち言語学では全米の大学の中でもトップレベルの大学です。ミシガンメソッドという語学の教え方に評判のプログラムを持っていて語学を学ぶならミシガン大学内にある英語学校というのは自然の流れでした。
夜行便でしたので早朝、デトロイト空港に着きます。閑散とした飛行場を出てアナーバー迄、バスで行こうと空港駅前のバス停に1人待っていますがいっこうにバスがくる様子がありません。それもそのはず、アメリカでは自家用車か迎えの車で移動するのが普通ですから数時間に1本のグレイハウンドバスを待つ人はほとんどいないのです。目の前を見るとタクシーが見えます。タクシーの運転手もそれがわかっているのでこちらがバスをあきらめて乗ってくるのを辛抱強く待っています。仕方なくタクシー料金はいくらかということを確認して乗車。広大なコーン畑を左右に見ながら初めてのアメリカのドライブなので本当に目的地に着くのか余計な心配しながらアナーバーへ。40分ほどで到着。市内のどこで降ろすのかというので「市内の一番良いホテル」の前へ!。キャンパス内の奇麗なホテルへチェックイン。部屋に入ると普段着のままベッドに倒れ込み目が覚めてみると日にちが変わっていて一昼夜寝ていたことに気付きます。これがアメリカでの第一日目。

デトロイト・ダウンタウン

アナーバー

ミシガン大学
英語学校
アナーバには学校が始まる2日前に着き、2日ほどホテルに滞在後、学校が始まるとその学生寮に入ることになっています。夏のキャンパスは休暇中なので閑散としています。日本人にもほとんど会いません。しかし、学校の始まる日になると沢山の日本人がグループで来たり、一人で来たり集まってきます。グループの連中は楽しく騒いでいますが、1人で留学してきた連中は顔はこわばり緊張した面持ちで入学手続きをします。私もその1人です。やはり異国で日本人に会うのはホッとするものです。英語学校には、アジアからは日本以外に、韓国・台湾・タイ、南米からはメキシコ・エクアドル・コロンビア・ブラジル、中東からはイラン・サウジアラビア等から学生が来ています。これらの学生が共同生活することで日本では経験できない交流と英語学校生活が始まります。寮は2人部屋が基本ですが少しお金を払い独り部屋を取ることが出来ました。クラス分けではテストの成績順で5段階に分けられます、アメリカ留学も急に決め、英語をあまり勉強していなかった私は下から2番目のクラスに編入されます。一番上は、ミシガン大学のロースクールに入学するため、大手銀行や製鉄所の選抜で選ばれ留学する人達が中心で英語学校は形ばかりで入ってきた人達が多く、毎日、テニスばかりやっています。それに引きかえこちらは余裕なく10歳ぐらい若いアジアや南米、イランの人達と毎日過ごします。
英語学校在学中、大手銀行からの留学生からは「井上さんその英語力では大学院入っても追い出されんじゃないの!」といわれたりしましたが、英語学校の留学生担当の女性職員からは「アメリカ人から見ればこの学校の5段階の1番目も5番目も同じですよ!」。あなたはすでに大学院の入学許可証を持っているのだから余計な心配しなくていいと。この言葉にどんなに勇気づけられたことか。英語学校滞在中の7月4日の独立記念日、近くの公園で花火大会がありクラスメイトと共に見に出かけます。花火を見ていて、なぜか涙がぽろぽろ出て止まりません。11年勤めた会社を退職し、無職・無収入になり、デザインの仕事も離れ、日本に家族を残し、1人で英語学校で先の見えない日々を過ごしている。花火を見ていたとき急に現実を思い出し涙が止まらないのでした。私の人生最悪の時代の英語学校生活でした。
1ヶ月半の英語学校も終わりに近づき、8月の半ばに終了です。クランブルックは9月の半ばから始まります。その間の約3週間、イリノイ州の農家にホームスティすることに日本で手続きをしていました。運転免許証は日本で取っていましたが更新し忘れもっていません。でもその失効した免許証をもっていくと経験有りということで筆記テストと実地運転テストを1回すればOKということになり、英語学校の日本人の友人の車で半日、練習させてもらい、試験官の車にて指定した道路を走ります。最後にバックで車庫入れして実地テストは合格。筆記テストは2回目で合格。オフィスに行くと仮免許のカードをすぐ出してくれ運転出来ます。その手続きの早いこと。車なしでは何も出来ないアメリカでは車に関してはすべて自己責任です。ということで日本で失効した運転免許証をアメリカでほとんどタダ同然で再取得したのでした。その次は車を買うことです。アメリカは車なしでは身動き出来ないので中古車を買うことにします。地元新聞には車を売る小さな広告が沢山載っています。個人が自分の車を売りに出すのです。2回ほど広告の主に連絡を取り、アメリカンモータースの中古車「ペーサー」を買います。フォルクスワーゲンのビートルを大きめにした形です。安いのと形が気に入り買いました。日本車、特にホンダのシビックを買いたかったのですが新車はもちろんのこと中古車も人気があってとても高く買えませんでした。英語学校が終わる時までに、なんとか車も手に入れ英語学校も終わり、クラスメイトともお別れです。
2012年10月10日 井上 昇

ファードミュージアム

ファードミュージアム・T型自動車

ファードミュージアム・飛行機
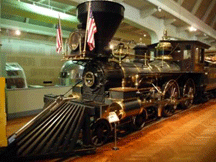
ファードミュージアム・機関車
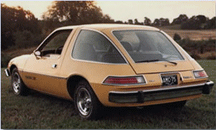
アメリカンモーターズ・ペーサー
● 井上昇のいすの話-31 Part 2
ホームステイ先はウィスコンシン州ベロイト(Beloit)という町の郊外の農家に約2週間半滞在。ベロイト郊外は典型的なアメリカ農村の町です。映画のフィールド オブ ドリームの世界です。シカゴからも近く州都のマデソンに行く途中にあります。
アナーバーからシカゴ迄約5時間、シカゴから約2時間、合計7時間ほどのドライブです。アメリカでの初めての長距離ドライブ。それで早朝に寮を出発。ミシガン大学構内を走り信号を左折した時、いきなりサイレンがしてパトカーに捕まります。早朝で車が全く走っていなかったので青になる直前に発進したのが物陰に隠れていたパトカーに見つかったのです。銃を持った警官は車から出て車に手を付けろと命令します。拳銃を警戒するあの映画のシーンそのままです。そして反則切符をきり警察署に出頭しろと言います。困ったなと思いつつこれからウィスコンシンに行き、9月にはミシガンにもどるからその時、警察署に行きますと返事して了解を取り解放されます。日本の警察と違いアメリカのパトカーはショットガンを持ち、腰の拳銃をガチャつかせての取り調べには肝を冷やしました。でもこの痛い経験はアメリカでの2年半の生活の中で常に運転に気をつける大きな戒めとなり事故もなく過ごせたことは結果として私には必要な経験だったのかも知れません。
後日、警察署に出頭したとき、警察官に、「only a few minutes」ほんの数分待てば捕まらなかったとこんこんと説得され、罰金を払ったのでした。
| ● バックナンバー | |
|
タイトル
|
|
| 2017年のいすの話 | |
| 2016年のいすの話 | |
| 2015年のいすの話 | |
| 2014年のいすの話 | |
| 2013年のいすの話 | |
| 2011年のいすの話 | |
| 2010年のいすの話 | |
| 2012年04月05日(木) | |
| 「はじめに」 | |
| 2012年05月02日(水) | |
| 「横浜市立鶴見工業高校と浪人時代」 | |
| 2012年06月01日(金) | |
| 「就職」 | |
| 2012年07月07日(土) | |
| 「念願の椅子のデザイナーへ」 | |
|
|
|
|
| 2012年10月10日(水) | |
| 「デトロイトへ」 |
ホルメス農場はトウモロコシ・ソイビーン(大豆)を主に作る典型的なアメリカ中部の大農場です。乳牛も何匹か飼っていました。子供達は独立して家にはいなくて奥さんは看護婦として勤めに出ていて昼間はいません。部屋は子供部屋だった屋根裏部屋に住まわしてもらいます。畑は収穫時期でもないので特別仕事らしい仕事はありません。もっぱらホルメスと一緒の時は、教会に一緒に行ったり、傷痍軍人協会の集まりや、地元の農業祭のようなイベントに連れてってもらったり、庭の芝刈り機で芝を刈る以外はあまりやることがありません。もっぱらホルメスとのおしゃべりが主。自由時間が多いのでウィスコンシンには沢山あるフランク・ロイド・ライトが設計した住宅、建物そして自身が作った学校、タリアセンに行ったり、現地の日本人に会ったりしているうちにあっという間の3週間が過ぎます。このホームステイでの経験はアメリカの本当の良さは都会でなく郊外、それも農場であること。あのフィールド オブ ドリームの世界です。アメリカは農業国であることを身を以て知ったことでした。近くにキッコーマンの醤油工場がありそれが話題にもなっていました。アメリカ人は大豆は家畜の飼料として生産していて人間が食べるという習慣はなく、その飼料からソースや豆腐を作ったり、日本人は大豆を食べるんだってねとホルメスに言われたり、彼らにとっては家畜飼料である大豆を日本人は食べる、そのことがよくわからないというそういう時代でした。今では醤油や豆腐、寿司がアメリカのどの田舎の郊外の町に行っても売っているということなど想像できない時でした。変われば変わるものです。そしてフランク・ロイド・ライトの私塾学校タリアセンは強く印象に残ります。

アメリカのパトカー

トウモロコシファーム

ソイビーン/大豆畑

キッコウマン工場
建築設計の仕事がほとんど来ない10数年間、タリアセンにこもり3つの代表的な仕事をします。1913〜1923日本の帝国ホテル。1930年代後半カウフマン邸(落水荘)とジョンソンワックス社です。この食べられない期間、タリアセンにこもって時期を過ごし見事に70代になって表舞台に返り咲き91歳(1959年)で死ぬまで現役で活躍します。私も52歳で事務用の仕事が全く来なくなり空白が10年以上続きましたが椅子塾で時間を過ごしつつ、現在は木製のダイニングチェアーで復活、デザインばかりでなく販売まで踏み込み、椅子の仕事を楽しくしています。

タリアセンの
フランク・ロイド・ライト

タリアセンの教室
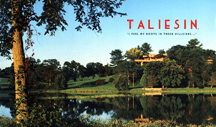
フランク・ロイド・ライトの自宅


ジョンソンワックスの外観 ジョンソンワックスの内観
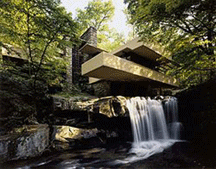
カウフマン邸・落水荘